ハインリッヒの法則とは?現場で活用できない理由と定着のポイントを解説
「ハインリッヒの法則」は、現場のリスク管理や安全対策に役立つとされています。しかし実際には、雰囲気や対応が原因で、この法則をうまく活用できていない現場も少なくありません。ハインリッヒの法則の基本から、定着に向けた課題と改善ポイントまでを整理します。
ハインリッヒの法則とは?
現場の安全管理やリスク管理に、ハインリッヒの法則を活用したいと考える企業もあるでしょう。活用方法を知るには、まず基本の整理が必要です。ハインリッヒの法則とは何なのか、類似した法則との違いも絡めて解説します。
労災発生についての法則
ハインリッヒの法則は、1931年にハーバート・ウィリアム・ハインリッヒが提唱した災害(事故)に関する法則です。この法則によれば、1件の重大事故の背後には29件の軽微な事故があり、さらにその背後には300件のヒヤリ・ハット(事故寸前の事象)が存在する(1:29:300の法則)とされています。
ハインリッヒの法則は、重大事故を防ぐためには、日常的に見られる小さな異常やヒヤリ・ハットを見逃さず、確実に対策することが重要であることを示しています。企業のリスク管理においても、ハインリッヒの法則は重要です。深刻な労働災害や重大なミスを引き起こさないよう、小さな異変に気付く体制が求められます。
似た法則との違い
ハインリッヒの法則と似ているものに、「バードの法則(事故トライアングル)」があります。バードの法則はハインリッヒの法則を拡張し、1件の重大事故の背後には10件の軽微な事故・30件の物損事故・600件のヒヤリ・ハットがあるとする法則です。
ハインリッヒの法則は主に労働災害に焦点を当てていますが、バードの法則はより広範な事故やトラブルに適用されます。両者は重大事故の背後には多数の軽微な事象が存在するという点で共通しており、予防の重要性を強調しているといえるでしょう。
ハインリッヒの法則が活用できない理由
ハインリッヒの法則は、現場の安全文化が土台になって初めて効果を発揮します。しかし実際には、ヒヤリ・ハットの報告が進まず、報告されても改善に結び付かないといった問題もあります。なぜ現場で活用しきれないのか、理由を整理してみましょう。
「ヒヤリ・ハット」を報告しにくい風潮がある
現場でヒヤリ・ハットの報告が進まない主な理由として、報告者が責任を問われることへの不安や、報告しても評価されない文化が挙げられます。危ないと思った事象を報告しても、逆に叱責されたり「やっかいなメンバーだ」と評価を下げられたりしては、報告する意欲がなくなるでしょう。
組織内で心理的安全性が欠如している状態が、ヒヤリ・ハットの共有を阻害しているといえます。これでは労働災害や重大なミスの防止に、ハインリッヒの法則を活用できません。また、報告の手続きが煩雑で報告しにくいという問題も考えられます。
報告されても改善に生かされない
ハインリッヒの法則を生かせていない現場の特徴に、ヒヤリ・ハットが報告されても、適切な分析や対策が講じられないという点が挙げられます。業務の中で感じた「危ない」という事象の報告が軽視されれば、同様の事象が繰り返されるリスクが高まります。結果として軽微な事故を引き起こし、重大な事故につながりかねません。
報告内容が蓄積されず組織全体で共有されないと、個々の経験が生かされず、学習効果が得られなくなります。実際に報告が握りつぶされた経験があると、「またか」という気持ちが生まれ、従業員は報告を避けるようになってしまいます。報告が改善策として反映されなければ、ヒヤリ・ハットを伝える意義が薄れ、報告意欲が低下するでしょう。
安全管理が属人化している
安全管理が特定の担当者やベテラン社員に依存している状況も、リスク管理にハインリッヒの法則が活用できない理由です。安全管理に関する知識や経験の継承が困難となり、組織全体の安全管理の質が低下します。
属人化により標準化された報告手順やルールが整備されず、現場ごとに対応が異なることで、事故のリスクが増大します。ヒヤリ・ハットを報告する際の基準やルールがなければ、従業員ごとに判断が変わってしまうでしょう。結果として本来報告すべき事象が放置されることになります。
ハインリッヒの法則を現場で生かすには
安全管理の要となるハインリッヒの法則を機能させるには、ヒヤリ・ハットの報告と改善サイクルの定着が不可欠です。現場で継続的にリスクを把握・改善できる環境づくりのポイントを紹介します。
ヒヤリ・ハットの共有を習慣化する
ハインリッヒの法則を活用して労働災害や重大な事故を防ぐには、まずヒヤリ・ハットの報告を日常的な業務の一部とする取り組みが必要です。報告することが当たり前であり、義務を果たしたと評価される環境なら、従業員はためらいなくヒヤリ・ハットを報告できるでしょう。
ヒヤリ・ハットの報告・共有を習慣化するには、定期的なミーティングやフィードバックが必要です。このような機会を設けることで、報告の重要性を全従業員に認識させられます。さらに成功事例の共有や報告者の評価制度を導入し、報告文化の定着を図るのが効果的です。
報告・分析・改善のサイクルを定着させる
ハインリッヒの法則をリスク管理に生かすには、まずヒヤリ・ハットの報告があったら改善に生かす必要があります。ヒヤリ・ハットの報告後は、迅速な分析と具体的な改善策の実施が必要です。
また、改善策の効果を評価し、必要に応じて再度対策を講じるPDCAサイクルを確立することもハインリッヒの法則活用に欠かせません。危機管理のPDCAサイクルを組織全体で共有し、継続的な安全性の向上を目指しましょう。
安全対策のルールを全社的に明示する
ヒヤリ・ハット報告のような安全管理を属人化させないことも、ハインリッヒの法則活用に欠かせません。企業として安全対策についてのルールを明示し、全従業員が報告の基準や手順を把握できるようにする必要があります。
安全に関する基準やルール・手順を共有することで、組織全体の安全意識も高められます。ルールは複雑すぎず、誰にでも実践可能なものにしましょう。安全管理のマニュアルを作る際は、動画を活用すると伝わりやすくなります。
TUNAGでハインリッヒの法則活用を「現場の当たり前」に
有用な法則であっても、現場の行動に落とし込む仕組みがなければリスク管理として活用できません。改善策の一例として、TUNAGを活用してハインリッヒの法則を現場に根付かせる工夫を見ていきましょう。
社内コミュニケーションの活性化で報告しやすい土台をつくる
ヒヤリ・ハットの報告がしやすい環境づくりには、TUNAGの社内チャットやタイムライン機能が役立ちます。普段から仕事上の出来事を共有しやすい仕組みができていれば、ヒヤリ・ハットの報告もしやすくなるでしょう。
タイムラインへの投稿は、制度一覧で「安全管理」などのカテゴリに分類することが可能です。現場の従業員が検索して、報告すべきかどうかの判断基準にもできます。また、しっかりとカテゴリ分けしてストックしておけば、PDCAサイクルに生かせます。
マニュアルや社内ポータルで報告・対策ルールを明示する
TUNAGのマニュアル機能では、動画や画像を使ったマニュアルの作成・格納が可能です。作成されたマニュアルはスマホからでも見られるので、普段パソコンを業務で使わない従業員が多い企業でも、安全管理のルールが社内に浸透しやすくなります。
社内ポータルとして使える外部リンク機能に、ルールを常設しておくのも一つの方法です。こちらもスマホからいつでもアクセスできるため、現場の従業員にも対策を講じる役職者にも、ハインリッヒの法則を活用するためのノウハウが簡単に共有されます。
ハインリッヒの法則を軸に安全文化を育てよう
重大事故の背後にあるのは、日々のヒヤリ・ハットに対する小さな見過ごしです。ハインリッヒの法則は、それらを拾い上げるための「気付きのレンズ」として機能します。現場の声に耳を傾け、改善のサイクルを回し続けることで、法則は組織の安全文化へと育っていきます。
リスクへの感度が組織全体に浸透して「当たり前」になっている状態が、ハインリッヒの法則を活用する土台です。TUNAGのようなツールも活用しながら、ヒヤリ・ハットの報告から分析・改善までのサイクルを定着させましょう。




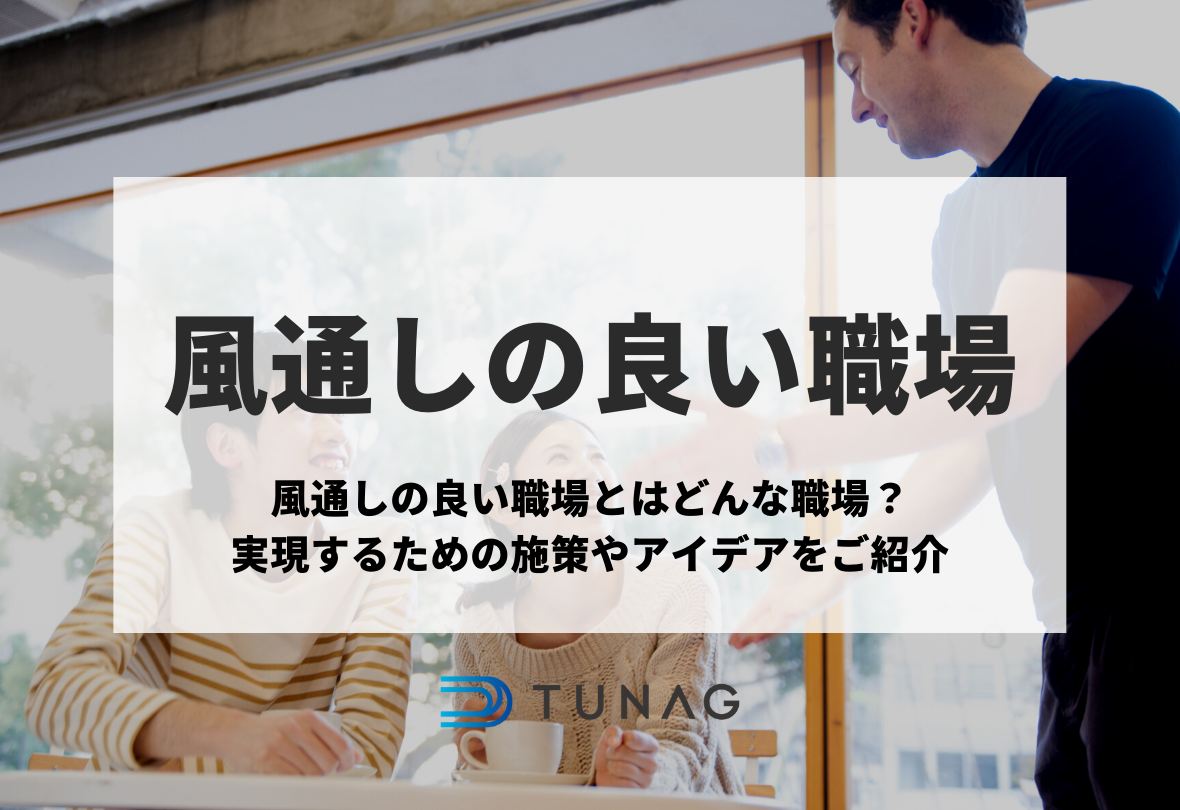
.webp&w=3840&q=75)







