男性の育休とは?制度の基本と現場運用の課題・対策を解説
男性の育休制度があっても、実際には取得できない状況にあり、頭を悩ませている企業もあるかもしれません。男性の育休とは何かという制度の基本から、男性従業員が育休を取れるメリット、企業ができる対策まで解説します。
男性の育休とは?制度の基本とその背景
男性が育休を取りやすい環境をつくるには、まず制度について正しく知っておく必要があります。男性の育休とは何を指すのかとともに、近年の動向を見ていきましょう。
一般には「育児休業」「産後パパ育休」の総称
男性の育休制度には、「育児休業」と「産後パパ育休(出生時育児休業)」の2つがあります。「育休」は育児休業の略称であり、「男性の育休」は厳密には育児・介護休業法で定められた「育児休業」(男女ともに取得可能)を指します。
ただ近年、同法に育児休業とは別枠で取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」も定められました。女性には労働基準法で定められた産後8週間までの産休(第65条第2項)があるため、主に男性向けの制度といえるでしょう。
一般的に「男性の育休」といえば、育児休業と産後パパ育休のどちらも含めている場合が多くなっています。
参考:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)第5条・第9条の2|e-Gov 法令検索
参考:労働基準法 第65条第2項|e-Gov 法令検索
「育児休業」と「産後パパ育休」の違いとは?
育児休業も産後パパ育休(出生時育児休業)も、育児・介護休業法で定められた休暇です。違いが何なのかよく分からない人も多いでしょう。
「育児休業」は、子の1歳の誕生日まで取得可能(条件により最長2歳まで延長可)です。「産後パパ育休」は、子の出生後8週間以内に最大4週間取得可能で、2回に分割して取得できます。
産後パパ育休は事前の申し出期限が原則2週間前であり、柔軟な取得が可能という点が特徴です。
参考:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)第5条・第9条の2|e-Gov 法令検索
参考:令和3(2021)年法改正のポイント|育児休業制度特設サイト|厚生労働省
各種の法改正で取得機会は広がっている
産後パパ育休(出生時育児休業)は、2022年の育児・介護休業法の改正によって新設されました。さらに改正により、育児休業の分割取得が可能となっています。
2025年4月からは、育児休業の取得状況の公表が従業員300人超・1,000人以下の企業にも義務付けられました。国として、男性の育休取得を促進する環境を整備していこうという意図が見て取れます。
参考:令和3(2021)年法改正のポイント|育児休業制度特設サイト|厚生労働省
参考:男性の育児休業取得率等の公表について「2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます(令和6年5月作成)」PDF|厚生労働省
男性の育休取得に立ちはだかる課題とは
男性の育休制度は充実してきましたが、実際には取得できない環境になっているという企業も多いでしょう。男性従業員が育休を取れない原因には、具体的に何があるのでしょうか。
人手不足の現場では取得調整が難しい
人手不足の現場では、育休取得者の業務をカバーする人員が確保できません。結果として男性の育休取得が難しくなります。
特に中小企業や、建設業・製造業などの業界は慢性的な人手不足の状態です。離職率が高く常に人が足りていない組織も同じく、制度はあっても育休が取れないという状態になってしまいます。
参考:令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-「全体版」PDF P.37〜38|厚生労働省
職場の理解不足や圧力が育休取得を妨げる
職場の理解不足や「育休を取得しづらい雰囲気」も、男性の育休取得を妨げている原因です。人手不足と違って数値化できる要素ではなく、経営層からは見えにくいかもしれませんが、現場で働く従業員にとっては深刻な問題です。
理解不足や「休んではいけない」という無言の圧力があるなら、上司や同僚の意識改革が必要です。企業としては、育休取得を推奨する職場文化を醸成していく必要があります。
収入減やキャリアへの不安も障壁に
育休取得中の収入減少を懸念する男性も見られます。育児休業中の収入は、原則として雇用保険からの「育児休業等給付金」の支給のみとなり、各種の給付金を合計しても休業開始時賃金日額の80%が上限です。
さらにキャリアについて、「育休を取得することで昇進や評価に影響が出るのではないか」と不安を抱えるケースも少なくありません。
実際に育休を取得した男性従業員が昇進したり高く評価されたりした実績がなければ、育休取得をためらってしまうでしょう。
男性従業員が育休を取得できるメリット
男性が育休を取得できる環境を整えることは、従業員側だけでなく企業にもメリットがあります。どのような点がプラスになるのか、育休を取得した男性従業員に起こり得る変化を軸に整理しました。
子どもの成長に関わることで満足度が上がる
子どもの成長を間近で感じられれば、家庭での満足度が向上します。育休中は、精神的に充実した時間を過ごせるはずです。
育休を取りやすい環境をつくってくれた勤務先に対しての満足度も上がり、組織エンゲージメントが高まります。育休からの復帰後、精力的に働いてくれたり長く在籍してくれたりと、企業にとってうれしい効果が期待できるでしょう。
現場のメンバーを信頼できるようになる
育休取得について理解してもらえれば、経営陣や人事はもちろん、自分がいない間の業務を担ってくれる現場への信頼も高まります。
育休取得を通じて業務を任せることで、同僚や部下への信頼が深まるでしょう。結果としてチームでの協力体制が強化され、職場の一体感が向上しやすくなります。
育児経験が仕事への行動・意識の変化につながることも
育児を経験すると、時間管理能力やマルチタスク能力、コミュニケーション能力が向上するといわれています。業務にもその能力を生かせるようになれば、生産性が上がって企業にとっての利益となるはずです。
育児を通じて得た経験が、仕事への意識変化につながる場合もあるでしょう。例えば明確なコミュニケーションの大切さに気付いたり、アンガーマネジメントを意識したりするようになる男性もいます。
TUNAGで男性の育休制度を職場に根づかせよう
男性が実際に育休を取得できる環境をつくるには、仕組み化が必要です。解決策の一例として、組織エンゲージメントを高める「TUNAG(ツナグ)」を活用した取り組みを紹介します。
制度内容と取得フローを社内ポータルで明示
TUNAGの社内ポータル(外部リンク)機能を活用し、育休制度の内容や取得手続きを明確に伝えることで、男性従業員にも「自分も取得できるのだ」という意識が芽生えます。
TUNAGはスマホやタブレットからでもアクセスできます。製造スタッフのようにパソコンを使わない従業員でも、休憩中に手軽に確認が可能です。制度の周知徹底により、従業員の理解と取得意欲が高められるでしょう。
チャットや掲示板で取得希望者と管理者の情報交換を促進
TUNAGの社内チャットや社内掲示板機能を活用すれば、育休取得希望者と管理者との情報交換を円滑にできます。
取得希望者の不安や疑問が解消しやすくなり、スムーズな育休取得を支援できるでしょう。社内チャットはコミュニケーションの活性化を実現するため、休みやすい雰囲気づくりの醸成にも役立ちます。
アンケート・エンゲージメント診断で現場の声も可視化
「休みにくい」「休まれると困る」など現場のリアルな声を可視化するのも、男性が育休を取りやすい職場づくりに必要な取り組みです。収集した声から、どうすれば育休に対する理解を促進できるのかを考え、対策に生かせます。
TUNAGの社内アンケートは、組織ごとに必要な項目のカスタマイズが可能です。男性の育休についての質問を設け、リアルな意見を集めましょう。
TUNAGが提供するエンゲージメントサーベイ「TERAS」を活用するのも1つの手です。サーベイ結果からの改善提案には料金がかかりますが、診断だけなら人数や回数に制限はなく、初期費用も月額費用もかかりません。
組織のための基本無料エンゲージメントサーベイツール|TERAS
男性も育休を取りやすい職場づくりを
男性の育休(育児休業や産後パパ育休)は、近年の法改正によって取得の機会が広がってきました。社会としても男性の育児参加が浸透してきている中、企業には男性も育休を活用しやすい職場づくりが求められます。
男性が育休を取得しにくい原因は、人手不足や職場の理解不足・圧力、収入・キャリアへの不安など、すぐに解決できる問題ばかりではありません。
ただ、男性も育休を取得できるのだという意識の醸成や、休みやすい環境づくりにはすぐ取り組めるはずです。TUNAGのようなツールの活用も検討しつつ、男性従業員も育休を取得しやすい環境を整え、組織エンゲージメントの向上を目指しましょう。




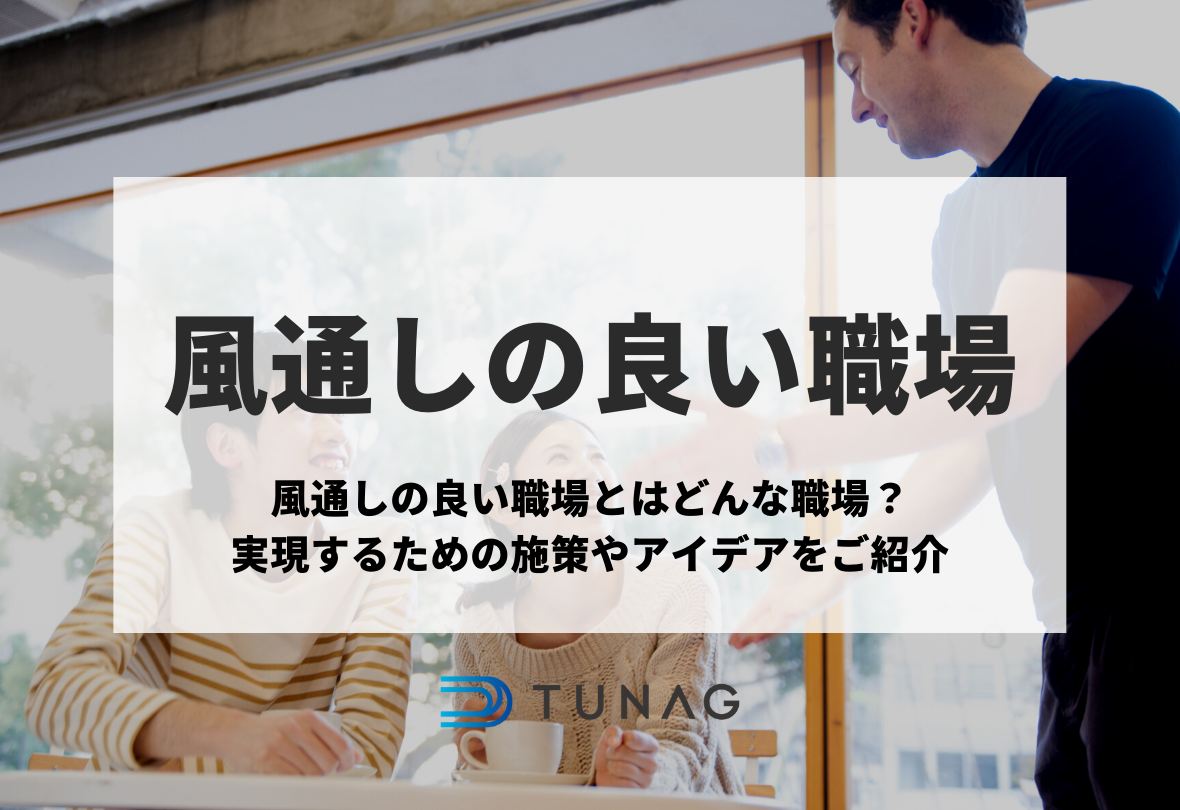
.webp&w=3840&q=75)







