組織効力感の高め方とは?従業員が自信を持ち、生産性が向上する仕組みづくりを解説
近年、多くの企業が生産性向上や離職率低下に向けた施策を模索しています。その中で注目されるのが「組織効力感」です。組織効力感とは、従業員が自社の目標達成能力を信じる感覚のことで、これが低下するとモチベーションやエンゲージメントの低下を招きます。
本記事では、組織効力感が企業にもたらすメリット、さらに具体的な向上施策まで詳しく解説します。
※『組織効力感』は株式会社Momentorの登録商標です。
組織効力感とは何か
効力感とは、「自分には課題を乗り越える力がある」という感覚を指し、似た概念である「自己肯定感(自分の存在そのものを肯定する気持ち)」とは異なります。
組織効力感とは、この効力感が個人ではなくチーム全体に広がったもので、「自分たちの組織なら目標を達成できる」と信じる集団的な確信を意味します。
この感覚は、リーダーの姿勢や組織文化、過去の成功体験を通じて培われます。
たとえば、トラブルを乗り越えた経験があるチームでは、「今回もやれる」と前向きに挑戦する傾向が強まります。メンバー同士が役割を理解し支え合う環境が整うことで、困難にも立ち向かえる、しなやかで強い組織が育つのです。
組織効力感不足は日本企業が抱える課題
多くの日本企業では、組織効力感の欠如が深刻な課題となっています。特に年功序列やトップダウン型の組織では、現場の従業員が意思決定に関与できず、「自分の行動が組織の成功に寄与している」という実感を得にくい傾向があります。
たとえば、新しい提案をしても「上司の判断待ち」となるケースが多く、結果として挑戦意欲が削がれ、主体性が失われがちです。
さらに、成果が個人よりも組織全体に帰属する文化では、努力が認識されにくく、モチベーションの低下にもつながります。このような構造が、組織効力感の醸成を妨げているのです。
組織効力感が組織にもたらす良い影響
組織効力感を高めることで、企業は単に雰囲気が良くなるだけでなく、具体的な経営上の成果を得ることができます。ここでは、組織効力感がもたらす代表的なメリットを3つに分けて解説します。
生産性が高まり、チームの力が最大化される
組織効力感の高いチームでは、メンバー間の信頼が強固で、協力しながら目標に向かって進む姿勢が自然に生まれます。心理的安全性が確保されているため、自由に意見を出し合える環境が整い、革新的なアイデアや改善提案が活発になるのです。
たとえば、通常であれば言い出しにくい改善案も、安心して発言できる雰囲気があることで実行に移されやすくなります。
失敗に対する寛容な文化も根付くため、挑戦へのハードルが下がり、結果として、業務の効率化と質の向上が同時に実現するのです。
離職を防ぎ、優秀な人材が定着する
組織効力感の高い職場では、従業員が「この会社なら成果が出せる」「努力が正当に評価される」と感じやすくなります。このような感覚は、仕事への満足感とモチベーションを引き上げ、組織への帰属意識を高める要因になるでしょう。
たとえば、自分の意見が反映される、成果を認められるといった経験が積み重なることで、「ここで働き続けたい」という気持ちが芽生えます。
特に、プレッシャーや過重労働が原因で離職が多い日本企業においては、組織効力感の醸成が人材定着の鍵を握ります。働きやすく、成長できると感じられる環境づくりが、長期的な人材確保と企業の安定成長につながるのです。
困難に挑む「前向きな風土」が生まれる
組織効力感が高いと、従業員は困難な課題に対しても前向きに挑戦する姿勢を持つようになります。「このチームなら乗り越えられる」という確信があることで、プレッシャーを力に変え、リスクを恐れずに行動できるのです。
また、挑戦に対するポジティブなフィードバックを行うことで、「努力すれば成功できる」という意識が醸成されます。
このような文化が組織全体に浸透すれば、新規事業の推進や業務改革にも積極的に取り組む風土が生まれ、組織全体の成長スピードが加速していくでしょう。
組織効力感を高めるための施策
「組織の目標達成力を高めたい」「チームの士気を向上させたい」と考えていても、何をすれば効果的なのか分からない企業は少なくありません。
組織効力感を高めるには、個人と組織の両面からアプローチすることが不可欠です。どのような施策が実際に効果を発揮するのでしょうか? 効果的な取り組みを紹介します。
個人レベルで自己効力感を高める仕組みをつくる
組織効力感を高めるためには、まず個々の従業員が自分の能力を信じ、主体的に行動できる環境を整えることが重要です。従業員一人一人のスキル向上を支援する研修制度や、キャリア開発の機会を提供しましょう。
定期的なスキルアップ研修、メンター制度の導入、挑戦を促すプロジェクトの提供などが有効です。また、上司や同僚からの適切なフィードバックや承認を受けることで、従業員は自信を深め、成長へのモチベーションを維持しやすくなります。
個人の成功を組織で共有する
個々の成功体験を組織全体の力へと昇華させることは、組織効力感を強化する上で欠かせません。個人が達成した成果を適切に評価し、それを全体で共有することで、組織のメンバー全員が「自分たちは成功できる」と実感できるようになります。
社内で成功事例を共有するための社内報や社内SNSなどをデジタルツールで紹介する仕組みを構築したり、従業員同士で感謝を贈り合えるサンクスカードなどの仕組みは、個人の成功や努力を組織全体に伝えることが可能です。
また、成功を称賛する文化を醸成することで、従業員同士がポジティブな影響を与え合い、さらなる挑戦を後押しすることにつながります。
従業員のエンゲージメントを高めるこれらの称賛文化を形成するには、「TUNAG」がおすすめです。組織効力感を高めるために、ぜひご活用ください。
組織全体で効力感を高める
これまで紹介してきた施策によって個人としての自己効力感を高まってきたら、次は組織全体で高められる施策を行いましょう。
新規事業や業務改善のアイデアを社内で募集するピッチコンテストの開催や、部署を超えたプロジェクトチームを編成し、従業員が普段関わらないメンバーと協力する機会を提供する「クロスファンクショナルチーム」の作成など、全社で組織効力感を高める取り組みを進めていきましょう。
また、経営者がビジョンや成功体験、従業員へのメッセージを共有することで、従業員もそれに倣って組織のエンゲージメントが高まります。
このような文化改革が進むことで、組織効力感はより強固になり、変化に適応できる組織へと進化していくでしょう。
組織効力感を高めて組織の課題を解決する
組織効力感を高めることは、企業の成長や従業員のモチベーション向上に直結します。組織のメンバーが「このチームなら目標を達成できる」と確信を持てる環境を整えることで、生産性向上や離職率の低下など、さまざまなメリットが生まれます。
特に、日本企業においては、年功序列やトップダウン型の意思決定による組織効力感の低下が課題となっています。この問題を解決するためには、従業員が主体的に行動できる環境を整え、成功体験を共有し、組織全体で「達成できる」という意識を育むことが重要です。
組織効力感を高めることは、単なる企業の戦略ではなく、働く人々の意欲や充実感を向上させるためにも不可欠な要素です。本記事で紹介した施策を参考にしながら、自社に適したアプローチを取り入れ、より強く、持続的に成長できる組織づくりを目指しましょう。




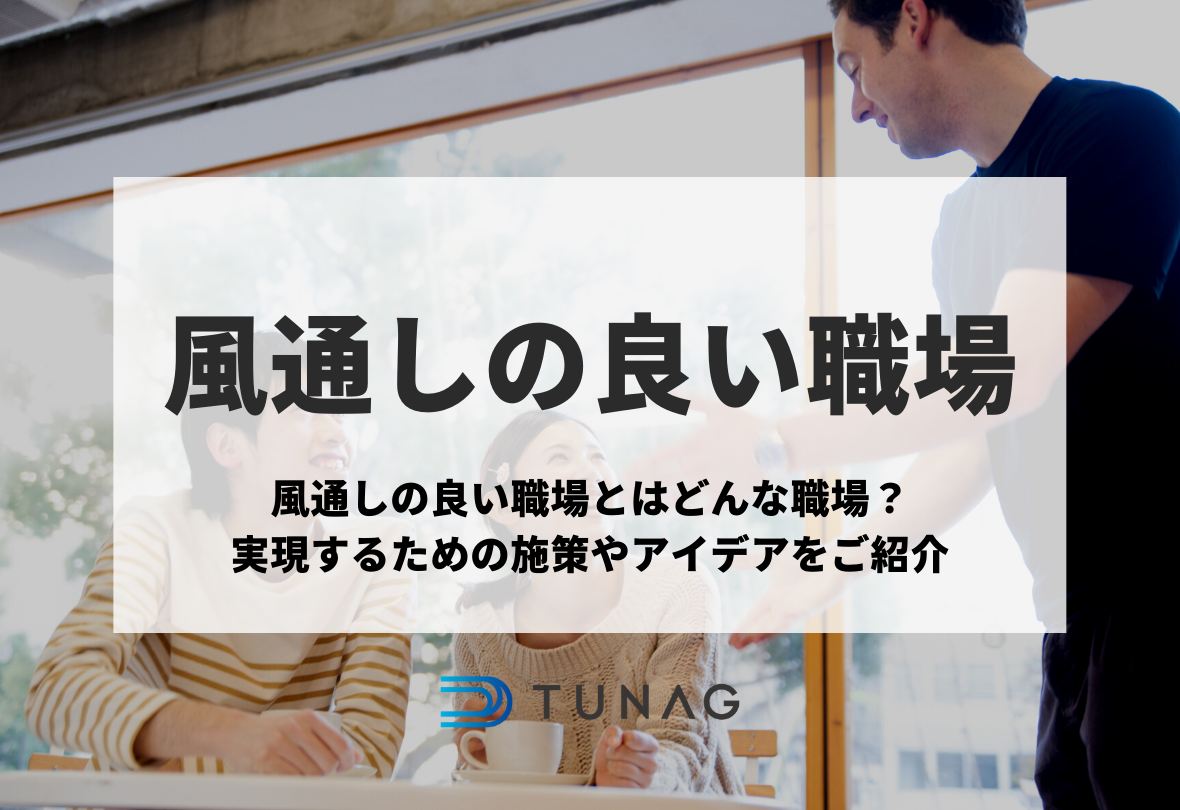
.webp&w=3840&q=75)







