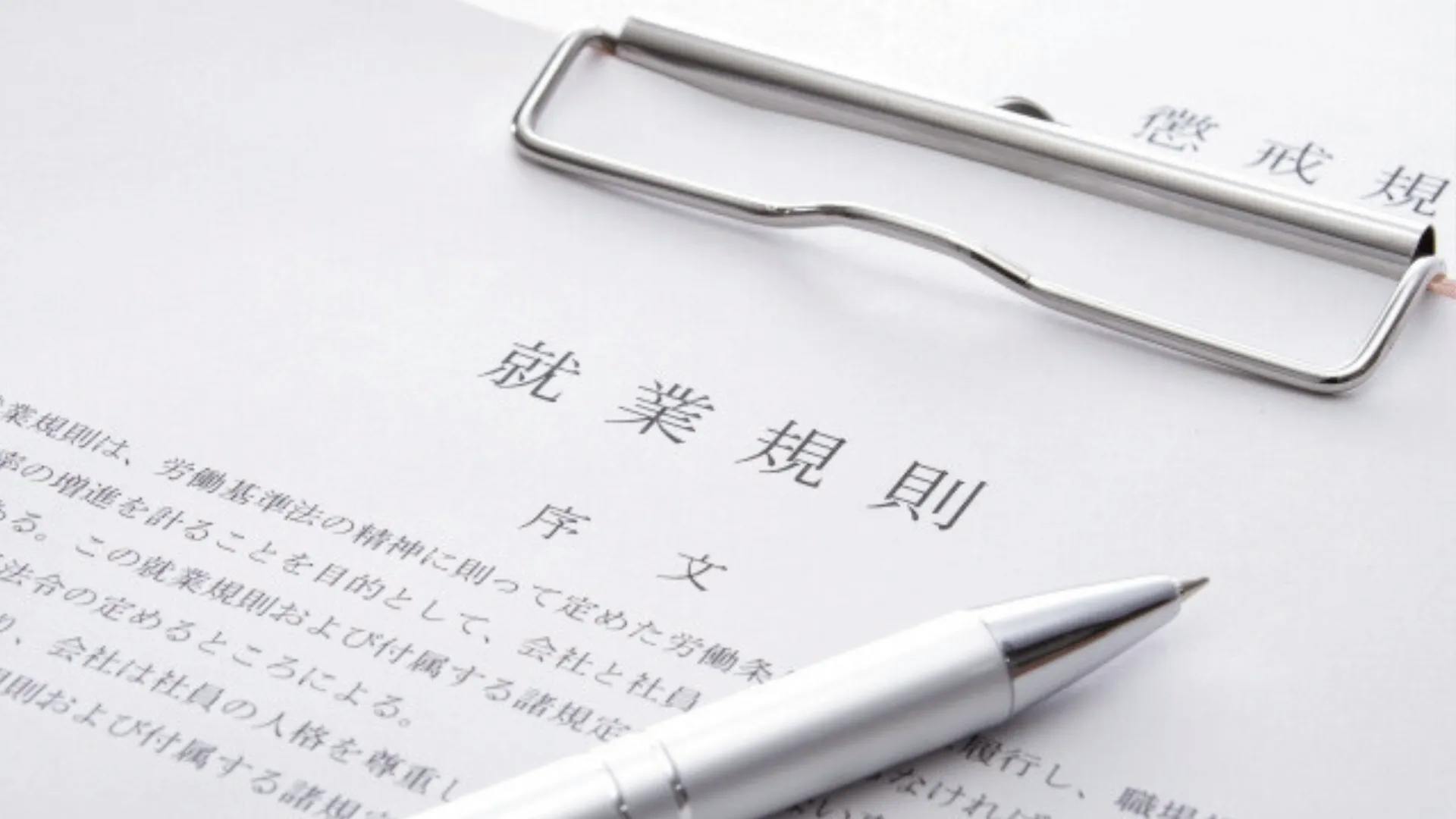社内通貨を導入している事例を紹介!導入メリット・デメリットも解説
社内通貨(社内ポイント)制度とは
社内通貨(社内ポイント)とは?
社内通貨とは、企業が従業員向けに発行する社内限定の通貨のことです。社内ポイント制度、企業内通貨、社内仮想通貨などと呼ばれることもあります。
ただし、普段私たちが通貨として使っている紙幣や硬貨のようなものを発行するのではなく、アプリやシステム上でポイント形式でやり取りする形が一般的です。
社内通貨の使い道は?
貯まった社内通貨は企業が用意した商品・特典と交換できたり、インセンティブとして毎月の給与とは別に与えられることが多いです。企業によって違いはありますが、具体的には以下のような使い道があります。
書籍の購入
貯まった社内通貨の分だけ書籍の購入を補助してもらうことができます。従業員の自己研鑽や学びに力を入れている企業で多いです。
資格取得やセミナー参加
同じく自己研鑽関連で、資格取得やセミナー参加の補助として社内通貨を利用できるケースもあります。
社割
飲食業や小売業の企業などでは、自社製品を購入したり自社のサービスを利用する際に社割として社内通貨の分だけ割引を受けられる仕組みもあります。
業務で使う物品の購入
キーボードやマウス、職種特有の道具など、業務で使う物品の購入に社内通貨を使えることもあります。
オフィスのお菓子や飲み物と交換
オフィスにあるお菓子や飲み物と社内通貨を交換できる企業もあります。
社内通貨制度の作り方のポイント
気になる社内通貨の作り方についてもご紹介します。冒頭でも紹介したように社内通貨はアプリやシステムでの運用が一般的なため、社内通貨の作り方もそれを前提に説明します。
目的を整理する
社内通貨の失敗事例で多いのが、目的を整理しないままなんとなく始めた結果、従業員に利用されず形骸化してしまうか、あるいは一部の人だけで盛り上がって社内に温度差ができてしまうケースです。
そうならないためには、自社で社内通貨を運用する目的が何なのか、何を解決したいのかを整理することが非常に重要です。
貯め方を決める
目的が決まったら、次に「従業員がどんな行動をしたら社内通貨が貯まるようにするのか」を決めます。これは、「社内通貨の目的をふまえて、従業員にどんな行動をとってほしいかを考える」という作業でもあります。
例えば、こんなパターンが考えられます。
目的が「コミュニケーション促進」の場合
目的が「モチベーション向上」の場合
- 売上や目標を達成した従業員に社内通貨が付与される
- MVPに社内通貨が付与されるなど、表彰制度と結びつけて運用する
目的が「経営理念や行動指針の浸透」の場合
- 経営理念や行動指針に沿った行動にサンクスカードを送ると、送った人・もらった人は社内通貨が貯まる
- 会社の方針に沿った行動をしている人をピックアップして紹介し、社内通貨を付与する
使い道を決める
貯まった社内通貨の使い道として、従業員が何を利用できるかも明確にしましょう。ここが曖昧だと、やはり形骸化しやすくなります。貯め方と同じく、目的を考えて使い道を考えるのが重要です。
- 他部署の人とランチや食事に行くときの食事代補助として使える
- 役員や社長にご馳走してもらえる食事会チケットと交換できる
- 業務利用する物品を購入するときの補助に利用できる
- 書籍の購入や資格取得の補助に利用できる
貯まる・使うときのポイント数と頻度を決める
目的・貯め方・使い道が決まったら、全体のバランスを見ながらポイント配分や利用可能な頻度を決めていきます。
社内通貨はこの配分が難しいところで、以下のような社内通貨の失敗例にならないよう、バランスよく設計する必要があります。
社内通貨が貯まりにくく従業員に利用されない
一度に貯まるポイント数を増やしたり、定期的に貯まる仕組みを作りましょう。
使い道のポイント数が高すぎて従業員が利用できない
利用に必要なポイント数を下げて調整したり、少ないポイントでカジュアルに利用できる仕組みを作りましょう。
従業員のポイント数が貯まりすぎて会社の負担になってしまう
ポイント数を下げるか、「一定以上貯まると月に一回利用できる」など頻度を絞りましょう。
社内通貨のアプリ・システムを選ぶ
社内通貨はアプリやシステムで運用・管理するのが一般的です。自社で社内通貨を運用する目的や使い道に合わせて、アプリやシステムを選びましょう。
テスト運用して、細かな運用ルールを策定する
貯め方や使い道、ポイント数と頻度についての大枠のルールを決めたら、実際に社内通貨・社内ポイントのシステムを試験運用してみて、運用ルールにおける抜け漏れがないかを確認します。
具体的には、下記のようなルールが設定されているかを再度確認すると良いでしょう。
- 社内通貨のポイント数に使える月次の予算
- 社内通貨の有効期限
- 社内通貨のポイントと交換できる商品の見直しタイミング
- 社内通貨を「誰が」「いつ」「どのように」管理していくか
- 社内通貨が不正に利用されることはないか(運用ルールや方針に逸脱した行動ができないようになっているか)
従業員に意図や背景を説明して運用スタート
アプリやシステム、運用ルールが揃ったら、従業員に社内通貨について説明していよいよ運用が始まります。しかし、説明の仕方によっては「よくわからないことが始まったなぁ」「また面倒なことが増えるんじゃないか」など、不満や不信感に繋がってしまうリスクがあります。
「どうしたら貯まるのか、どんな使い道があるのか」ももちろんですが、最も重要なのが意図や背景です。「なぜやるのか」「どんな会社にしたいからやるのか」などの部分を丁寧に伝えれば従業員も納得しやすく、社内通貨の仕組みがより活発に利用されるでしょう。
◾️関連するお役立ち資料
社内通貨のデメリットと失敗対策
メリットの多い社内通貨ですが、デメリットも存在します。ここでは、社内通貨運用の懸念点と対策を解説します。
コストがかかる
アプリやシステムを導入する必要があるため、社内通貨の運営にはコストがかかるケースが多いです。
また、最初の制度設計が不十分だと運用・管理の工数もかかってきます。
使われないというリスクがある
せっかく社内通貨を導入しても、それが使われないというリスクもあります。
使う人がいなければ想定していた効果も生まれず、コストだけがかかる結果となってしまいます。
社内通貨のデメリットを回避するには?
上記のようなデメリットを回避するには、解決したい課題や目的を明確にし、それに合わせて貯め方や使い道などの運用方法を決め、社内で推進していくことが必要です。
以下のホワイトペーパーには、社内通貨の運用ノウハウもまとめてあります。ぜひ参考にしてください。
◾️お役立ち資料「社内ポイント・社内通貨の運用事例」
ダウンロード(無料)⇒こちらから
社内通貨の4つのメリット・運用目的
社内通貨の導入・運用には、次のようなメリットや目的があります。
コミュニケーション促進
社内通貨を仲間への感謝の気持ちとともに贈るという運用や、「ピアボーナス※」という形で第三の給与として活用されることもあります。
感謝を伝え合うことによって職場に称賛文化を浸透させたり、承認欲求を満たす一つの手段として用いられたりしています。
昔は飲み会などでコミュニケーションをとることが多くありましたが、コミュニケーションの形も働き方や価値観の多様化によって変わってきています。
モチベーション向上・称賛文化の醸成
自分の働きが評価されない、目で見えない頑張りが認められない。そういった不満が募ることを解消するため、社内通貨制度を活用して従業員の頑張りをこまめに称賛し、認めていくこともできます。
社内通貨の場合は「通貨」という形のため、目に見える報酬として実感しやすいのもポイントです。会社や他の従業員からの称賛・承認が可視化されるという点で、モチベーション向上につながる有効な手段の一つです。
経営理念や行動指針の浸透
経営理念や行動指針を浸透させるには、どんな行動が経営理念や行動指針に沿っているのか従業員が具体的に理解することが重要です。
そこで、例えばサンクスカードを送るときは「どの経営理念や行動指針に沿っているか」を書く運用にして、サンクスカードで社内通貨が貯まる仕組みで動機づけをしてあげると、経営理念や行動指針が社内に浸透しやすくなります。
スキルアップや学びの文化づくり
学びやスキルアップは従業員の仕事のやりがいにつながるだけでなく、会社としても生産性の向上などにつながります。
自己研鑽によって社内通貨が貯まったり活用できたりする仕組みを作れば、従業員もより積極的にスキルアップに取り組んでくれるでしょう。
社内通貨の運用事例10社
実際に社内通貨を導入している企業の例を紹介します。自社での導入・運用の参考にしてみてください。
1. 株式会社ディスコの「will」
まず紹介するのは半導体切断装置の最大手である株式会社ディスコの「will」です。この会社は、厚生労働省の選ぶ働きやすい企業の部門で最優秀賞を取ったことがあります。その理由の一つがここで紹介する「will」です。月の収入や支出、社内業務の受発注などをこの通貨を用いて行っています。
また、社内プレゼンの賞金として「will」が贈られたり、「will」保有者の上位者はホームページ上で発表されたりするなど、仕事のモチベーションアップや競争心を煽るために使われています。
2. スーパーサンシ株式会社の「サンシコイン」
 スーパーマーケット事業・店舗宅配事業を展開するスーパーサンシ株式会社では、パートやアルバイトの方も対象に「サンシコイン」という社内通貨を運用しています。
売上目標の達成、売り場コンクール、業務改善案の提出などで社内通貨が支払われる仕組みで、頑張っている人、仕事で光っている人が報われる制度になっています。従業員の誕生日や入社記念日にも付与され、従業員によっては数十万もの社内通貨が貯まっている人もいるそうです。
貯まった社内通貨の使い道はさまざまで、途中で引き出して「車検代の足し」にする方もいるそうです。また、パートやアルバイトの方が退職するときの退職金として支払われることもあります。
>>スーパーサンシ株式会社様の取り組み事例はこちら
スーパーマーケット事業・店舗宅配事業を展開するスーパーサンシ株式会社では、パートやアルバイトの方も対象に「サンシコイン」という社内通貨を運用しています。
売上目標の達成、売り場コンクール、業務改善案の提出などで社内通貨が支払われる仕組みで、頑張っている人、仕事で光っている人が報われる制度になっています。従業員の誕生日や入社記念日にも付与され、従業員によっては数十万もの社内通貨が貯まっている人もいるそうです。
貯まった社内通貨の使い道はさまざまで、途中で引き出して「車検代の足し」にする方もいるそうです。また、パートやアルバイトの方が退職するときの退職金として支払われることもあります。
>>スーパーサンシ株式会社様の取り組み事例はこちら
3. 株式会社牛若丸の「ウシポ」
 美容室やネイルサロン経営、ブライダル事業、振袖レンタル事業など、「美」にまつわる事業を幅広く展開する株式会社牛若丸では、社内通貨「ウシポ」を運用しています。アプリ上でサンクスカードを送ったとき・もらったときなどに貯まる仕組みになっています。
貯まったポイントは、アシスタントやスタイリストの方が練習で使うウィッグやクリップ、店舗で使える1,000円分の商品券などと交換できます。「アイリストやネイリストの仕事道具や、より全員が使える交換商品も選べたら嬉しい」といった声もあり、今後さらに美容関係の道具や消耗品のラインナップを増やす予定だそうです。
>>株式会社牛若丸様の取り組み事例はこちら
美容室やネイルサロン経営、ブライダル事業、振袖レンタル事業など、「美」にまつわる事業を幅広く展開する株式会社牛若丸では、社内通貨「ウシポ」を運用しています。アプリ上でサンクスカードを送ったとき・もらったときなどに貯まる仕組みになっています。
貯まったポイントは、アシスタントやスタイリストの方が練習で使うウィッグやクリップ、店舗で使える1,000円分の商品券などと交換できます。「アイリストやネイリストの仕事道具や、より全員が使える交換商品も選べたら嬉しい」といった声もあり、今後さらに美容関係の道具や消耗品のラインナップを増やす予定だそうです。
>>株式会社牛若丸様の取り組み事例はこちら
4. 有限会社光田モータースの「ミツダポイント」
愛知県一宮市を中心に、自動車販売、車検・整備、レンタカーなどの事業を8拠点で行う有限会社光田モータースでは、社内通貨の「ミツダポイント」を運用しています。社内アプリ「TUNAG」上でコミュニケーションに関する投稿をするとポイントが貯まっていき、貯まったポイントで豪華景品が当たる「サイコロチャレンジ」という社内イベントの抽選券を獲得することができるよう設計されています。 社内通貨を起点に「ポイントがあと少しで貯まります」「この投稿しますね」という声が生まれるなど、拠点を超えたコミュニケーションの促進や、社内イベントの活性化を実現しています。 >>有限会社光田モータース様の取り組み事例はこちら5. 株式会社オロの「Oron」
株式会社オロでは、"感謝"や"お祝い"の気持ちをポイントにして相手に伝える「Oron」を運用しています。貯まった社内通貨は、人気の商品や社内のオリジナルグッズと交換できます。 この社内通貨は従業員同士で贈り合うことができるので、コミュニケーション活性化にも繋がっているそうです。 参照: 社内 Greeting Point 制度「Oron(オロン)」のご紹介|株式会社オロ6. 株式会社Wizの「Wizコイン」
株式会社Wizでは「Wizコイン」という社内通貨が運用されています。この社内通貨は、社内の良い行動に対して贈られます。 仕事内容以外にも、社内イベントの企画、プライベートでの引っ越しの手伝いなども評価の対象になっています。貯まった社内通貨は1枚から景品と交換でき、スリッパやノートなど日用品のほか、加湿器や豪華チェア、オーダーメイドスーツ、上司との食事券などと交換することができます。 参照:「いいね」の気持ちを贈りあうピアボーナス「Wizコイン」導入事例7. 株式会社じげんの「GAT」
株式会社じげんでは、社内通貨として「GAT」が運用されています。毎月お世話になった人に感謝の気持ちを込め、一言コメントとともに社内通貨を贈ります。 社内通貨を貯めると、豪華景品と交換することができます。 参照: 社内通貨制度「GAT」 | 株式会社じげん - UWORK(ユーワーク)8. カブドットコム証券株式会社の「OOIRI」
ガブドットコム証券株式会社では、コミュニケーション活性化を目的に「OOIRI」という社内通貨を導入しました。 この社内通貨は、社内で進めている施策のインセンティブとして付与したり、社員のアドバイスに感謝を伝えたり、効率的な会議運営へのお礼として付与するなどの方法で貯まります。貯まった社内通貨は、近隣の飲食店などで利用できるようです。 参照:ジオフェンシング技術とブロックチェーンを活用した企業コイン「OOIRI」を導入|プレスリリース|企業・開示情報|株のことならネット証券会社【auカブコム】9. 株式会社リンクアンドモチベーションの「LIMO」
株式会社リンクアンドモチベーションでは、社内通貨「LIMO」を運用しています。研修や自社理解テストの成績に応じて社内通貨が配布され、社内表彰制度の報酬としても付与されます。さらに、社内教育や仕事の報酬をポーカーやビンゴといったカジノゲームに見立てた人事教育制度「カジノルール」の報酬としても、社内通貨を獲得できます。 この社内通貨は円との交換が可能なため、ピアボーナスとして社員の働きを還元することもできます。 参照: 社内通貨「LIMO」でゲーム感覚新人研修を行うリンクアンドモチベーション社内通貨の運用方法4選
社内制度の運用方法として、よくあるパターンを4つまとめました。1. 表彰制度やMVP受賞などのインセンティブ制度に活用
成績優秀者や、社内コンテストの受賞者など、表彰制度などに社内通貨を付与するという方法があります。 ただ、一部の従業員しか貯めることができない状態が続くと、うまく運用がまわらないため、小さなことでも付与する機会を設けるなどの工夫が必要です。2. 感謝を送る「サンクスメッセージ」と絡める
仕事を手伝ってもらえた、業務で学びを得たなど、感謝を感じるシーンで社内通貨を贈るという使い方もあります。 会社の理念によっては、そのような「他人に感謝する人」も増やしたいという気持ちがあるかもしれません。その場合は、感謝を伝えた人、伝えられた人どちらにも通貨を付与するような運用も考えられるでしょう。 関連記事:社内表彰のアイデア5種類や事例4社、選考基準について解説 | 社内ポータル・SNSのTUNAG3. 業務依頼に用いる
社内の部門間で業務を依頼する際にこのような社内通貨を用いることも活用方法の一つです。通貨を通して依頼するルールを決めることで、急な業務の依頼や曖昧な依頼を防ぐことができます。4. 健康経営の推進に活用する
社内通貨は健康促進のために活用することもできます。例えば、残業時間を抑えた場合、予防接種等の健康に関わる行動をした場合に社内通貨を付加するということが考えられます。また、1日に歩いた歩数に応じて社内通貨を付与するという仕組みを取り入れても面白いかもしれません。 このように社内通貨を健康促進や働き方改革などのために用いることもできます。社内通貨制度は設計と運用が重要
社内通貨を作るだけでは目的を果たせない
社内通貨を導入することで、コミュニケーションの活性化やモチベーションの向上につながる運用が可能です。 しかし、ただ導入するだけでは目的を果たすことはできません。このような社員の方を巻き込んだ組織改革を行う場合は、継続的な実行と改善が必要です。誰も使わない状態になってしまうと、従業員は逆にしらけてしまったり、会社としての本気度が伝わらず不信感を募らせてしまうことになります。 どんな状態にするために導入するのか、目的と達成イメージを明確にしたうえで検討していきましょう。『TUNAG』なら、設計・運用までトレーナーが伴走してサポート
 社内通貨のサービスの一つである『TUNAG(ツナグ)』では、設計や運用の難しい社内通貨だからこそ、各社の課題に合わせて最適な設計・運用ができるよう、トレーナーが伴走してサポートを実施しています。他社事例やこれまでのサポート実績をもとに、組織課題に合わせて設計・運用するため形骸化しにくいのが特徴です。
また、サンクスカードの送り合いではもらう人だけでなく送る人にもポイントを付与でき、「良い行動を見つけ出した側」も称賛する仕組みにできます。その他にも、自己研鑽など学びの文化を醸成したい場合は、勉強会やスキルアップの行動に対して通貨を付与することも可能です。
TUNAG上で社内通貨を運用する場合、会社の課題にあわせて通貨の名前・ポイント数・頻度も自由に設定することができます。
実際の企業での事例はこちら:社内通貨・ポイント | 目的別導入事例
※本記事での「ピアボーナス」の使用には、商標権者Unipos(株)から使用許諾を得ています。
社内通貨のサービスの一つである『TUNAG(ツナグ)』では、設計や運用の難しい社内通貨だからこそ、各社の課題に合わせて最適な設計・運用ができるよう、トレーナーが伴走してサポートを実施しています。他社事例やこれまでのサポート実績をもとに、組織課題に合わせて設計・運用するため形骸化しにくいのが特徴です。
また、サンクスカードの送り合いではもらう人だけでなく送る人にもポイントを付与でき、「良い行動を見つけ出した側」も称賛する仕組みにできます。その他にも、自己研鑽など学びの文化を醸成したい場合は、勉強会やスキルアップの行動に対して通貨を付与することも可能です。
TUNAG上で社内通貨を運用する場合、会社の課題にあわせて通貨の名前・ポイント数・頻度も自由に設定することができます。
実際の企業での事例はこちら:社内通貨・ポイント | 目的別導入事例
※本記事での「ピアボーナス」の使用には、商標権者Unipos(株)から使用許諾を得ています。