ワークショップとは?実施の効果を高める方法やDX推進への活用メリット
DXのような組織変革を推進している中で、ワークショップの導入を考えている企業もあるのではないでしょうか。ワークショップとは何なのかを整理した上で、活用できる具体的な場面を解説します。ワークショップ成功のポイントも紹介しますので、参考にしてみてください。
ワークショップとは?
ワークショップを取り入れたいと考えていても、具体的にどのような教育手法なのか、セミナーと何が違うのか詳しく把握していない企業もあるかもしれません。まずはワークショップの定義や種類、講義形式のセミナーとの違いを整理していきます。
参加者主体の対話型・体験型の教育手法
ワークショップは、参加者が自ら学びや発見を深めるための、体験・対話型の教育スタイルです。実践や意見交換、共同作業を通じて知識を定着させ、技能の向上を促します。
ワークショップの特徴は、参加者同士の相互作用が働く点です。参加者がインプットとアウトプットの両方を通じて、ワークショップのテーマに「自分ごと」として取り組めます。以下に、ワークショップの主な種類を見ていきましょう。
研修型
研修型のワークショップでは、グループごとに特定のテーマについての意見交換、プレゼンテーションを実施します。主に企業や教育機関の研修に用いられるワークショップです。
イベント型
特定分野の専門家から知識や技術を学ぶワークショップは、イベント型と呼ばれます。芸術関係やものづくり・趣味系のワークショップに多く、特殊な業種を除いて企業の教育にはあまり使われないでしょう。
問題解決型
問題解決型のワークショップは、特定の課題についてアイデアを出し合い評価した後、解決策を実行するための計画を立てる手法です。チームワークやブレインストーミングなどの手法を用いて、課題に対してどのような解決策が有効かを探ります。
組織が抱える課題に対して、参加者が主体的に解決策を導き出すことが問題解決型ワークショップの目的です。部署間の連携不全や新サービス企画に向けた議論など具体的な課題を題材にすることが多く、解決策に至るまでのプロセス自体が学びとなります。
講義型セミナーとの違いは「双方向性」
講義型は一方向の情報提供が中心ですが、ワークショップでは参加者同士の双方向的なやりとりが発生します。参加者が主体的に関与し、意見交換や共同作業を通じて学びを深められるのがワークショップの特徴です。
近年では、ワークショップとセミナーの混合型のような研修も見られます。企業の目的に応じて、インプット中心の講義型セミナーと、アウトプットもできるワークショップを併用するのも一つの手です。
ワークショップはどのような場面で活用できる?
ワークショップは単なる教育手法ではありません。企業において、ワークショップは幅広いシーンで活用されています。具体的にワークショップが役立つ場面を三つ見てみましょう。
社員教育やチームビルディング
社員のスキル向上やチームの結束力を高めるために、ワークショップが活用されるケースは少なくありません。この場合、研修型・問題解決型のワークショップが多いです。
社員教育の目的には、知識を習得させることだけでなく、実務で使える能力を身に付けさせることも含まれているはずです。ワークショップでテーマについてディスカッションしたり課題に対して解決策を提案したりすることで、業務を遂行する能力が高まります。
チームビルディングでは、メンバーが互いの責任を把握して組織としての力を向上させていく必要があります。ワークショップでは、共同作業やディスカッションを通じてメンバー間の責任の認識を促進することが可能です。
制度設計や組織変革の合意形成
人事制度の改定や組織再編など、従業員の納得感が求められる施策においてもワークショップは有用です。研修型のワークショップを開催し、従業員間で意見交換をしてもらって記録すれば、現場の意見を反映しやすくなるでしょう。
トップダウンで決定された施策よりも、参加型で進められた施策の方が、従業員の理解と協力を得やすくなります。ワークショップを通じて現場の声を収集し、施策に反映できれば、組織の変化に対する抵抗感の軽減が可能です。
現場を巻き込む「DXワークショップ」も
DX推進においては、経営層と現場の間に温度差が生じて現場の納得感が得られない場合も少なくありません。関係者がDX知識の習得やアイデア出しなどをする「DXワークショップ」を取り入れると、DXの重要性や自社でDXを推進する目的について共通認識を持ちやすくなります。
ワークショップを通じて現場の課題を把握し、新たなニーズの発見につながるのも、DX推進にワークショップを活用するメリットです。DX推進に従業員との温度差を感じている企業は、ワークショップの導入も検討してみましょう。
ワークショップを成功させるポイント
ワークショップを取り入れても、大きな利点である「参加者が主体的に関与し、相互作用が生まれる」という状態をつくれなければ目標を達成できません。成功するワークショップには、どのような工夫が必要なのでしょうか。
現場が主体となる仕組みをつくる
ワークショップを開催しても、従業員が「義務として参加させられている」という意識では、活発な発言や良い相互作用が期待できません。参加者が主体的に関与することで初めて意見交換が活発になり、ワークショップの効果が高まります。
そのためには、まず参加する従業員が興味を持てる・自主性を持って取り組めるテーマ設定が必要です。現場の課題や業務上興味を持てそうなテーマを選択し、ワークショップの内容を設計しましょう。
また、参加者に役割(進行役、タイムキーパー、記録係、発表者など)を割り当てることで、参加者に責任感と主体性を持った行動を促しやすくなります。役割分担は、チームの協力関係を構築するのにも効果的です。
発言しやすい環境をつくる
発言すれば批判される・意見を軽視されるといった環境では、ワークショップで主体的に発言・提案をする参加者が減ってしまいます。
ワークショップでは心理的安全性を確保し、参加者が自由に意見を述べられる雰囲気をつくることが大切です。アイスブレイクやチェックインなどの手法を活用し、リラックスした環境を提供しましょう。
ファシリテーターには適性のある人材を選ぶ
ファシリテーターは中立的な立場で議論を進行し、参加者の意見を引き出す役割を担います。傾聴力、質問力、共感力、タイムマネジメント能力など幅広い能力が必要です。
これらは誰にでも備わっている能力ではないので、元々ある程度の素質を見極めなければなりません。ファシリテーターに近い経験を積んでいる人や、日頃の業務の進め方などから適性がある人を選びましょう。
TUNAGで現場巻き込み型のワークショップを実現
DX推進をはじめとした課題に対応するためのワークショップでは、参加者にワークショップのテーマを自分ごととして捉えてもらう必要があります。そのために使えるツールの1つが、組織エンゲージメントを高める「TUNAG(ツナグ)」です。
社内アンケートで現場のニーズを把握する
TUNAGには社内アンケート機能が備わっており、現場の課題やニーズを収集できます。収集した情報を基にワークショップのテーマや内容を設計すれば、参加者が当事者意識を持って臨めるワークショップが実現するでしょう。
TUNAGの社内アンケートは項目を自由にカスタマイズできるため、ファシリテーターに適任の人物について意見を集めることも可能です。また、ワークショップ終了後に参加した感想を聞くのにも役立ちます。
社内チャットやタイムラインで意見を発信しやすい土台をつくる
社内全体でコミュニケーションが活性化すると、ワークショップでも自然と参加者が発言しやすい環境をつくりやすくなります。日頃から活発にやりとりできていれば、発言のハードルがグッと下がるでしょう。
発言しやすい土台づくりの方法として、TUNAGの社内チャットやタイムライン機能・コメント・リアクション機能を活用した、日常的なコミュニケーションの促進が挙げられます。コメントに抵抗がある従業員でも、リアクションであれば気軽にできることもあるはずです。
社員プロフィールでファシリテーター候補を把握・共有する
TUNAGの社員プロフィール機能では、社員番号のようなオフィシャルなデータだけでなく、「人となり」が分かる項目を設定することも可能です。強みや特技など、普段の業績や勤務態度からは分からない要素を見て、ファシリテーターとしての適性が判断できることもあります。
ファシリテーターはワークショップにおいて重要な役割ですが、適性を持つ人材を見つけるのは簡単ではありません。社員プロフィールのようにオフの人物像まで分かる機能を活用すれば、ファシリテーターの選定がスムーズになります。
現場を巻き込んでワークショップを取り入れよう
ワークショップとは、参加者が主体的に発言や提案をしながら学んだり気付きを得たりする教育手法です。講義型のセミナーと違って双方向性があり、インプットと同時にアウトプットも可能、参加者同士の相互作用を期待できるという点が特徴です。
企業で活用できるワークショップは、特定のテーマについて意見交換をする研修型や、課題に対するディスカッションや解決策の提案をする問題解決型が主です。実務スキルまで身に付けさせたい社内教育やチームビルディング、DXを含む組織の変革に対する理解の促進といった場面で活用できます。
ワークショップで期待していた効果を実感するには、現場が主体となって取り組めるテーマ設計が必要です。発言しやすい環境づくり、ファシリテーターの適切な選定も求められます。
現場の声をしっかりと拾いながらコミュニケーションを活性化させ、ツールも用いながらファシリテーターの選定を進めましょう。従業員が自分事として活発に発言できるワークショップは、企業の課題解決につながります。




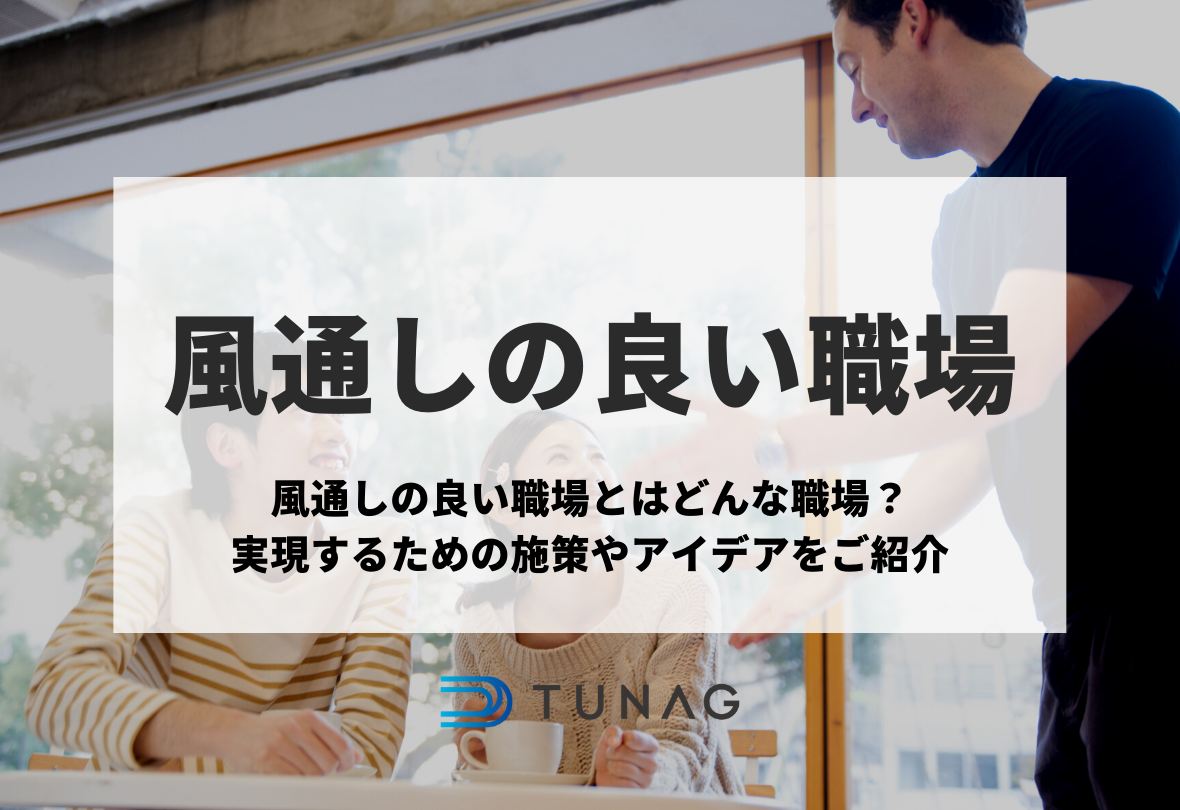
.webp&w=3840&q=75)







