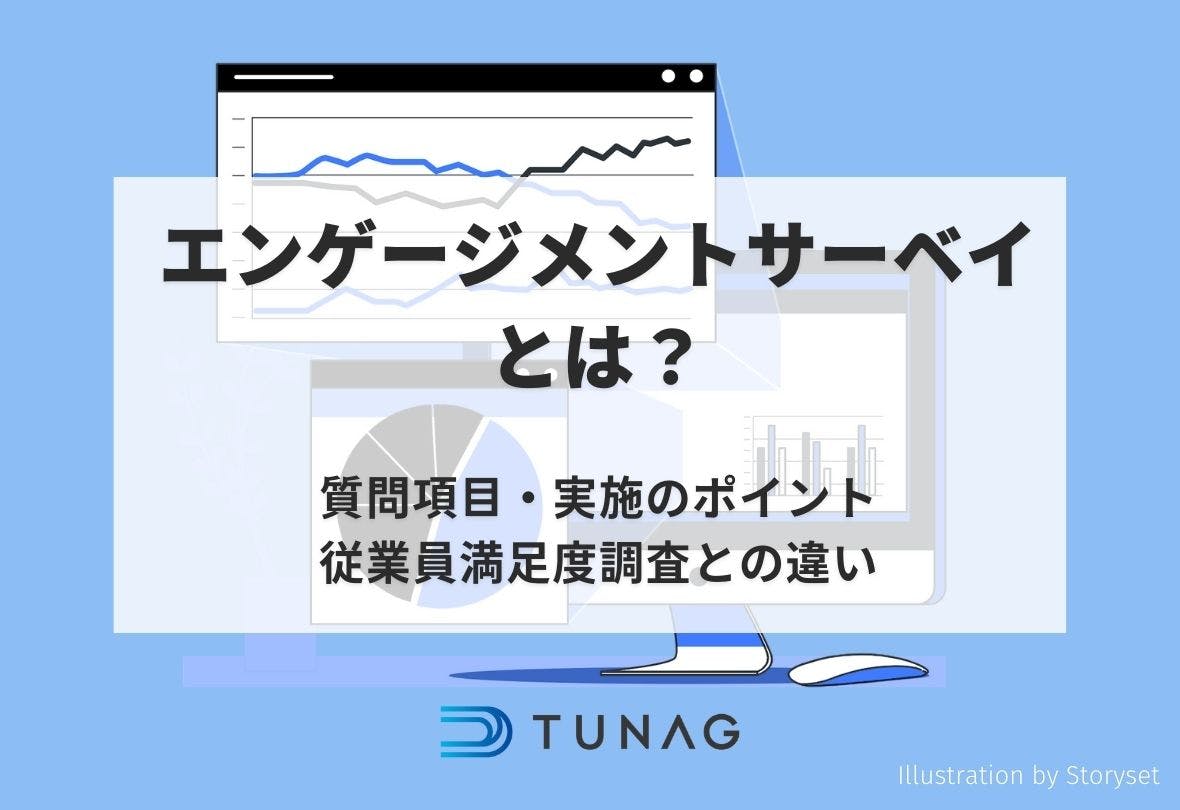サーベイとリサーチの違いとは?使い分け方と活用シーンを分かりやすく解説
企業活動では、現状把握や課題発見の手段として「サーベイ」や「リサーチ」がよく活用されます。しかし、サーベイとリサーチの違いを十分に理解しないまま両者を使っているケースも少なくありません。本記事では、サーベイとリサーチの基本的な違いを整理し、それぞれの適切な使い分け方や活用シーンを解説します。両者の違いを正しく理解し、組織課題の可視化と解決に役立てましょう。
サーベイとリサーチの基本的な違い
サーベイ(survey)とリサーチ(research)はどちらも調査を意味しますが、その手法や活用シーンには違いがあります。
サーベイは対象を広く設定し、多数の意見や傾向を集めることが目的です。例えば、組織の満足度やエンゲージメントなどを可視化する際に使われ、組織全体の概要を把握するのに適しています。
一方リサーチは、特定の課題やテーマを掘り下げて、より深く専門的に調べるために行われます。問題点が明確に浮かび上がった際に、その背景や要因を詳しく分析する際に有効な手法です。
このようにサーベイは広く浅く意見を集めるのに対し、リサーチは狭く深く課題を追求する調査方法といえるでしょう。
サーベイとアンケート、アセスメントとの違い
「サーベイ」と似たような意味で使われる言葉に「アンケート」や「アセスメント」がありますが、それぞれの役割や目的には違いがあります。
サーベイとは、調査活動全体を指す概念であり、その中で行われる個々の質問票を指しているのがアンケートです。
例えば従業員満足度サーベイを実施するとき、その具体的な手法として用いられるのがアンケートというわけです。
一方、アセスメントは「評価」に特化した手法であり、個人の能力や組織状態を客観的に測定します。具体的なスキルや能力を把握し、人材配置や育成計画の策定などに活用するのがアセスメントです。
このようにサーベイは情報収集を目的とした調査であり、アセスメントは能力や状態を測るための評価手法として位置づけられています。
サーベイの種類と特徴
次に、人事・組織領域でよく使われる各種サーベイの特徴を押さえておきましょう。
サーベイとひと口に言ってもさまざまな種類があり、目的に応じて適切なものを選ぶ必要があります。ここでは代表的な三つのサーベイについて解説します。
従業員サーベイ
従業員サーベイとは、職場環境や人間関係、仕事に対する満足度など、従業員の率直な意識を捉えるための調査方法です。
特に従業員満足度調査や意識調査の一環としてよく活用され、企業の離職防止、生産性向上、さらには組織風土の改善に役立てられています。
従業員サーベイでは部署ごとの傾向や課題も把握できるため、企業全体に対する施策だけでなく、現場レベルでの具体的な改善にもつなげやすいというメリットがあります。
このサーベイを通じて得られるデータは、企業にとっていわば健康診断のような役割を果たし、組織の現在の状態を客観的に把握し、より良い職場づくりに向けた第一歩を踏み出す基盤となります。
エンゲージメントサーベイ
エンゲージメントサーベイは、従業員が企業や自身の仕事にどの程度愛着や情熱を持っているのかを可視化するための調査です。
「会社で働くことに誇りを感じているか」「自身の仕事が正当に評価されていると感じるか」といった質問を通して、従業員の企業への忠誠心や仕事へのモチベーションを数値化します。
その結果からエンゲージメントを高める障害となっている要因が特定され、的確な改善施策を打つことが可能になります。また、定期的に実施すれば施策後の効果検証にも使えます。
従業員の定着率改善やエンゲージメントの向上を促すだけでなく、生産性や業績アップにもつながる重要な経営指標として位置付けられています。
パルスサーベイ
パルスサーベイは、短期間に何度も継続して実施することで、従業員の状況や職場の雰囲気の変化をリアルタイムに近い形で把握するための手法です。
週単位や月単位などの高い頻度で短いアンケートを行い、従業員のモチベーションやストレス状況を即座に捉えることができます。
この手法の大きな利点は、従来の調査では把握できない急激な変化や微妙な変動をいち早く見つけられることで、問題が深刻化する前に迅速な対応を取ることが可能になります。
また、設問数を絞り込むことで回答者の負担が少なく、回答率も高く保たれます。
リモートワークが普及した現在の働き方にも適した方法で、日々の組織マネジメントや従業員へのタイムリーなフォロー体制の構築に役立つ、現代型のサーベイ手法といえるでしょう。
サーベイとリサーチの活用シーン
ここまで、サーベイとリサーチの基本的な違いや、それぞれの種類を見てきました。最後に、この二つの調査手法をどのような場面で使い分け、活用することで効果的なのかを整理しておきましょう。
それぞれの特性を理解して組み合わせることにより、組織の意思決定や改善施策の精度を高めることが可能になります。
サーベイが効果を発揮するビジネスシーン
サーベイは、多くの対象から意見や状況を広く把握したいときに役立つ調査手法です。主に、以下のようなシーンで活用されます。
- 定期的な従業員満足度調査を行い、離職防止や働き方改革につなげる
- 新制度導入の前後で期待感や満足度を測り、研修効果を検証する
- 顧客満足度調査を実施し、製品やサービスの改善ポイントを明らかにする
- マーケットの消費者動向やトレンドを把握し、戦略立案や新製品開発のヒントを得る
サーベイはまず全体の傾向や実態を把握するために最初に活用すべき、基本的かつ重要な手法だといえるでしょう。
リサーチが求められる場面とその具体例
リサーチは、特定の課題に対してより深い理解や解決策を見いだしたいときに求められます。主に以下のようなシーンで活用されます。
- 新規事業を立ち上げる前に市場のニーズや差別化ポイントを具体的に掴。
- 従業員の離職率が高い部門においその理由や背景を探り、効果的な定着支援策を検討する
このように、リサーチは狭い範囲を深く掘り下げることで、的確で納得感のある意思決定を支える調査手法といえます。
サーベイとリサーチを組み合わせて活用する方法
サーベイとリサーチは単体でも有効ですが、組み合わせることでより精度の高い意思決定を支える強力なアプローチとなります。特に、以下のようなシーンで有効です。
- 定期的な従業員サーベイで組織全体の状況を把握し、課題が浮き彫りになった部署に対して、詳細なリサーチを行い、具体的な施策を策定する
- 顧客満足度サーベイで特定の商品やサービスの評価が低かった場合、その理由を掘り下げるためにフォーカスグループや顧客インタビューを実施し、製品改善につなげる
- エンゲージメントサーベイを通じて企業文化への不満が確認された場合、従業員へのインタビューやワークショップを開催し、真の課題を探り出して改善策を練る
サーベイで現状を定点観測し、重要局面ではリサーチで裏付けを取る。この使い分けこそが、戦略的で実効性のある組織改善や事業推進の鍵となるのです。
サーベイとリサーチの違いを正しく理解し、課題解決に生かす
「サーベイ」と「リサーチ」はどちらも情報収集の手段ですが、その目的や手法には明確な違いがあります。サーベイは広く全体の傾向を捉えるために、リサーチは特定のテーマを深掘りするために行うものです。
どちらも重要ですが、大切なのは「何を知りたいのか」「なぜ調べるのか」という視点を明確にし、目的に応じて最適な手法を選ぶことです。そうすることで、収集したデータが実践的な意思決定につながり、組織の課題解決に直結します。
経営層や人事担当者にとっては、定期的な従業員サーベイによる組織状態の可視化が第一歩となります。その上で、必要に応じてリサーチを組み合わせれば、表面的な課題だけでなく、その背景や真因にまで迫ることができます。
サーベイとリサーチを上手く使い分けることは、エンゲージメント向上や離職防止、ひいては企業の健全な成長に欠かせません。
こうしたデータに基づく組織づくりを後押しするのが、組織改善ツール「TERAS(テラス)」です。従業員の声をリアルタイムで可視化し、組織課題を正確に捉え、改善施策の立案から実行までを一気通貫でサポートします。
調査だけで終わらせず、「行動」につなげる仕組みが整っています。サーベイとリサーチの知見を、貴社の組織改善にぜひお役立てください。
▼詳細はこちらから
TERAS(テラス)公式サイト|エンゲージメントを高める組織改善ツール