人的資本をわかりやすく解説。企業成長に不可欠な理由と実践ポイント
人的資本とは、従業員が持つスキル・知識・経験・健康・モチベーションなど、企業の競争力を高める無形資産のことです。近年、人的資本開示の義務化やサステナビリティ経営の観点から注目が集まっています。本記事では、人的資本の基本概念や活用するメリット、実践のポイント、企業事例までをわかりやすく解説し、経営層や人事担当が明日から動ける実務知識を提供します。
人的資本とは?
近年は、従業員を単なるリソースではなく、「資産」として捉える考え方が注目されています。
「人的資源」との違いを理解すれば、企業にとって人材がどれほど価値ある存在かが見えてくるでしょう。
この章では、人的資本の定義と従来の「人的資源」との違いを解説します。
人的資本の定義
人的資本とは、従業員が持つスキル、知識、経験、創造力、健康状態、モチベーションなど、企業の生産性や業績に直接・間接的に貢献する要素を総合的に捉えた概念です。
これらは財務諸表には記載されませんが、イノベーションの創出や顧客満足の向上、新たな市場開拓などに深く関わるため、企業の中長期的成長にとって不可欠な資産といえます。
昨今では、従業員エンゲージメントや組織文化、職場の心理的安全性なども人的資本として評価されるようになり、人的投資の対象領域が広がっています。
人的資本と人的資源の違い
人的資源(Human Resources)は、主に労務管理や人件費など「コスト」の視点から人材を管理する考え方で、従来の労働集約型経営において主流でした。
一方、人的資本(Human Capital)は、人材が価値を生み出す存在であると捉え、「投資対象」として成長支援や環境整備を重視します。
人的資源では業務の効率性が重視されるのに対し、人的資本では従業員の創造性や主体性が評価されます。
人的資本が注目される背景
人的資本が企業経営の中で重要視されるようになった背景には、社会構造の変化があります。
本章では、人的資本が注目を集める理由を4つの観点から詳しく解説します。
人的資本開示の義務化
日本では、2023年1月31日に「企業内容等の開示に関する内閣府令」などが改正され、人的資本に関する情報開示が義務化されました。この改正により、対象企業は有価証券報告書の2カ所において、人的資本に関する情報を記載することが求められます。
まず、「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」「男女間の賃金格差」という多様性に関する3つの指標が記載されることが義務付けられました。
加えて「戦略」や「指標及び目標」に関する記載も必須となっています。具体的には、「人材育成方針」や「社内環境整備方針」などを戦略として明示し、それに基づく指標の内容や実績、目標達成状況を報告することが求められます。
非財務情報の重要性が増している
企業価値の評価基準が「財務指標」から「非財務指標」へとシフトしています。
知的財産、ブランド、組織文化と並び、人的資本などの「非財務指標」は企業の競争優位性を支える最重要項目とされます。
投資家やステークホルダーも人的資本への取り組みを企業評価に取り入れており、「非財務指標」の重要性が高まっています。
働き方や人材の多様化
テレワークの普及、副業の解禁、育児や介護との両立支援、そして外国人・高齢者・女性の活躍推進など、働き方や労働力の構成は大きく多様化しています。
このような変化の中では、画一的なマネジメントや制度では対応しきれず、個人の状況や価値観に応じた柔軟な対応が求められます。
人的資本経営では、従業員一人ひとりの能力や希望を尊重し、それぞれの強みを活かした配置や育成を行うことが重要です。多様性を尊重した経営姿勢は、イノベーション創出や組織活性化にもつながります。
サステナビリティへの関心の高まり
人的資本は「ESG」の中でも「S(Social)」の中核的存在と位置づけられます。労働環境の整備、公平な待遇、多様性と包摂性の推進といった取り組みは、単なる福利厚生を超えて企業の社会的責任(CSR)を果たす行動と見なされます。
また、サステナブル経営における人材戦略は、企業のブランド価値や採用力にも直結します。人的資本の強化は、環境・社会・ガバナンスの全体的バランスを整える鍵ともいえるでしょう。
人的資本経営のメリット
人的資本経営に対するアプローチを実践することで、企業にとって多面的なメリットがもたらされます。
この章では、人的資本経営が具体的にどのような効果をもたらすのかを3つの視点から解説します。
採用力の強化
企業が人的資本を大切にし、その取り組みを明確に発信することで、「この会社で働きたい」と思う候補者が増えます。
実際、働きがいや育成方針が明示されている企業は、求職者にとって魅力的に映ります。
採用段階から企業の価値観が伝わることで、入社後の定着率やエンゲージメントの向上にも貢献するでしょう。
従業員の能力やスキルを可視化できる
人的資本の価値を最大化するには、従業員一人ひとりのスキルや経験、志向性を可視化することが不可欠です。
人事データを定量的に分析することで、配置や育成の最適化が可能になります。
たとえば、スキルマップを導入すれば、成長が見込まれる領域やスキルギャップが一目で把握でき、適切な教育投資の判断材料になります。
キャリア形成の支援にもつながり、従業員のモチベーション維持・向上にも寄与するでしょう。
従業員のエンゲージメントが向上
人的資本経営では、従業員の声を尊重し、働きやすい環境を整える取り組みが進められます。
その結果として、組織に対する信頼や共感が高まり、従業員エンゲージメントが向上します。
心理的安全性の高い職場や、定期的な1on1ミーティングの実施、柔軟な勤務制度の導入などは、従業員の満足度を高める施策の一例です。
エンゲージメントの高い社員は生産性が高く、離職率も低くなるため、企業の持続的成長に直結します。
人的資本開示と「ISO 30414」の関係について
人的資本を可視化し、投資家やステークホルダーに対して説明責任を果たすには、一定の国際的な指標やガイドラインを参照することが重要です。
中でも「ISO 30414」は、人的資本に関する情報開示を行ううえでグローバルに活用されている指針です。本章では、「ISO 30414」の概要と、その評価指標の構成内容について紹介します。
「ISO 30414」とは
ISO 30414は、人的資本に関する情報開示の国際的なガイドラインとして、2018年に国際標準化機構(ISO)によって制定されました。
この規格は、企業が人材に関する施策や成果を定量・定性的に測定・開示する枠組みを提供するもので、透明性のある人事戦略の実現を支援します。
投資家や社会に対して、人的資本の運用状況や成果を信頼性のある形式で伝えることで、企業価値の向上や信頼の獲得に繋がります。
「ISO 30414」の評価領域
ISO 30414では、11の評価領域が定められており、人材マネジメントに関する包括的な視点を提供します。
対象には「リーダーシップ」「エンゲージメント」「ダイバーシティ」「健康と安全」「生産性」「採用・育成」「離職率」などが含まれます。
これらは数値(KPI)と質的記述の両面で評価され、組織の人的資本の健全性や課題を可視化するツールとして活用されます。
人的資本を向上させるポイント
人的資本の価値を高めるためには、経営者や人事部門が戦略的かつ継続的に取り組むことが必要です。
そのためには、人的資本の「可視化」と「活用」を両輪として、実効性ある施策を組み合わせていくことが重要です。
本章では、人的資本を強化するうえで押さえておくべき実践ポイントを紹介します。
資本の可視化とデータの活用
人的資本を管理・改善する第一歩は、定量的な指標を設定し、現状を把握することです。
たとえば、従業員満足度調査、離職率、スキル評価、研修受講率といったKPIを用いて、組織の健康状態を定期的にモニタリングします。
データの可視化によって、問題の早期発見と施策の優先順位付けが容易になり、意思決定の精度も高まります。こうした取り組みは、PDCAを回す上でも極めて有効です。
人材の価値を上げる
人的資本の質を高めるには、従業員のスキルアップを支援する制度の整備が重要です。具体的には、OJTの仕組み化、社内研修の強化、リスキリング支援、キャリアパス制度の導入などが挙げられます。
特に、自己成長意欲の高い人材に対しては、自律的なキャリア設計を支援する環境が求められます。企業が学びの機会を提供し続けることは、従業員エンゲージメントの向上にも直結するでしょう。
HRテックを活用する
スキルマップの作成、配置・育成のシミュレーション、人事KPIの自動集計などを実行するためのタレントマネジメントシステムや人事分析ツールの導入により、人的資本の見える化と活用は大きく進展します。
人的資本の価値について、数値によってフェアに判断することが可能です。また、ツールで集計したデータは一目で人的資本の価値や特性を把握できるため、経営層への報告・戦略立案にも有効です。
労働環境を改善する
どれだけ優秀な人材を採用・育成しても、働く環境が整っていなければ人的資本の価値は発揮されません。
心理的安全性の確保、ハラスメント防止、柔軟な勤務制度、ウェルビーイングの推進など、働く人が安心・快適に過ごせる職場づくりが前提です。
職場環境の質は離職率や生産性に直結するため、経営課題として継続的に取り組むことが求められます。
人的資本の価値向上に取り組んだ事例
先進的な取り組みを行う企業の事例からは、人的資本の可視化や施策の成果がどのように組織成長につながるかを学ぶことができます。
この章では、ISO 30414に準拠した取り組みや、多様性・育成強化を実現した2社の具体例を紹介します。
旭化成株式会社
旭化成株式会社は、経営戦略に基づき、人材ポートフォリオを動的に拡充しています。
毎年、事業や機能に必要な人材の質と量を洗い出し、新卒採用や社内育成を計画的に実施。必要な人材が確保できない場合、M&Aやコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)、少額投資を活用し、外部からの人材獲得を進めています。
また、従業員エンゲージメントの向上に向けて、「KSA(活力と成長アセスメント)」を用いて職場環境や活力を調査。これにより、従業員の活力向上と組織全体の生産性向上を実現しています。
人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書 ~人材版伊藤レポート2.0~ 事例-01|旭化成株式会社
アステラス製薬株式会社
アステラス製薬株式会社は、経営戦略に沿った組織・文化・人材の創造を目指し、人的資本経営を推進しています。
まず、経営層と事業部門と共に戦略を実現するために、グローバルHRヘッドを招聘し、人事部門の役割を進化させています。
また、全社一体でパフォーマンスの高い組織を作るため、組織健全性を目指した目標を設定し、社内文化やマインドセットの浸透に努めています。
これにより、グローバルに多国籍の経営陣が形成され、組織の競争力が強化されています。
人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書 ~人材版伊藤レポート2.0~ 事例-02|アステラス製薬株式会社
人的資本を理解し、企業成長に活かす
人的資本は、目に見えないながらも企業の将来を左右する経営資源の一つです。
スキル、経験、モチベーション、健康など、従業員が持つ無形の価値を「見える化」し、組織として戦略的に活用していくことが、持続可能な成長の鍵となります。
まずは、現状をデータで把握し、課題を洗い出し、改善と制度化を図ることが第一歩です。
人的資本への正しい理解と投資が、企業の未来を切り拓く基盤となります。




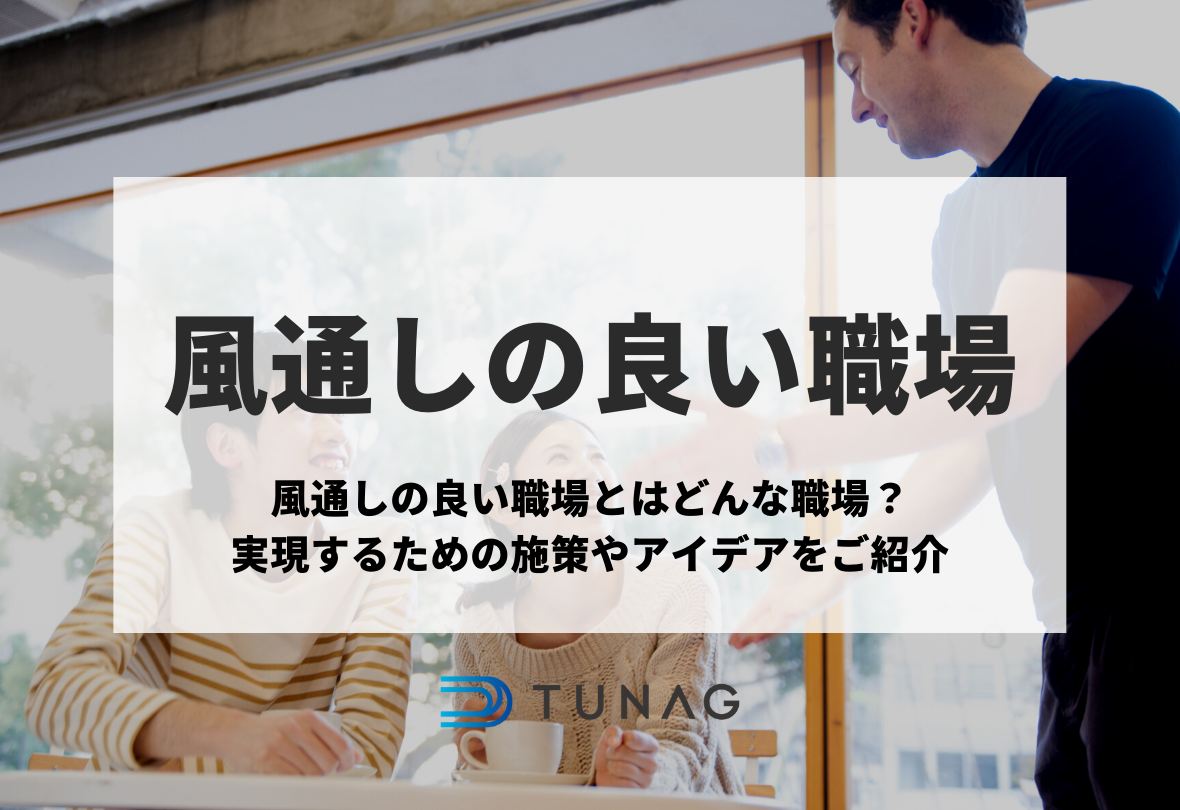
.webp&w=3840&q=75)







