マトリックス組織とは?他の組織との違いやメリット・デメリットなどを解説
マトリックス組織は、従来の縦割り組織の枠を超えて、職能や事業など複数の軸を組み合わせて運営される組織形態です。変化の激しいビジネス環境に対応しやすい形態といわれているので、他の組織との違いや、メリット・デメリットを知っておきましょう。
マトリックス組織とは?
マトリックス組織は、職能や事業部・エリア別など、異なる組織形態を2つ以上掛け合わせて構成されます。従業員は通常、職能別の部門とプロジェクトや事業部といった、別の軸にも同時に所属し、それぞれの上司から指示を受けるのが一般的です。
まずはマトリックス組織の基本的な構造と、注目される理由について、知っておきましょう。
マトリックス組織の基本構造
マトリックス組織とは、職能別の専門性とプロジェクト単位の目標達成といった、2つの軸を掛け合わせた組織形態です。縦軸には機能(開発部門、営業部門など)を、横軸にはプロジェクトや製品ラインなどを配置し、それぞれの従業員が両方の指揮命令系統に属するのが特徴です。
同構造により、企業は専門性を維持しつつ、プロジェクト単位での迅速な対応や柔軟なリソース配分が可能になります。一人の社員が複数の上司を持つ場合もあり、情報伝達や意思決定が複雑になる半面、複数の視点からの指導や調整が実現できる仕組みです。
組織の壁を越えた協力体制が求められる業界や、多様な商品・サービスを展開する企業において特に効果を発揮する組織形態として注目されています。
マトリックス組織が注目されたきっかけ
マトリックス組織が広く注目されるようになったのは、グローバル化や技術革新の加速、消費者ニーズの多様化といった、ビジネス環境の変化があります。従来の縦割り型の組織では、部門間の連携不足や意思決定の遅れが問題となることが多く、そうした課題を克服するために導入された背景があります。
特に1970年代以降、航空宇宙産業や製薬業界・IT業界などでは、複雑なプロジェクトの管理に対応できる組織形態として急速に導入が進みました。
複数の部門が培ってきた知見を融合し、プロジェクト単位で成果を最大化しやすい点が評価され、近年はグローバル企業を中心に導入が拡大しています。
他の代表的な組織形態との違い
マトリックス組織は、従来の機能型組織やプロジェクト型組織・事業部制組織とは、異なる特徴を持っています。それぞれの組織形態との違いを理解しておきましょう。
機能型組織との違い
機能型組織は、業務内容に応じて部署を構成する伝統的な組織形態です。営業部門・開発部門・総務部門といったように、機能別に明確に分かれており、各部門が独自の専門性を持って業務を遂行します。
一方、マトリックス組織は機能型組織の構造をベースにしつつも、プロジェクト単位での指揮命令系統を加えた点が大きく異なります。
機能型組織では、情報や意思決定が縦の流れに限られがちですが、マトリックス組織では横のつながりが重視されるのが特徴です。横のつながりが強いため、製品開発や市場対応のスピードや、意思決定の柔軟性を高められるのが強みです。
プロジェクト型組織との違い
プロジェクト型組織は、特定のプロジェクトの達成を目的として、メンバーを一時的に集めて編成する組織です。プロジェクトの完了とともに解散するのが一般的で、権限と責任が明確であることから、迅速な意思決定が可能です。
しかし専門知識やノウハウの蓄積や、人材の継続的育成という面では課題もあります。マトリックス組織はこうした利点を取り入れつつ、機能別の専門部署に属する形を保つのが特徴です。これにより継続的なプロジェクト運営と、人材育成の両立を図れます。
事業部制組織との違い
事業部制組織は、製品別や地域別などの単位で独立した事業部を設け、それぞれがある程度の権限と責任を持って運営される組織形態です。市場に応じた機動的な対応ができる一方で、事業部間の連携がおろそかになることがあります。
マトリックス組織では、こうした縦割りの弊害を避けるために、複数の指揮系統を組み合わせることで、事業横断的な連携を実現します。事業部制では「縦」の分権が中心ですが、マトリックス組織では「縦」と「横」の両方を機能させることで、全社的な調整力を高めているのが特徴です。
マトリックス組織の類型
上記のように、マトリックス組織と他の組織形態では、さまざまな違いがあります。しかしマトリックス組織にもいくつかのタイプがあり、それぞれ特徴や運用上のポイントがあるので、基本的なところを押さえておきましょう。
ストロング型
ストロング型のマトリックス組織では、プロジェクトマネージャーの権限が強く、メンバーに対して直接的な指示や評価を行います。プロジェクトの進行が円滑に進みやすく、スピード感のある意思決定が可能です。
しかしプロジェクトや事業部の権限が強く、職能部門よりもプロジェクトリーダーや事業部長の指示が優先される傾向にあります。プロジェクトの推進力が高まる一方で、職能部門の専門性や標準化が後回しになる可能性もあるため、組織運営にはバランス感覚が必要です。
ウィーク型
ウィーク型は機能部門のマネージャーが主導権を握る、マトリックス組織の形態です。プロジェクトマネージャーは調整役にとどまり、メンバーに対する評価・指揮などは、主に機能部門のマネージャーが担います。
この構造では、部門としての一貫性が保たれやすく、専門性の維持・向上に有利です。しかし、意思決定の遅れが生じやすく、状況変化への即応性に課題が残る場合もあります。明確な役割分担とともに、組織内のコミュニケーションを円滑にする仕組みの設計が、運用上のポイントです。
バランス型
バランス型はプロジェクトマネージャーと、機能部門のマネージャーがほぼ対等な権限を持ち、協力しながらプロジェクトを推進する形態です。双方が責任を分担しながら進めるため、柔軟かつ全体最適を意識した運営が可能です。
ただし、対等な権限故に意思決定のスピードが遅れる場合もあり、調整のための会議やコミュニケーションが頻繁に求められます。組織内での信頼関係や役割の明確化が不可欠で、パワーバランスの維持が難しくなるケースも多いため、運用には高いマネジメント力が必要です。
マトリックス組織のメリット
マトリックス組織は、複数の視点を持つ体制を築ける点で、変化の激しい市場や複雑な業務に対応しやすいのがメリットです。専門性と柔軟性を両立させることで、組織の対応力・競争力を高められます。
機能部門とプロジェクト部門の両方から支援を受けられるため、人材は高い専門性を維持しながら、複数の業務領域を横断的に経験できるでしょう。視野の広い人材を育成しやすくなるほか、職務の多様性によるモチベーションの向上も期待できます。
また、プロジェクト単位で必要なリソースを柔軟に再配分できるため、状況に応じて迅速な対応が可能です。例えば、新規事業や海外展開のように、機能別の組織単体では難しい意思決定が多い場面でも、プロジェクト単位で一気に進められる強みがあります。
さらに、組織全体で専門知識やリソースを共有しやすいため、重複した業務や非効率な投資を避けられるのもメリットです。
マトリックス組織のデメリット
マトリックス組織は、柔軟な意思決定を実現しやすい一方で、運用には高度なマネジメント力が必要です。機能部門とプロジェクト部門の双方に属する構造上、役割や権限が曖昧になりやすく、意思決定や責任の所在が不明確になるケースがあります。
例えば、同じ社員が2人の上司を持つ状態が常態化することで、どちらの指示を優先すべきか迷い、業務が停滞する事態も起こり得るでしょう。特に、プロジェクトの優先度や方向性に対する認識が、機能部門と食い違っていた場合には、現場での混乱が大きくなります。
また、自律的に動ける社員や、対話力・調整力のあるマネージャーが欠けていると、組織が機能不全に陥りやすくなる点も注意が必要です。適切な人材が不足しているとマトリックス構造の強みを生かしきれないため、導入に当たっては、自社に合った形態か慎重に判断しなければいけません。
マトリックス組織の運営を成功させるには?
マトリックス組織を円滑に機能させるためには、上下関係ではなく横の連携を重視する文化の定着や、情報共有の仕組みの徹底が必要です。機能部門とプロジェクト部門の両者が対等に協力できるように、信頼関係を築く仕組みを考えましょう。
評価制度や目標管理も個人単位だけではなく、部門間の協働成果を重視した内容にすることで、対立ではなく協働を促すことも重要です。
また上記のように、マトリックス構造に適した人材の育成も欠かせません。複数の指示系統の下で働く社員には、自律性や柔軟性・コミュニケーション力が求められます。
一方で、マネージャーに高いバランス感覚と調整能力がなければ、スムーズな意思決定が難しくなります。これらの資質は一朝一夕で身に付くものではないため、早い段階から人材育成に注力しましょう。マネージャー同士の連携を徹底し、指示の齟齬や対立を防ぐ仕組みも必要です。
マトリックス組織の特徴を理解する
マトリックス組織は、機能的な専門性とプロジェクトごとの柔軟性を両立できる組織形態として、さまざまな業界で注目されています。
一人の社員が複数の上司に報告する体制や、機能部門とプロジェクト部門を両立する仕組みは、従来型の組織にはない特徴です。複雑な業務や市場変化に対応しやすい一方で、明確なルールや信頼関係がなければ、機能不全に陥るリスクも高くなります。
これからマトリックス組織を導入・運用するならば、単なる組織図の変更にとどまらず、組織文化や評価制度、人材育成などを含めた包括的な設計が必要です。特に、人材の育成には時間がかかるので、早い段階から自律的に動ける人材や、調整力・対話力に優れたマネージャーの育成に力を入れましょう。




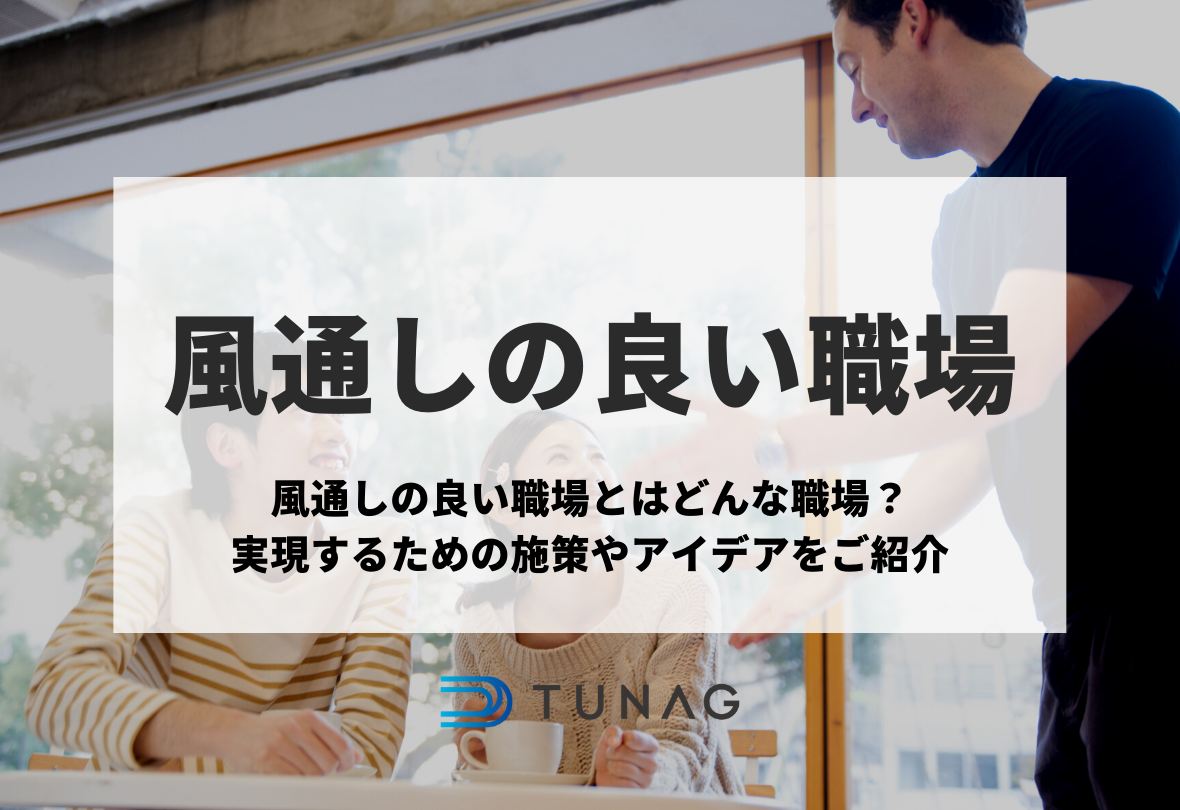
.webp&w=3840&q=75)







