クレドとは?作り方や浸透方法、目的や効果を解説
従業員の価値観が多様化する中で、組織としての一体感をいかに醸成するかが課題となっている、若手社員の離職が止まらない。このような課題に直面していませんか?これらの問題を解決する鍵となるのが「クレド」です。本記事では、クレドの本質的な意味から、具体的な作成方法、形骸化を防ぐ浸透施策、さらに成功企業の事例まで詳しく解説します。
クレドとは?組織変革を実現する行動指針の本質
組織の一体感が薄れ、従業員の価値観が多様化する現代において、クレドは企業が進むべき方向を示す羅針盤となります。単なる理念の掲示ではなく、日々の業務における具体的な判断基準として機能する、実践的なマネジメントツールとして注目を集めているのです。
クレドの定義
クレドとは、ラテン語で「信条」「志」「約束」を意味する言葉です。企業においては、従業員が日々の業務で判断に迷った際の拠り所となる価値観や行動基準を明文化したものを指します。
クレドの起源は1943年、ジョンソン・エンド・ジョンソンの3代目社長ロバート・ウッド・ジョンソンJr.が作成した「我が信条(Our Credo)」にさかのぼります。第二次世界大戦の混乱期において、企業が社会的責任を果たすための行動指針として生まれました。当時としては画期的だった「顧客第一」「従業員への責任」「地域社会への貢献」「株主への責任」という4つの責任の優先順位を明確に示したことで、現代のクレドの原型となったのです。
経営理念やビジョンをより具体的な行動レベルに落とし込んだものがクレドの本質です。例えば「お客様第一」という理念があったとしても、それだけでは現場での判断に迷います。
クレドでは「お客様からのお問い合わせには24時間以内に返答する」というように、誰もが実践できる具体的な行動として表現します。従業員が現場で迷った時、上司の指示を待たずとも適切な判断ができるよう設計されているのがクレドの特徴なのです。
経営理念・ミッション・ビジョン・バリューとクレドの違い
企業の価値観を表す言葉は複数存在しますが、それぞれに明確な役割があります。
経営理念は企業の存在意義や根本的な考え方を示すものです。ミッションは企業が果たすべき使命、ビジョンは将来のあるべき姿を描きます。バリューは組織が大切にする価値観を表現したものです。
一方、クレドはこれらすべてを踏まえ、従業員一人ひとりの具体的な行動レベルに落とし込んだ日常的な行動指針として機能します。抽象的な理念を具体的な行動に変換する「翻訳装置」のような役割を果たすのです。
例えば、バリューが「革新性」であれば、クレドでは「新しいアイデアは必ず検討し、実現可能性を探る」という行動指針になります。このように、クレドは理念と現場をつなぐ架け橋として機能するのです。
なぜ今クレドが必要なのか?
現代の企業が直面する課題は複雑化しています。リモートワークの普及により、物理的な距離が生まれ、組織の一体感を保つことが困難になりました。世代間の価値観の違いも顕著になり、共通の行動基準を持つことの重要性が増しているのです。
また、スピード経営が求められる中、現場での即座の判断が必要な場面が増えています。すべての判断を上層部に委ねていては、ビジネスチャンスを逃してしまいます。クレドがあることで、従業員一人ひとりが判断に迷った際の助けとなり、自信を持って行動しやすくなります。
さらに企業の社会的責任が問われる時代において、従業員の行動一つひとつが企業ブランドに直結します。クレドは全従業員が企業の代表として社会からの信頼に応えるための指針となり、結果として企業ブランドを守る防波堤の役割も果たすのです。
クレド導入による組織変革の5つの効果とメリット
クレドを導入することで得られる効果は多岐にわたります。単に理念を共有するだけでなく、組織全体のパフォーマンス向上や従業員満足度の改善など、測定可能な成果として現れることが、多くの企業で実証されています。
従業員エンゲージメント向上による離職率の改善
クレドの導入は、従業員エンゲージメントの向上に直結します。自分の行動が企業の価値観と一致していることを実感できれば、仕事への誇りと充実感が生まれます。
実際に、クレドを導入した企業では離職率が大幅に改善されています。従業員が「なぜこの仕事をしているのか」「どのように貢献しているのか」を明確に理解できるようになるからです。特に若手社員にとって、仕事の意義を見出せることは継続就業の大きな動機となります。
またクレドは採用段階でのミスマッチを防ぐ効果もあります。企業の価値観を明確に示すことで、その価値観に共感する人材が集まりやすくなるのです。採用面接でクレドを共有し、応募者の価値観との適合性を確認することで、入社後の早期離職リスクを大幅に低減できます。
結果として定着率の高い組織づくりが可能になり、採用コストの削減にもつながるのです。
現場判断力の向上と主体的な人材育成の実現
クレドは従業員の判断力を養う教育ツールとしても機能します。具体的な行動指針があることで、従業員は自信を持って判断し、行動できるようになります。
マニュアルとの違いは、状況に応じた柔軟な対応が可能な点です。クレドは「なぜそうするのか」という理由も含んでいるため、想定外の状況でも応用が利きます。これにより、指示待ちの姿勢ではなく、主体的に考え行動できる人材の育成を促進します。
管理職にとっても、部下への指導基準が明確になるメリットがあります。「クレドに照らし合わせるとどうか」という共通の判断軸があることで、一貫性のある指導が可能になるのです。
組織の一体感醸成と帰属意識を高める
クレドは組織全体で共有される「共通言語」となります。部門や職種を超えて、同じ価値観を共有することで、組織の一体感が生まれます。
日常的にクレドを参照し、実践することで、従業員同士の相互理解も深まります。「あの人もクレドに基づいて行動している」という認識が、信頼関係の構築につながるのです。
帰属意識の向上は、業績にも好影響を与えます。自分が所属する組織に誇りを持てれば、より高いパフォーマンスを発揮しようという意欲が生まれます。クレドはその誇りの源泉となるのです。
クレド作成の7つのステップ
クレド作成は、組織全体を巻き込んだプロジェクトです。トップダウンで一方的に押し付けるのではなく、従業員参加型で作り上げるプロセスそのものが、クレドを組織に根付かせる鍵となります。ここでは、実効性のあるクレドを生み出すための実践的な7つのステップを解説します。
【ステップ1】多様性のあるプロジェクトチームを結成する
クレド作成の第一歩は、社内の多様な声を反映できるプロジェクトチームの結成です。重要なのは、多様性のあるメンバー構成にすることです。
- メンバー構成: 営業、製造、管理部門など部署の垣根を越え、若手からベテランまで幅広い年齢層からメンバーを選出します。管理職だけでなく、現場の声を直接届けられる一般社員の参加が不可欠です。チームサイズは10名前後が理想的です。多すぎると議論がまとまりにくく、少なすぎると多様な視点が得られません。
- 選出方法: 意欲的な人材を募る「公募制」と、各部門のキーパーソンを確保する「推薦制」を組み合わせると効果的です。
- 環境整備: 経営層はプロジェクトの重要性を全社に伝え、メンバーが本業とのバランスを取りながら活動に集中できる環境を整えましょう。クレド作成を「本業の片手間」にしてしまうと、形骸化したクレドしか生まれづらくなります。
【ステップ2】経営層とクレドの方向性をすり合わせる
チーム結成後、まずは経営層とクレドの目的と方向性を明確に共有します。企業の将来ビジョンや経営戦略とクレドが連動するよう、基本的な方針をここで固めます。これは、プロジェクトが迷走しないための羅針盤となります。
- 目的の明確化: 経営層にインタビューやワークショップを実施し、「クレド作成を通じて、具体的にどのような組織課題を解決したいか(例:顧客満足度の向上、若手の離職率低下など)」を言語化します。
- キーワードの共有: クレドに含めるべき、企業のDNAとなるような「変えたくない価値観」と、これから目指す姿として「新たに獲得したい価値観」について議論し、キーワードを共有します。
- 権限の委譲: プロジェクトチームがどこまで裁量を持って進めて良いか、最終承認のプロセスはどうするか、といったプロジェクトの進め方についても合意形成を図ります。
【ステップ3】全従業員から価値観やエピソードを収集する
次に、全従業員を対象にヒアリングを行い、現場に根付いた価値観や大切にしている想いを集めます。
- 方法: アンケートや部門・階層ごとのインタビューを実施し、偏りのない意見収集を心がけます。オンラインツールも活用し、リモート勤務者を含め、全従業員が参加できる機会を作ることが重要です。
- 質問例: 「仕事で最も誇りに思った瞬間は?」「お客様から感謝された経験で、特に心に残っていることは?」といった具体的な質問で、生きたエピソードを集めましょう。
【ステップ4】集まった声からクレドの「骨子」を抽出する
ヒアリングで集まった多くの意見やエピソードから、共通するキーワードや価値観を丁寧に分類・整理し、クレドの「骨子」を抽出していきます。この段階で、組織が本当に大切にしている価値観の核が見えてきます。
- KJ法などの活用: 集まった意見を付箋などに書き出し、似た内容のものをグルーピングしていきます(KJ法、親和図法)。そして、各グループに共通する価値観を「挑戦」「顧客第一」「チームワーク」「誠実」といったキーワードで見出しをつけます。
- 頻出単語の分析: アンケート結果などをテキストマイニングツール(無料のものもあります)にかけるなどして、頻繁に出現するポジティブな単語をリストアップし、重視すべき価値観のヒントにします。
- エピソードの構造化: 特に象徴的な「成功エピソード」を分析し、「どのような状況で」「誰が」「どのような判断・行動をし」「どんな良い結果になったか」を分解することで、その行動の裏にある共通の価値観を探ります。
【ステップ5】心に響き、行動につながる「言葉」にする
骨子を基に、クレドを具体的な文章にしていきます。このステップでは、以下の点に注意しましょう。
- 覚えやすさ: 一つの項目は20文字程度、全体で7〜10項目程度に収めます。
- 分かりやすさ: 専門用語を避け、誰もが理解できる平易な言葉を選びます。
- 主体性: 「私たちは〜します」というような、行動を促す宣言形式が効果的です。
「現実離れした理想論」や「抽象的すぎる表現」にならないよう注意が必要です。
【ステップ6】草案を共有し、全社でブラッシュアップする
完成した草案は、すぐに決定稿とせず、必ず全社に共有してフィードバックを募ります。
- レビュー: 現場の従業員に読んでもらい、「これなら実践できるか」「違和感はないか」といった意見を集めます。
このプロセスを経ることで、クレドは「会社から与えられたもの」ではなく「自分たちが作り上げたもの」という当事者意識を育むことができます。
【ステップ7】定期的に見直し、進化させる
クレドは一度作ったら終わりではありません。時代や事業環境の変化に対応するため、定期的に見直しの機会を設けましょう。見直しの際も、従業員の意見を取り入れながら更新していくことで、クレドは形骸化することなく、常に組織の指針として機能し続ける「生きたクレド」となります。
- 見直しのタイミング: 「年に一度」の定例見直しに加え、「中期経営計画の更新時」「M&Aや大規模な組織再編時」「経営トップの交代時」など、企業にとって大きな節目となるタイミングでも見直しを検討します。
- 浸透度調査の実施: クレドの各項目が、現在どのくらい従業員に理解・実践されているかを測るサーベイを定期的に実施し、形骸化している項目がないかを確認します。
- 見直しワークショップの開催: 従業員代表者を集め、「このクレドは今の私たちに合っているか?」「もっと良い表現はないか?」「新しい事業環境において、追加すべき価値観はないか?」といったテーマで議論し、アップデートの要否を判断します。
形骸化を防ぐ!クレドを組織に浸透させる実践的な4つの方法
せっかく作成したクレドも、浸透しなければ意味がありません。多くの企業が陥る「作って満足」という罠を避け、日常業務に根付かせるための具体的な方法を紹介します。継続的な取り組みこそが、クレドを組織文化として定着させる鍵となります。
クレドカード配布と朝礼での唱和による日常化戦略
クレドを日常的に意識させる最も効果的な方法の一つが、クレドカードの配布です。名刺サイズのカードにクレドを印刷し、全従業員に配布します。
常に携帯できるサイズにすることで、いつでも確認できる環境を作ります。迷った時にカードを見返す習慣が、クレドの実践につながるのです。デザインにもこだわり、誇りを持って携帯したくなるような仕上がりにすることも大切です。
朝礼での唱和も効果的な浸透策です。毎朝全員でクレドを読み上げることで、一日の始まりに価値観を共有できます。ただし、機械的な唱和にならないよう、日替わりでクレドの実践例を共有するなど、工夫が必要です。
ラインナップなどの対話型ミーティングによる理解促進
ラインナップミーティングは、クレドについて対話形式で理解を深める取り組みです。定期的に実施することで、クレドが単なるお題目ではなく、実践的な指針として機能するようになります。
具体的には、週次や月次のミーティングで、クレドの項目を一つずつ取り上げて議論します。「このクレドを実践した具体例は?」「もっと良い実践方法はないか?」といった問いかけで、参加者全員が考える機会を作ります。
重要なのは、会社からの一方的な押し付けにしないことです。従業員自身が考え、発言し、共有することで、クレドが自分事化されていきます。小グループでのディスカッションを取り入れることで、全員が発言しやすい環境を作りましょう。
形骸化を防ぐ定期的な評価と改善の仕組みを作る
クレドの形骸化を防ぐには、定期的な評価と改善の仕組みが不可欠です。人事評価にクレドの実践度を組み込むことで、日常的な意識付けができます。
人事評価との連動では、具体的な行動指標を設定することが重要です。
例えば「顧客対応におけるクレド実践度」を5段階で評価し、具体的な行動例を評価シートに記載します。四半期ごとの1on1面談でクレドに基づいた行動を振り返り、上司と部下で認識を共有します。昇進・昇格の判断基準にもクレドの体現度を組み込むことで、組織全体への浸透が加速します。
また、クレドの実践優良事例を表彰する制度も効果的です。月間MVPや年間表彰など、クレドを体現した従業員を称えることで、モチベーション向上につながります。表彰された事例は社内報やイントラネットで共有し、良い実践例として水平展開していきます。
デジタルツールを活用した新時代のクレド浸透施策
デジタル化が進む現代では、ITツールを活用したクレド浸透策も重要です。社内SNSやチャットツールで、クレドに関する投稿を促進する仕組みを作ります。
例えば、クレドを実践した事例を写真付きで投稿し、「いいね」やコメントで反応し合う文化を作ります。デジタルネイティブ世代にとっては、このような双方向のコミュニケーションが浸透の近道となります。
eラーニングシステムを活用した教育プログラムも効果的です。クレドの背景や実践例を動画で学べるコンテンツを用意し、新入社員研修や定期研修に組み込みます。クイズ形式で理解度をチェックする機能を付けることで、楽しみながら学習できる環境を整えましょう。
成功企業から学ぶクレド導入の実践事例とポイント
クレドを効果的に活用している企業の事例から、成功のポイントを学びましょう。世界的に有名な企業から国内企業まで、それぞれの特色あるクレド活用法を紹介します。これらの事例は、自社でクレドを導入する際の貴重な参考となるはずです。
リッツカールトンのゴールドスタンダードが生む感動のホスピタリティ
リッツカールトンの「ゴールドスタンダード」は、クレドの成功事例として世界的に有名です。従業員一人ひとりが、お客様に感動を与えるサービスを提供できる仕組みが確立されています。
以下がリッツ・カールトンの掲げているクレドです。
リッツ・カールトンはお客様への心のこもったおもてなしと快適さを提供することをもっとも大切な使命とこころえています。
私たちは、お客様に心あたたまる、くつろいだ、そして洗練された雰囲気を常にお楽しみいただくために最高のパーソナル・サービスと施設を提供することをお約束します。
リッツ・カールトンでお客様が経験されるもの、それは感覚を満たすここちよさ、満ち足りた幸福感そしてお客様が言葉にされない願望やニーズをも先読みしておこたえするサービスの心です。
また、この「ゴールドスタンダード」の最終項には「従業員との約束」という形で人材育成を重視しています。
従業員もまた大切な資産として考える企業理念があることで、従業員も会社に対する信頼が生まれ、働きがいやモチベーション向上につながるのではないでしょうか。
ジョンソン・エンド・ジョンソンのタイレノール事件対応に見る危機管理の真髄
ジョンソン・エンド・ジョンソンのクレドは、1982年のタイレノール事件で真価を発揮しました。製品に毒物が混入された際、同社は迷うことなく全製品を回収しました。
顧客への責任を最優先に掲げるクレドに従い、巨額の損失を伴っても製品回収を実施したのです。結果として、この誠実な対応が評価され、ブランド価値はむしろ向上しました。
クレドが単なる理念ではなく、危機的状況での判断基準として機能した好例です。平時からクレドを徹底していたからこそ、緊急時にも迷いなく行動できたのです。
楽天の成功事例と導入のコツ
国内企業でも、クレドを効果的に活用している企業は多数あります。中でも楽天の「楽天主義」は、グローバル展開しながらも組織の一体感を保つ役割を果たしています。
楽天では、「成功のコンセプト」として以下の5項目を掲げています。
◾️常に改善、常に前進
人間には2つのタイプしかいない。
【GET THINGS DONE】様々な手段をこらして何が何でも物事を達成する人間。
【BEST EFFORT BASIS】現状に満足し、ここまでやったからと自分自身に言い訳する人間。
一人一人が物事を達成する強い意思をもつことが重要。
◾️Professionalismの徹底
楽天はプロ意識を持ったビジネス集団である。
勝つために人の100倍考え、自己管理の下に成長していこうとする姿勢が必要。
◾️仮説→実行→検証→仕組化
仕事を進める上では具体的なアクション・プランを立てることが大切。
◾️顧客満足の最大化
楽天はあくまでも「サービス会社」である。
傲慢にならず、常に誇りを持って「顧客満足を高める」ことを念頭に置く。
◾️スピード!!スピード!!スピード!!
重要なのは他社が1年かかることを1ヶ月でやり遂げるスピード。
勝負はこの2~3年で分かれる。
(引用:楽天主義|楽天グループ株式会社)
企業理念の抽象的な文言から、更に理解しやすいように5つの見出しに加え各項目で2行程度の解説も記されています。
クレドにより、よりプロフェッショナル集団として、顧客満足の最大化への実現を目指している事が伺えます。
クレドの浸透から組織変革を実現する「TUNAG」
クレドを掲げるだけでは、組織に深く浸透させ、真の行動変革へとつなげることはできません。掲示や唱和といった形式的な取り組みにとどまらず、日常業務の中で自然に活用される仕組みをつくることが大切です。そのためには、継続的な取り組みと適切なツールの活用が欠かせません。
組織改善クラウドサービス「TUNAG(ツナグ)」は、クレドの策定から浸透、効果測定、改善までを一貫してサポートし、「働きがいのある組織づくり」を実現します。
1. 経営層の想いとクレドを全従業員に届ける
TUNAGでは、社長メッセージや経営陣コラムなどを発信することができます。テキストだけでなく動画や音声も活用できるため、経営層の想いやクレドに込められた考えを、距離のある拠点や部署にまでダイレクトに伝えることが可能です。経営層の熱量をそのまま届けることで、従業員の共感を深められます。
2. クレドを日々の行動に落とし込み、称賛文化を育てる
サンクスメッセージ機能を使えば、クレドに沿った行動や貢献に対して、従業員同士が気軽に感謝や称賛を送り合える環境をつくれます。例えば、メッセージ送信時にクレドの行動指針を選べるようにしておくと、どの行動がクレドに即しているのかを意識しやすくなります。可視化されることで、従業員はクレドをより実践的に理解できるようになります。
3. 浸透度をデータで把握し、改善サイクルを回す
クレドの浸透状況は感覚ではなくデータで把握し、改善につなげることが重要です。TUNAGでは、社長メッセージの閲覧率やサンクスメッセージの利用率、クレドに関するアンケート回答率などを可視化できるダッシュボードを提供しています。
これにより、浸透度の低下や形骸化の兆候を早期に発見でき、「本当の課題はどこか」を明らかにできます。さらに、専属カスタマーサクセス担当者がデータをもとに改善策を提案し、PDCAサイクルを継続的に回すことで、クレド浸透を着実に支援します。
4. 誰もが使いやすい設計で、クレドを「自分ごと」にする
TUNAGはPCだけでなくスマートフォンアプリにも対応しているため、社用PCを持たない現場スタッフやアルバイト・パート社員も、いつでもどこでもクレドに関する情報にアクセスし、情報発信や交流が可能です。SNSのように直感的なUI/UXによって、従業員は抵抗なく利用でき、自然と日々の業務にクレドを取り入れられます。
クレドを作成・育成し組織改革を
大切なのは、クレドを「生きた文化」として育てることです。作成して終わりではなく、日々実践し、振り返り、改善を続ける。このサイクルを回すことで、クレドは組織の血肉となり、真の組織変革をもたらす力となります。
クレドは、組織と従業員をつなぐ架け橋です。適切に活用すれば、エンゲージメントの向上や離職率の改善、そして最終的には業績向上にもつながります。
あなたの組織でも、クレドという羅針盤を手に、新たな組織文化づくりに取り組んでみませんか。



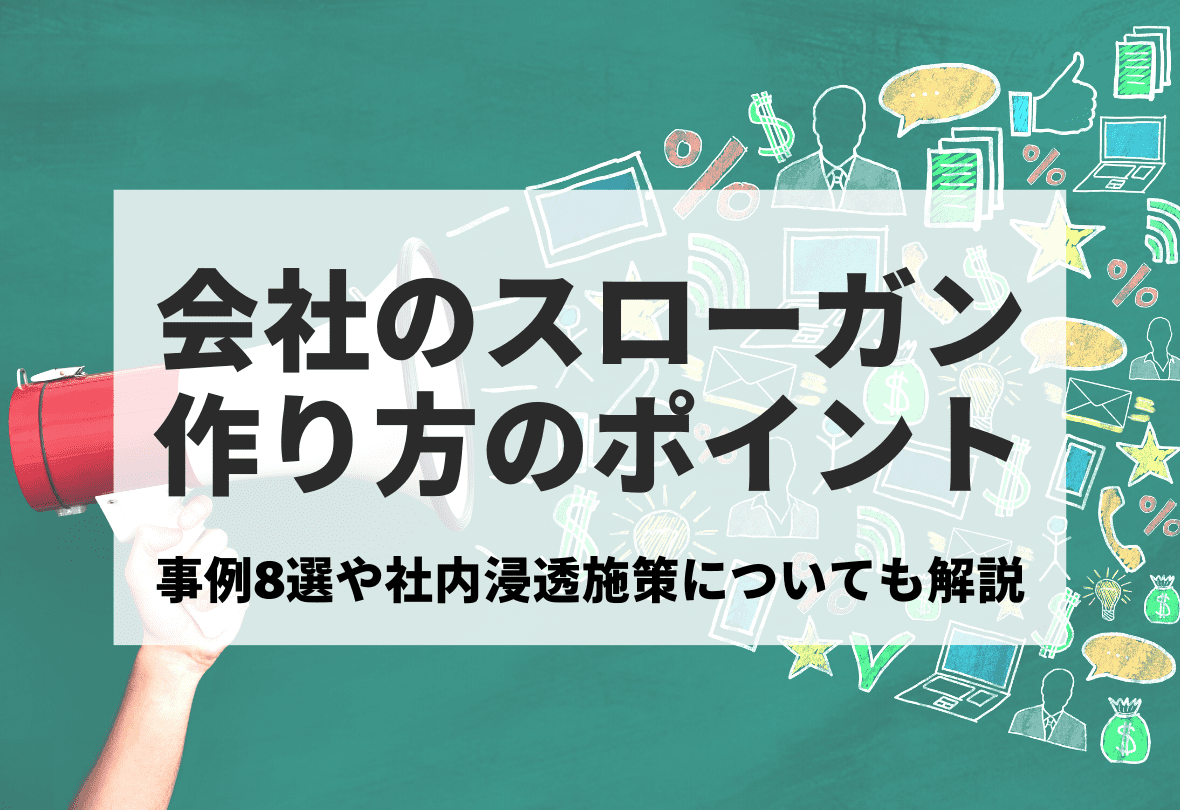
.webp&w=3840&q=75)








