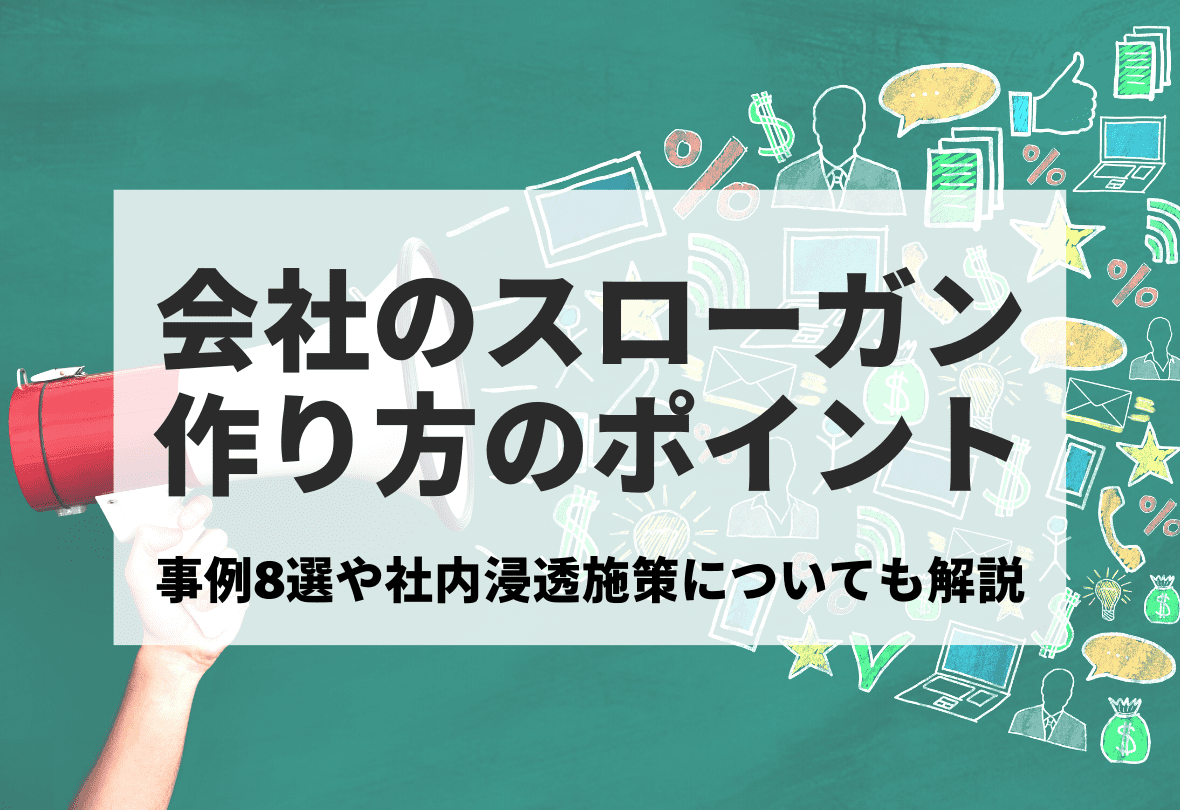パーパス経営とは?注目される背景から実践5ステップ・成功事例まで解説
自社の魅力を打ち出せず、優秀な人材の獲得に苦戦している企業も少なくないでしょう。こうした組織課題の解決策として、「パーパス経営」が注目を集めています。明確なパーパスを持つ企業は、従業員に働く意味と誇りを提供でき、エンゲージメント向上や採用力強化につながると期待されています。本記事では、パーパス経営の基本概念から実践方法、成功事例まで詳しく解説します。
パーパス経営とは
パーパス経営は、企業の持続的成長と社会への貢献を両立させる経営手法として、多くの企業が取り組みを始めています。ここでは、パーパス経営の基本的な考え方と重要性について見ていきましょう。
パーパス経営の定義と基本概念
パーパス経営とは、企業の存在意義や社会における役割を明確にし、それを経営の中心に据えて事業活動を展開する経営手法です。企業が「何のために存在するのか」「社会にどのような価値を提供するのか」を明確に定義し、その実現に向けて組織全体で取り組みます。
パーパスは単なるスローガンではありません。経営判断の基準となり、従業員の行動指針となる重要な要素です。利益追求だけでなく、社会課題の解決や持続可能な社会の実現に貢献することを目指します。
従来の経営手法との大きな違いは、短期的な利益最大化だけでなく、長期的な企業価値の向上と社会への貢献を同時に追求する点にあります。これにより、多様なステークホルダーとの信頼関係を構築できるでしょう。
パーパス経営とMVVの違い
パーパス経営と混同されやすいのが、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)です。両者には明確な違いがあります。
MVVは企業が目指す方向性や行動規範を示すものです。ミッションは企業の使命、ビジョンは目指す未来像、バリューは大切にする価値観を表します。一方、パーパスは企業の存在意義そのものを示します。
例えば、ある製薬会社のパーパスが「人々の健康と幸福に貢献する」であれば、そのミッションは「革新的な医薬品の開発」、ビジョンは「世界中の患者に希望を届ける」といった形で展開されます。パーパスを軸にMVVを設定することで、一貫性のある経営が可能になるのです。
パーパス経営の重要性
近年は業績だけでなく、多くのステークホルダーが企業に社会的価値の創出を求めるようになりました。
従業員の視点では、単なる給与や待遇だけでなく、働く意味や社会への貢献を重視する傾向が強まっています。明確なパーパスを持つ企業は、従業員に誇りと働きがいを提供できます。これが高いエンゲージメントと生産性向上につながるでしょう。
顧客の視点では、製品やサービスの品質だけでなく、企業の姿勢や社会への取り組みが購買行動に影響を与えます。パーパスに共感した顧客はロイヤルカスタマーとなり、企業と長期的な関係を築くことができます。
投資家の視点では、ESG投資の拡大により、財務指標だけでなく非財務指標も重視されるようになりました。
明確なパーパスを持ち、それを実践する企業は、投資家から高く評価されます。企業の持続的成長には、パーパス経営が不可欠な要素となっているのです。
パーパス経営が注目される社会的背景
パーパス経営への注目が高まる背景には、社会全体の価値観の変化があります。企業を取り巻く環境が大きく変化する中、パーパス経営が求められる理由を見ていきましょう。
SDGs・サステナビリティへの関心の高まり
2015年に国連サミットでSDGs(持続可能な開発目標)が採択されて以降、企業の社会的責任への意識が世界的に高まりました。気候変動、貧困、格差など、地球規模の課題解決に企業が果たす役割への期待が大きくなっています。
日本でも多くの企業がSDGsへの取り組みを公表し、サステナビリティ経営を推進しています。単なる社会貢献活動ではなく、本業を通じた社会課題の解決が求められるようになりました。
パーパス経営は、このSDGsへの取り組みと親和性が高い経営手法です。企業の存在意義を社会課題の解決に結び付けることで、事業活動そのものが持続可能な社会の実現に貢献します。これにより、企業は社会からの信頼を獲得し、持続的な成長を実現できるでしょう。
ミレニアル世代のエシカル消費と企業選び
1980年代から1990年代後半に生まれたミレニアル世代は、消費行動や企業選びにおいて独自の価値観を持っています。彼らは製品やサービスの機能だけでなく、企業の社会的姿勢を重視します。
例えばエシカル消費と呼ばれる、環境や社会に配慮した消費行動が広がっていることや、フェアトレード商品や環境配慮型製品を積極的に選ぶ消費者が増えていることが挙げられます。企業の倫理的な取り組みが、ブランド選択の重要な基準となっているのです。
就職先の選択においても、同様の傾向が見られます。ミレニアル世代は給与や待遇だけでなく、企業のパーパスや社会への貢献度を重視します。明確なパーパスを持ち、それを実践する企業は、優秀な人材を引きつけることができるでしょう。
今後、労働力の中心となるZ世代においても、この傾向はさらに強まると予測されます。パーパス経営は、次世代の従業員や顧客との関係構築に不可欠な要素となっています。
ESG投資の拡大と投資家の意識変化
ESG投資とは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の要素を考慮した投資手法です。近年、世界的にESG投資が急速に拡大しています。
従来の投資判断は財務指標が中心でしたが、現在は非財務指標も重視されます。企業の長期的な価値創造力を評価する上で、ESGへの取り組みが重要な指標となりました。
機関投資家の多くがESG投資を採用し、企業に対してESG情報の開示を求めています。そのため、企業は財務報告だけでなく、統合報告書やサステナビリティレポートを通じて、非財務指標を積極的に発信する必要があります。
VUCA時代における「ぶれない軸」としてのパーパスの必要性
VUCAとは、変動性(Volatility)、不確実性(Uncertainty)、複雑性(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)の頭文字を取った言葉です。現代のビジネス環境を表す概念として広く使われています。
テクノロジーの急速な進化、グローバル化の進展、パンデミックなど予測困難な事象により、企業を取り巻く環境は急激に変化しています。従来の成功パターンが通用しなくなり、柔軟な対応が求められるようになりました。
このような不確実性の高い時代において、パーパスは組織の羅針盤となります。例えば、新規事業への参入判断や、コスト削減と従業員の待遇維持のトレードオフに直面した際、パーパスを判断基準とすることで、場当たり的ではない一貫性のある意思決定が可能になるのです。
パーパス経営がもたらすメリット
パーパス経営の導入は、企業に多様なメリットをもたらします。組織の内側と外側、両方の視点から具体的な効果を見ていきましょう。
従業員のモチベーション向上
明確なパーパスを持つ企業では、従業員のモチベーションが大きく向上します。自分の仕事が社会にどのように貢献しているのかを理解できることで、働く意味を実感できるからです。
モチベーションの向上は、生産性の向上にも直結します。やる気のある従業員は、創意工夫を凝らし、高い成果を生み出します。また、困難な状況においても粘り強く取り組む姿勢が生まれるでしょう。
離職率の低下も重要な効果です。パーパスに共感し、その実現にやりがいを感じる従業員は、長期的に企業に貢献したいと考えます。優秀な人材の定着は、組織の継続的な成長を支える基盤となるのです。
組織の一体感強化
パーパスが浸透すると、部署や職位を越えて全員が同じ方向を向いて働けるようになります。共通の目標に向かうことで、組織全体としての力が最大化されるのです。
具体的には、部門間の壁を越えた協力関係が生まれやすくなります。それぞれの部署が個別の目標だけでなく、共通のパーパス実現に向けて連携するようになるためです。この協力体制により、複雑な課題にも組織全体で対応できるようになるでしょう。
意思決定のスピードも向上します。パーパスという明確な判断基準があることで、各レベルでの迅速な決断が可能になります。経営層から現場まで、一貫性のある判断ができるようになるのです。
ブランド価値の向上
明確なパーパスを持ち、それを実践する企業は、強力なブランドを構築できます。パーパスは企業の個性を際立たせ、他社との差別化を実現するのです。
その結果、商品やサービスの背景にある企業の思いや姿勢に共感した顧客は、熱心なファンとなります。単なる取引関係を超えた、深い絆を築けるでしょう。ブランドロイヤルティの向上により、顧客の継続的な購買行動が促進されます。
また、魅力的なパーパスを持つ企業には、価値観の合う優秀な人材が集まります。メディアからの注目度も高まり、企業の認知度向上にもつながるでしょう。
持続可能な成長の促進
パーパス経営は、企業の持続的な成長を支える基盤となります。短期的な利益追求だけでなく、長期的な視点で経営を行えるようになるからです。
パーパス経営が浸透すると、社会課題の解決を事業機会として捉えられるようになります。パーパスに基づいた新規事業の開発により、新たな市場を開拓できるでしょう。社会のニーズに応える事業は、長期的な収益源となります。
リスク管理の面でも効果があり、パーパスに基づいた倫理的な経営により、不祥事や法令違反のリスクを低減できます。イノベーションも促進され、パーパスの実現に向けて従業員が主体的に新しいアイデアを生み出すようになるでしょう。
パーパス経営を推進するデメリット
パーパス経営には多くのメリットがある一方で、推進する上での課題やリスクも存在します。これらを理解し、適切に対処することが成功への鍵となります。
パーパス・ウォッシュに陥るリスク
パーパス・ウォッシュとは、企業が掲げるパーパスと実際の行動が伴っていない状態を指します。
宣言と行動の乖離は、ステークホルダーからの信頼を大きく損ないます。特にSNSの普及により、企業の矛盾した行動は瞬時に拡散されるため、一度失った信頼を回復するには多大な時間とコストがかかるでしょう。
効果が出るまでの時間と継続的コミットメントの必要性
パーパス経営の効果は、短期間で現れるものではありません。組織文化の変革には、通常数年単位の時間がかかります。
そして、浸透するまで経営層は継続的なコミットメントをしなければなりません。短期的な業績悪化や外部環境の変化があっても、パーパスへの取り組みを継続する覚悟が求められます。
効果測定の難しさも課題です。パーパス経営の成果を定量的に測定することは容易ではなく、従業員エンゲージメントや顧客満足度など、複数の指標を長期的にモニタリングする必要があるでしょう。
リソースの分散と短期的収益へのプレッシャー
パーパス経営の推進には、人的リソースや予算の投入が必要です。パーパスの策定、浸透施策、社会貢献活動など、さまざまな取り組みにコストがかかります。するとリソースの分散により、短期的な収益性が低下する可能性があります。
特に上場企業では、四半期ごとの業績に対するプレッシャーが強く、長期的な取り組みへの理解を得にくい場合があるでしょう。
ステークホルダー間の利害調整の難しさ
パーパス経営では、多様なステークホルダーの利害を調整する必要があります。従業員、顧客、株主、取引先、地域社会など、それぞれが異なる期待を持っています。
株主利益と社会的価値のバランスは、特に難しい課題です。利益の一部を社会貢献に振り向けることに、株主が反対する可能性もあるため、両者を両立させる戦略と説明が必要でしょう。
パーパスに対する共感度は従業員によって異なり、全員が同じ熱意でコミットするわけではありません。そのため、多様な価値観を持つ従業員を尊重しつつ、組織全体としての方向性を一致させるための工夫が不可欠です。
パーパス経営を実践するための5ステップ
パーパス経営を成功させるには、計画的なアプローチが必要です。ここでは、実践するための具体的な5つのステップを解説します。
ステップ1:ステークホルダーと自社の調査・パーパスの定義
パーパスの策定は、徹底的な調査から始まります。まず、自社を取り巻くステークホルダーのニーズや期待を把握しましょう。
従業員へのヒアリングやアンケートを実施します。従業員が会社に何を期待しているのか、どのような価値観を大切にしているのかを理解することで、現場の声という貴重な情報源が得られるでしょう。顧客の声も重要です。既存顧客への調査だけでなく、潜在顧客のニーズも探ります。
調査結果を統合し、自社ならではのパーパスを定義します。経営層だけでなく、多様な部門のメンバーを巻き込んだワークショップを開催し、議論を深めることが効果的でしょう。
ステップ2:パーパスの共有
策定したパーパスを組織全体に共有することが、次のステップです。ただ発表するだけでなく、その背景や意義を丁寧に伝える必要があります。
そのためには経営層からのメッセージ発信が重要です。CEOやトップマネジメントが、パーパスへの強いコミットメントを示します。なぜこのパーパスを掲げるのか、どのような未来を目指すのかを、自分の言葉で語ることが大切です。
また、プレスリリース、企業サイト、SNSなどを通じて、顧客や社会に向けてパーパスを公表しましょう。
ステップ3:行動指針の策定
パーパスを日々の行動に落とし込むため、具体的な行動指針を策定します。抽象的なパーパスを、実践可能なレベルまで具体化するのです。
そのためにもまずは、部門ごとの行動指針を作成しましょう。営業部門、開発部門、管理部門など、それぞれの役割に応じた行動指針を定めます。各部門がパーパスの実現にどう貢献するのかが明確になるでしょう。
具体的な取り組み事例を示すことも効果的です。パーパスに基づいた好事例を社内で共有し、表彰する仕組みをつくります。成功体験の共有により、パーパスの実践が広がっていくでしょう。行動指針は一度作って終わりではなく、定期的に見直し、環境の変化に応じて更新していく必要があります。
ステップ4:パーパスの浸透
パーパスを組織文化として定着させるには、継続的な浸透活動が必要です。時間をかけて、じっくりと組織に根付かせていきます。
定期的な研修やワークショップによる普及活動はもちろん、朝礼やチームミーティングなど、日常的なコミュニケーションの中でもパーパスに関連する話題を取り上げることで、日々の業務とパーパスのつながりを意識する習慣が生まれます。
社内イベントの活用も効果的です。周年行事や表彰式など、従業員が集まる機会にパーパスを再確認し、楽しみながら理解を深められる工夫が大切です。
ステップ5:継続的な評価と改善
上記で紹介したステップを実行する中で、定期的にパーパスの浸透度を測定しましょう。
従業員サーベイを実施し、パーパスへの理解度や共感度、実践度を確認します。数値データとして可視化することで、改善すべきポイントが明確になるでしょう。
改善策を実施したら、PDCAサイクルを回します。課題が見つかったら、原因を分析し、対策を立てて実行するのです。その結果を再度評価し、次の改善につなげます。
環境の変化に応じて、パーパスそのものの見直しも検討しましょう。
パーパス経営に必要な要素は?
パーパス経営を成功させるには、いくつかの重要な要素があります。これらを適切に組み込むことで、実効性の高いパーパス経営が実現できるでしょう。
インパクト指標の設定と活用
パーパスの実現度を測るには、適切な指標が必要です。インパクト指標とは、パーパスに基づいた活動が社会や組織にもたらす影響を測定する指標です。
従業員エンゲージメントスコア、顧客満足度、環境負荷削減量、社会貢献活動の受益者数など、パーパスに関連する多様な指標を定めます。
指標は定量的に測定可能であることが重要です。曖昧な評価ではなく、数値として把握できる指標を選ぶことで、進捗を客観的に評価できるでしょう。
パーパスとビジネスモデルの統合
パーパスを掲げるだけでなく、ビジネスモデルそのものに統合することが重要です。本業を通じてパーパスを実現する仕組みをつくります。
製品やサービスの開発において、パーパスを起点に考えましょう。顧客のニーズを満たすだけでなく、社会課題の解決に貢献できる製品を開発することで、パーパスが競争優位性の源泉となるのです。
イノベーションの推進にもパーパスを活用しましょう。パーパスの実現に向けた新規事業の創出を奨励し、従業員からのアイデアを募集して実現を支援する仕組みをつくります。組織構造や業務プロセスもパーパスに合わせて見直し、意思決定のプロセスにパーパスの視点を組み込むことで、パーパスが組織のあらゆる活動に浸透するでしょう。
グリーンウォッシュを防ぐための透明性確保
グリーンウォッシュとは、環境配慮を装いながら実態が伴わない行為を指します。パーパス経営においても、同様のリスクがあるため、透明性の確保が不可欠です。
パーパスに関連する活動の内容、成果、課題を正直に公開します。良い情報だけでなく、改善が必要な点も率直に共有することが信頼につながるのです。
このとき、ネガティブな情報も隠さずに公開する姿勢が大切です。問題が発生したときこそ、迅速かつ誠実に対応します。
隠蔽やごまかしは、長期的に大きな信頼損失を招くでしょう。ステークホルダーとの対話を重視し、一方的な情報発信だけでなく、意見や批判を受け止める姿勢を持つことで、対話を通じてより良い取り組みへと改善していくことが、真のパーパス経営につながるのです。
パーパス経営の成功事例5選
実際にパーパス経営を実践し、成果を上げている企業の事例を紹介します。これらの事例から、具体的な取り組みのヒントを得られるでしょう。
ソニーグループ|全世界11万人へのパーパス浸透
ソニーグループはパーパスとして、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」を掲げています。
当初は、「パーパスを作ろう」という流れではなく、「MVVをもう一度見直そう」という議論からスタートしました。その過程で、海外ではパーパスという考え方が広がっていることを知り、ソニーグループでもパーパスを策定することに決めました。
代表自ら「ミッションを見直したい」「社員の皆さんの意見が欲しい」と全世界の社員に呼びかけ、「ソニーグループらしさとはなんだろう」と意見を求めたり、対話を重ね、さらに代表とマネジメント層が議論してパーパスを形にしていきました。
パーパスの浸透については、専門の事務局を立ち上げ、以下のような取り組みを実施していきました。
- キービジュアルを作成し、ポスターにして全世界に配布
- 代表のパーパスへの思いをつづった署名入りレターを配信
- ビジュアルで理解を促進するためのビデオを作成
- 代表から各事業のマネジメント層に「事業戦略を語るときは、必ずパーパスと関連付けて話してください」と依頼
- 社内のWebサイトで、世界中の社員に「パーパスをあなた自身に置き換えるとどうなるのか」「日々の業務の中でどう実践しているのか」をインタビューした記事を公開
パーパスを作ったメリットとして、コロナ禍であってもパーパスを軸として社員が団結し、困難やリスクのある中でも業務に取り組めたことを挙げています。
参照:
ソニーグループポータル | Sony's Purpose & Values
多事業・多国籍の11万人の社員の心を同じベクトルへ。 ソニーグループのPurpose経営 | CCL. | 日経BPコンサルティング
味の素|対話とサイクルで実現するパーパス経営
味の素株式会社は、まず自社のパーパス(存在意義)を「食と健康の課題解決」と定義しました。このパーパスに基づき、グループビジョンとして「アミノ酸の働きで食習慣や高齢化に伴う食と健康の課題を解決し、人々のウェルネスを共創します」を策定しています。
経営陣と従業員は対話を重ね、パーパスとビジョンを社内に浸透させるための一連のサイクルで取り組みを実施しています。
- 代表と部長の対話をもとに組織・個人目標を設定し、個人目標発表会を実施
- ベストプラクティスを社内SNSで共有し、年に1回表彰
- エンゲージメントサーベイで効果測定
参考:味の素・西井社長は「パーパス経営」実践のために何を行ったか | Special Report [PR](1/3)|DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー
ネスレ日本|本業を通じた社会課題解決の実践
日本ではコーヒーなどで知られるネスレでは、存在意義(パーパス)として「ネスレは、食の持つ力で、現在そしてこれからの世代のすべての人々の生活の質を高めていきます。」を掲げています。
このパーパスを実現するため、ネスレ日本では以下の三つの領域で本業を通じた社会課題の解決に取り組んでいます。
個人と家族のために
ネスレの製品やサービスを通じて生活の質を高めることを目指すものです。
- コーヒーマシンをオフィスでも活用する「ネスカフェ アンバサダー プログラム」では、オフィス内のコミュニケーションの活性化に貢献
- ネスレは、ヘルシーな食事の選択肢を増やすため、植物由来の代替肉ブランド「Garden Gourmet(ガーデン・グルメ)」や、植物性ミルク「ネスレ ミルクメイド ヴィーガン」など、持続可能な食システムに貢献する製品のラインナップを拡充しています。
コミュニティのために
活力のあるコミュニティづくりへの取り組みです。
- 沖縄で初となる大規模な国産コーヒー豆の栽培を目指す産学官連携の「沖縄コーヒープロジェクト」
- バス車両を全面的に改装した「ネコのバス」を活用して保護猫の譲渡会を実施し、保護猫の啓発と譲渡促進に貢献
地球のために
未来の地球のために、資源と環境を守ることを目指しています。
- 「包装材料を2025年までに100%リサイクル可能、あるいはリユース可能にする」というコミットメント
- 日本では、「ネスカフェ」や「キットカット」など主力製品のパッケージの紙化
参照:
ネスレ日本株式会社 企業情報 (会社案内掲載情報)| ネスレ日本
ネスレのPurposeと実践 | Ideal Leaders株式会社
富士通|評価制度Connectでパーパスを起点とした成長評価
富士通は、存在意義として「わたしたちのパーパスは、イノベーションによって社会に信頼をもたらし世界をより持続可能にしていくことです。」と掲げています。
パーパスを実現していくために、新しい評価制度「Connect」を2021年から導入しました。
この評価制度では、パーパスを起点にマネジメント層がビジョンを描き、そのビジョンに向けてどれだけのインパクトを与えたかが評価されます。また、個人のパーパスを起点にどれだけ成長したかなども評価の対象となります。
参照:
共感・信頼をベースとしたマネジメントへ、富士通が実践する新たな評価制度とは - フジトラニュース : 富士通
三菱UFJフィナンシャル・グループ|新時代をリードする金融機関へ
日本の3大メガバンクグループの一角である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下、三菱UFJFG)は、2021年4月に新しいパーパスを設定しました。
■世界が進むチカラになる
ここには、新しい時代において社会をリードする存在になる、という思いが込められています。その新しい時代には、輝かしい未来だけでなく、少子高齢化、人口減少、世界経済の低成長、コロナ禍といった困難な現実も含まれています。
また、金融業界はデジタル技術の進展が目覚ましく、異業種の金融事業への参入も相次いでいます。三菱UFJFGは国内で最大規模の金融機関グループですが、自ら、世界の変化を進める存在であることで、存在意義を生み出していこうという姿勢がうかがえます。
参照:「MUFG Way」の制定および新中期経営計画について
パーパス経営の推進を支援するTUNAG
パーパス経営の成功には、パーパスを組織全体に浸透させる仕組みが不可欠です。TUNAGは、パーパス経営の推進を効果的に支援します。
その理由や機能について、詳しく紹介します。
TUNAGがパーパス経営の推進に選ばれる理由
TUNAGは、多くの企業でパーパス経営の推進ツールとして選ばれています。その理由は以下の通りです。
パーパスの浸透に必要な機能が一つのプラットフォームに集約されている
情報発信、双方向コミュニケーション、エンゲージメント測定など、多様な機能を統合的に活用できるため、複数のツールを使い分ける必要がなく、運用負荷を軽減できるでしょう。
使いやすいインターフェース
ITリテラシーにかかわらず、全従業員が簡単に利用できます。スマートフォンからもアクセスできるため、現場の従業員にも情報が届きやすくなっています。
従業員のエンゲージメントや情報の閲覧状況を可視化できる
定量的なデータに基づいて施策の効果を測定し、改善につなげられます。
専任のコンサルタントによる支援も受けられる
パーパス浸透の経験豊富な専門家が、企業の状況に応じた最適な活用方法を提案します。導入から運用まで、伴走型のサポートを受けられるでしょう。
パーパス浸透に効果的なTUNAGの機能
TUNAGには、パーパスの浸透を促進する多様な機能が備わっています。企業の状況に合わせて、効果的に活用できるでしょう。
パーパス浸透に特に効果的な機能として、以下があります。
- 社長メッセージ:経営層の思いとパーパスへのコミットメントを直接伝達
- Web日報:パーパスに関連する取り組みや成果をリアルタイムに共有
- サンクスメッセージ:パーパスに基づいた行動を相互に認め合う
- 社内ポイント:経営理念や行動指針を体現した行動を可視化・評価
- MVP表彰:パーパスを体現した従業員を表彰し、推奨行動を明確化
- お客様の声共有:顧客や社会への価値提供を実感し、パーパスの意義を再確認
これらの機能を組み合わせることで、パーパスの理解から実践、そして称賛まで、一貫した浸透サイクルを構築できます。
経営層からのメッセージ発信、現場での実践事例の共有、従業員同士の相互承認が有機的につながり、組織全体にパーパスが根付いていくでしょう。
カンロ株式会社の事例|社内報と動画発信でパーパス理解度を向上
「金のミルク」「ピュレグミ」などの菓子や食品を製造・販売するカンロ株式会社は、TUNAGを活用してパーパスの浸透に成功しました。
同社は2022年に創業110周年を迎え、パーパスとして「"Sweeten the Future" 心がひとつぶ、大きくなる。」を策定しました。TUNAG上でパーパスについて動画で発信し、パーパスに対する思いを従業員から募集する取り組みを実施しています。
社内報の記事も定期的に発信し、記事の既読数も増加しました。社内アンケートでは、パーパス理解に関する数値がどんどん上がっていき、発信を始めた当初から順調にパーパスの理解が進んでいることが確認できました。
TUNAGの活用により、パーパスが確実に組織に浸透した同社の事例は、パーパス浸透の好例と言えるでしょう。
カンロ、社内報アプリとワークショップでパーパス浸透。本社と各拠点の情報格差を解消 | TUNAG(ツナグ)
パーパス経営は掲げるだけではなく、浸透させることが重要
パーパス経営において最も大切なのは、パーパスを掲げることではなく、組織全体に浸透させることです。表面的なスローガンに終わらせてはなりません。
そのためには、継続的な対話と学びの機会が必要です。研修やワークショップ、日常的なコミュニケーションを通じて、パーパスについて語り合う文化を醸成しましょう。
パーパスの浸透には長期的な視点を持ち、粘り強く取り組み続けることが重要です。明確なパーパスを持ち、それを実践する組織は、従業員のエンゲージメント向上、顧客からの信頼獲得、持続的な成長を実現できるのです。
パーパス経営への取り組みを始めるなら、今がそのタイミングです。自社の存在意義を見つめ直し、ステークホルダーとともに未来を創造していきましょう。



.webp&w=3840&q=75)