ミッションステートメントとは?作り方や事例、浸透方法を徹底解説
組織の規模が拡大し、事業が多角化する中で、従業員の方向性がバラバラになり、組織としての一体感が失われていると感じる経営者や人事担当者もいるでしょう。こうした課題を解決する鍵となるのが「ミッションステートメント」です。本記事では、ミッションステートメントの基本的な定義から作り方、そして形骸化させないための社内浸透の手法まで、体系的に解説します。
企業におけるミッションステートメントとは
企業経営において、組織の存在意義を明文化することは非常に重要です。ミッションステートメントは、まさにその役割を果たす重要な経営ツールといえるでしょう。ここでは、その基本的な定義から、関連する概念との違いまでを詳しく解説していきます。
ミッションステートメントの定義と役割
ミッションステートメントとは、企業や組織が「なぜ存在するのか」「何のために事業を行うのか」を表すミッションを明文化した宣言文です。単なる標語ではなく、組織が大切にする軸や、進むべき方向性を示すものです。
ミッションステートメントには、以下のような重要な役割があります。
- 組織の判断基準:日々の意思決定の指針となる
- 社内の求心力:従業員の行動原理を統一する
- 対外的な信頼:ステークホルダーへの約束となる
- 差別化要因:競合他社との違いを明確にする
- 採用ブランディング:共感する人材を引き寄せる
ミッション・ビジョン・バリューの違い
企業理念を構成する要素として、ミッション・ビジョン・バリューという3つの概念があります。これらは密接に関連していますが、それぞれ異なる役割を持っているのです。
以下、ミッション・ビジョン・バリューの違いを表にまとめました。
要素 | 定義 | 特徴 | 時間軸 | 具体例 |
|---|---|---|---|---|
ミッション | 存在意義 | なぜこの組織が必要なのか、社会にどんな価値を提供するのかを表現 | 普遍的・不変 | 「すべての人に健康な生活を届ける」 |
ビジョン | 目指す未来像 | 3年後、5年後、10年後にどのような姿になっていたいかを具体的に提示 | 期限付き・更新可能 | 「2030年までに日本の教育格差をゼロにする」 |
バリュー | 行動指針 | ミッション実現とビジョン到達のために持つべき価値観や行動規範 | 継続的・実践的 | 「顧客第一」「チャレンジ精神」「誠実さ」 |
これらの関係性を整理すると、ミッションという土台の上にビジョンという目標があり、バリューという行動規範がそれらをつなぐ構造になっています。相互に補完し合いながら、組織の方向性を示す重要な要素となっているのです。
クレドとの違いと使い分け
ミッションステートメントとクレドは密接に関連しながらも、異なる役割を持っています。ミッションステートメントが企業の存在意義や社会的使命を示すのに対し、クレドはその実現のための具体的な行動指針を明文化したものです。ラテン語で「信条」を意味するクレドは、従業員が日々の業務で判断に迷った際の具体的な基準となります。
ミッションステートメントを起点として、それをより具体的な行動レベルに落とし込んだものがクレドといえるでしょう。
多くの企業では、ミッションステートメントで大きな方向性を示し、クレドで日常的な行動規範を定めています。この二つを連携させることで、理念と実践の間のギャップを埋め、組織全体で一貫した行動を実現できるようになります。
ミッションステートメントを策定する目的
ミッションステートメントの策定には、組織運営において極めて重要な目的があります。単なる飾り文句ではなく、実践的な経営ツールとして機能させるために、その目的を正しく理解することが大切です。ここでは、ミッションステートメントが果たす目的について詳しく見ていきましょう。
組織の方向性が統一される
明確なミッションステートメントがあることで、従業員一人ひとりが「何のために働いているのか」を理解できるようになります。日々の業務に追われる中でも、自分の仕事が組織の大きな目的につながっていることを実感できるのです。
例えば、トヨタ自動車では「わたしたちは、幸せを量産する」というミッションを掲げています。工場で働く従業員も、開発部門のエンジニアも、このミッションのもとで自分の役割を認識し、誇りを持って働けるようになっているのです。
経営判断を支える明確な基準になる
経営者は日々、さまざまな判断を迫られます。新規事業への参入、投資の可否、提携先の選定など、重要な意思決定の連続です。そんな時、ミッションステートメントは判断の拠り所となります。
「この決定は、我々のミッションに合致しているか」という問いかけが、正しい判断への道しるべとなるでしょう。短期的な利益を追求するあまり、組織の存在意義から外れてしまうことを防ぐ役割も果たします。ミッションステートメントは経営の羅針盤として機能するでしょう。
ステークホルダーの信頼構築につながる
企業を取り巻くステークホルダーは多岐にわたります。顧客、株主、取引先、地域社会など、それぞれが企業に対して異なる期待を持っています。
明確なミッションステートメントを公開することで、企業が何を大切にし、どのような価値を提供しようとしているのかが伝わります。その結果、ステークホルダーは企業の行動を予測しやすくなり、信頼関係が構築されていくのです。
例えば、環境保護を重視するミッションを掲げる企業に対しては、環境意識の高い消費者が支持を寄せます。また、投資家も企業の長期的な方向性を理解した上で投資判断ができるようになるでしょう。
従業員エンゲージメントが向上する
自分の仕事が社会にどのような価値をもたらしているのかを理解できると、従業員のモチベーションは大きく向上します。単なる作業ではなく、意味のある仕事として捉えられるようになるのです。
エンゲージメント向上がもたらす効果は多岐にわたります。
- 生産性向上:自発的に効率化を図るようになる
- 創造性発揮:新しいアイデアを積極的に提案する
- 顧客満足度の向上:熱意を持った対応が顧客に伝わる
- チームワークの強化:互いに協力し合う風土が生まれる
特に若い世代を中心に、給与や待遇だけでなく、仕事の意味や社会貢献を重視する傾向が強まっています。明確なミッションステートメントは、こうした世代の心を掴む重要な要素となっています。。
優秀人材の獲得につながる
求職者は、単に仕事内容や待遇だけでなく、その企業で働く意味を求めています。明確なミッションステートメントがあれば、求職者は入社後の自分の姿をイメージしやすくなるでしょう。
実際に、ミッションを前面に打ち出した採用活動を行っている企業では、応募者の質が向上したという報告が多数あります。価値観を共有できる人材が集まることで、採用後のミスマッチも減少しています。
採用力強化による効果は次の通りです。
- 応募者の質向上:ミッションに共感する優秀な人材が集まる
- 採用コスト削減:ミスマッチによる早期離職が減る
- 組織文化の強化:同じ価値観を持つ人材が増える
- 採用ブランディング:企業の魅力が明確に伝わる
- 内定承諾率向上:入社の動機づけが強くなる
このように、ミッションステートメントは人材戦略においても重要な役割を果たしているのです。
ミッションステートメントの作り方
ミッションステートメントの重要性を理解したら、次は実際に作成する段階です。形だけのものではなく、組織に根付く実効性のあるミッションステートメントを作るには、体系的なアプローチが必要です。ここでは、実践的な作り方をステップごとに整理していきます。
まずは目的を整理する
最初のステップは、「なぜ今ミッションステートメントを作る(or 見直す)のか」をはっきりさせることです。
- 組織の一体感を高めたいのか
- 事業の方向性を整理したいのか
- 採用・育成・評価など人事施策と結びつけたいのか
このような目的を明確にすることで、ミッションの言葉選びや、関係者の巻き込み方も変わってきます。目的を曖昧にしたまま進めると、「誰のためのミッションなのか」がぼやけてしまうため、最初にしっかり整理しておくことが重要です。
専門チームを編成してプロジェクト化する
ミッションステートメントの作成は、経営層だけで決めるものではありません。組織全体で共有し、実践していくものだからこそ、作成段階から多様な視点を取り入れることが重要です。
まず、専門チームを編成しましょう。経営層、中間管理職、現場の従業員など、様々な立場の人を巻き込むことが大切です。部門横断的なメンバー構成にすることで、組織全体の意見を反映できるようになります。
この専門チームが中心となり、全社的な議論を促進していきます。定期的なミーティングを設定し、進捗を管理しながら進めていくことが成功の鍵となるでしょう。
ワークショップなどでアイデアを発散する
専門チームだけでなく、より多くの従業員を巻き込むためには、ワークショップの実施が効果的です。参加型のワークショップを通じて、組織全体でミッションについて考える機会を作りましょう。
ワークショップでは、階層や部門の壁を越えた対話が生まれます。普段は接点のない従業員同士が意見交換することで、新たな気づきが生まれることも多いでしょう。
進行のポイントとして、ファシリテーターは中立的な立場で進行し、すべての参加者が発言しやすい雰囲気を作ることが重要になります。付箋やホワイトボードを活用し、視覚的にアイデアを整理していくと効果的です。
複数回のワークショップを実施し、段階的に内容を深めていくことをお勧めします。初回は自由な発想を重視し、2回目以降で具体的な文言を検討していくという進め方が良いでしょう。
9つの要素を使って内容を検討する
ミッションステートメントに含めるべき内容を体系的に検討するため、9つの要素を活用する方法があります。これらの要素を網羅的に検討することで、抜け漏れのない充実した内容になります。
検討すべき9つの要素は以下の通りです。
- 顧客:誰のために存在するのか
- 製品・サービス:何を提供するのか
- 結果・市場:どこで、どのような価値を生み出すのか
- 技術:どのような強みを活かすのか
- 成長性:どのように発展していくのか
- 哲学:何を大切にするのか
- 自己概念:自社をどう定義するのか
- 社会的責任:社会にどう貢献するのか
- 従業員:働く人にどんな価値を提供するのか
これらの要素について、チームで議論を重ねていきます。すべての要素を盛り込む必要はありませんが、検討することで組織の本質が見えてくるはずです。
例えば、「顧客」について考える際は、直接的な顧客だけでなく、その先にいる最終消費者まで想像を広げてみましょう。「技術」については、現在の強みだけでなく、将来獲得したい能力も含めて考えることが大切です。
ステークホルダーと議論して推敲する
ワークショップで集まったアイデアを基に、いよいよ文章化の段階に入ります。この段階では、言葉の一つひとつを慎重に選ぶ必要があります。
まず、シンプルで分かりやすい表現を心がけましょう。専門用語や難解な言葉は避け、誰もが理解できる平易な言葉を選びます。長すぎる文章も避け、覚えやすく、口にしやすい長さにまとめることが大切です。
言葉選びのポイントは次の通りです。
- 具体性と抽象性のバランス:普遍的イメージしやすい内容にする
- 能動的な表現:受け身ではなく主体的な姿勢を示す
- ポジティブな印象:前向きで希望を感じる言葉を使う
- 独自性:他社と差別化できる表現にする
- 記憶に残る:リズムや響きも考慮する
作成した文案は、様々なステークホルダーの視点でチェックします。従業員はもちろん、顧客、取引先、地域社会など、それぞれの立場から見て違和感がないか確認しましょう。
また、英訳した際の印象も確認することをお勧めします。グローバル展開を視野に入れている企業では、海外でも通用する表現であることが重要です。
作っただけでは意味がない!ミッションステートメントを浸透させる方法
せっかく作成したミッションステートメントも、額縁に入れて飾っているだけでは意味がありません。従業員一人ひとりの行動に反映され、日々の業務で実践されて初めて価値を発揮します。ここでは、効果的な浸透施策と実践方法について、具体的に解説していきます。
継続的な社内コミュニケーション設計をする
ミッションステートメントの浸透には、継続的なコミュニケーションが欠かせません。一度伝えただけでは、日々の業務に追われて忘れ去られてしまうでしょう。
まず、経営トップ自らがミッションについて語る機会を定期的に設けることが重要です。全社会議、部門会議、朝礼など、あらゆる場面でミッションに触れ、その重要性を伝え続けます。
社内報やイントラネットも有効な浸透ツールです。ミッションに基づいた行動事例を紹介したり、従業員インタビューを掲載したりすることで、身近な存在として感じてもらえるようになります。
また、新入社員研修では必ずミッションステートメントについて時間を割いて説明します。入社時点でしっかりと理解してもらうことで、その後の行動指針として定着しやすくなるでしょう。
近年活用が進んでいる社内コミュニケーションツールも、有効な手段の一つです。こうしたツールを通じて、経営層からのメッセージやミッションに関連する情報を発信するだけでなく、従業員同士が「サンクスカード」機能などでミッションを体現した行動を気軽に称賛し合うことで、理念を組織文化として根付かせることができます。
評価制度・人事制度と紐づける
ミッションステートメントを真に浸透させるには、評価制度や人事制度に組み込むことが不可欠です。ミッションに沿った行動が評価され、報われる仕組みを作ることで、従業員の行動変容を促すことができます。
そのためにも、人事評価項目にミッション関連の指標を追加しましょう。例えば、「ミッションを体現した行動」という評価軸を設け、具体的な行動事例を基に評価します。数値目標だけでなく、価値観に基づいた行動も評価対象とすることが重要です。
昇進・昇格の判断基準にも、ミッションへの貢献度を含めます。リーダーシップポジションに就く人材は、特にミッションの体現者であることが求められるでしょう。
表彰制度も効果的な施策の一つです。ミッションアワードのような表彰制度を設け、優れた実践事例を全社で共有します。金銭的な報酬だけでなく、認知と称賛という精神的な報酬も重要な動機づけとなります。
日常的に意識しやすい仕組みを創る
ミッションステートメントを日常業務に落とし込むには、抽象的な理念を具体的な行動に変換する必要があります。各部門、各職種において、ミッションがどのような行動として現れるべきかを明確にしましょう。
部門ごとにミッション実践計画を策定します。営業部門であれば「顧客との信頼関係構築」、製造部門であれば「品質へのこだわり」など、ミッションを部門の特性に合わせて解釈し、具体的な行動目標を設定します。
会議の進め方も見直します。議題の検討時には「この決定はミッションに合致しているか」を必ず確認するようにします。判断に迷った時は、ミッションに立ち返って考える習慣を作るのです。
このような小さな行動の積み重ねが、組織文化を変えていきます。一人ひとりが日々の業務でミッションを意識することで、組織全体が同じ方向を向いて進めるようになるでしょう。
効果測定を実施し、取り組みを改善する
ミッションステートメントの浸透度や効果を定期的に測定し、改善していくことが重要です。PDCAサイクルを回すことで、より実効性の高い取り組みへと進化させていきます。
測定のタイミングは、年に1〜2回程度が適切でしょう。あまり頻繁に測定すると負担になりますし、間隔が空きすぎると改善のサイクルが遅くなってしまいます。
その後は測定結果を基に、課題を特定し改善策を立案します。浸透が不十分な部門があれば、追加の研修を実施したり、成功事例の共有を強化したりします。
情報共有ツールを活用する
ミッションを浸透させ続けるには、「発信 → 共感 → 行動 → 振り返り」のサイクルを回し続ける必要があります。これを人力だけで行うのは負担が大きく、属人的にもなりがちです。
そこで有効なのが、情報共有を促進する社内SNSや社内報といったツールの活用です。
例えば、組織改善クラウドサービス「TUNAG(ツナグ)」は、サンクスカード・社内報などを通じて、ミッション・ビジョン・バリューといった企業理念の浸透と実践を支援します。社内コミュニケーションの活性化、エンゲージメントの可視化、組織文化の醸成など、ミッションステートメントを含む組織全体の指針を生きたものにするためのプラットフォームとして活用できます。
- トップメッセージの発信
- ミッションに紐づく行動の可視化・称賛
- 部門・拠点を超えたコミュニケーション
- 成功事例やナレッジの共有
このような取り組みを一つの場に集約することで、「作っただけで終わらないミッション」の実現を後押しします。
ミッションステートメント浸透に成功した企業事例
ここからは、ミッションステートメントを軸に組織づくりを行い、浸透・実践に成功している企業の事例を紹介します。
株式会社サイバーエージェント
株式会社サイバーエージェントでは、「21世紀を代表する会社を創る」というビジョンに紐づく形で以下のようなミッションステートメントを掲げています。
インターネットという成長産業から軸足はぶらさない。
ただし連動する分野にはどんどん参入していく。
オールウェイズFRESH!
能力の高さより一緒に働きたい人を集める。
採用には全力をつくす。
若手の台頭を喜ぶ組織で、年功序列は禁止。
スケールデメリットは徹底排除。
迷ったら率直に言う。
有能な社員が長期にわたって働き続けられる環境を実現。
法令順守を徹底したモラルの高い会社に。
ライブドア事件を忘れるな。
挑戦した敗者にはセカンドチャンスを。
クリエイティブで勝負する。
「チーム・サイバーエージェント」の意識を忘れない。
世界に通用するインターネットサービスを開発し、グローバル企業になる。
同社は主力事業の成長と並行して関連分野へ積極的に参入し続けてきました。採用ではスキルだけでなく「一緒に働きたいか」という価値観を重視し、若手に大きな裁量を任せる文化を徹底することで、社員全体が同じ方向を見てチャレンジできる土台をつくっています。
その結果として、企業全体の着実な増収に加え、多くの社員が「働きがい」と「成長機会」を実感するエンゲージメントの高い組織が構築され、クリエイティブ人材が新規事業やサービス開発の最前線で活躍する環境が整っています。ミッションステートメントを起点に、事業戦略・採用・組織文化が一体となって成果につながっている事例といえるでしょう。
株式会社銀の葡萄
「麺's room 神虎」「鶏soba 座銀」などのラーメン店を展開する株式会社銀の葡萄では、ミッションとして「世界一かっこいいラーメン屋」を掲げています。同社は、ラーメン店と居酒屋業態を合わせて国内に20店舗以上、海外に10店舗以上を運営しています。
このミッションと6つのバリューを浸透させるため、組織改善プラットフォームTUNAGを活用した様々な施策を実施しています。
「ワクワクを共有します」というコンテンツでは、新しい事業や取り組みについて
「大手食品メーカーさんの監修でラーメン作りました」
「給食で当社のラーメンが食べられるようになります!」
といった内容を共有し、店舗で働く従業員も会社の動きを知ることで、誇りを持って働けるようになっています。
さらに、サンクスカードを6つのバリュー項目と紐づけて運用した結果、アルバイトから正社員や準社員になりたいという方が5名ほど採用でき、採用単価も正社員・アルバイトともに半分ほどに抑えられたという成果を上げています。
このように、「ミッション・バリュー → TUNAGでの行動可視化 → 文化醸成」という流れを仕組み化することで、現場レベルでミッションが“生きている状態”を作り出している事例です。
参照:採用単価が半分に。「鶏 soba 座銀」がアルバイトからの正社員登用を仕組み化するまで | TUNAG(ツナグ)
渡辺パイプ株式会社
全国に約600カ所の拠点を持ち、約6,000名の従業員が働く渡辺パイプ株式会社では、企業としての方針を毎年発信しているものの、関連するイベントや施策が不十分で理念が組織全体に浸透していないという課題がありました。
そこでTUNAGを活用し、「トップスピリッツ」という社長からの連載メッセージを発信。社長の考え方やマインドをブログ形式で従業員に伝えたところ、従業員からはスタンプによる多くの反応に加えて、「社長の人となりが伝わりやすくなった」という声が上がっています。
他にもTUNAG上で拠点同士のつながりを生むコラムコンテンツやレクリエーション企画を実施したところ、離職率も改善傾向にあるという効果を実感しています。
このように、トップメッセージの継続発信、拠点間コミュニケーション、表彰・コンテンツなどをTUNAG上で連動させることで、「理念 → コミュニケーション → 評価・称賛」という好循環をつくり、ミッション・スピリットが浸透する土台を整えています。
参照:600拠点の従業員6,000名がつながる。コミュニケーション課題を解決した渡辺パイプの挑戦 | TUNAG(ツナグ)
個人のミッションステートメントと組織力の関係性
ここまで企業のミッションステートメントについて見てきましたが、近年は「個人としてのミッションステートメント」を持つ重要性も高まっています。
なぜ個人のミッションステートメントが重要なのか
個人のミッションステートメントは、「自分は何のために働くのか」 「どんな価値を周囲や社会に提供したいのか」
を明文化した、自分自身の存在意義や人生の指針です。
生成AIなどのテクノロジーが急速に普及するなかで、あらかじめ用意された正解どおりに動くのではなく、自分で考え、問いを立て、周囲を巻き込みながら行動する主体性がこれまで以上に求められるようになっています。こうした環境では、個人が自分なりの軸を持っておくことが重要です。
個人のミッションをはっきり意識させると、企業の方向性とのギャップを再認識し、離職のリスクを高めてしまうのではと不安に感じる方もいるかもしれません。 ですが、実際にはその逆のケースも多くあります。
自分のミッションと会社のミッションがどこで重なっているかを理解している人ほど、「自分の仕事は何のためにやっているのか」を実感しやすくなり、仕事への納得感や前向きさが高まりやすくなります。その結果、組織の中心を支えるコア人材が熱力高く働き、活躍しやすい環境づくりにつながっていきます。
個人のミッションステートメントの作り方
個人のミッションステートメントは、必ずしも難しい言葉である必要はありません。短くても、自分がしっくりくる表現であることが大切です。
作成のステップ例は次の通りです。
STEP1:これまで嬉しかった経験・誇りに思う出来事を書き出す
ミッションステートメントの根幹は、個々人の性格や経験によって培ってきた価値観です。特に嬉しかった経験などを書き出すことで、人生の軸を見出しやすくなります。
- どんなときに「やってよかった」と感じたか
- どんな場面で「自分らしさ」を感じたか
STEP2:その出来事に共通する「価値観」を言葉にする
それぞれの経験を並べてきた時に、共通する価値観でグルーピングしてみましょう。特定の事象から抽象的な価値観に変換する難しい作業ですが、このステップを通して、新しい自分の軸を見つけることができるかもしれません。
- 「人の成長を支えること」
- 「困っている人の力になること」
- 「新しい仕組みをつくって世の中を便利にすること」
STEP3:誰に・どんな価値を届けたいのかを文章にする
価値観が言葉になってきたら、次は その価値観を、誰のために、どんな場面で活かしたいかを具体的にイメージします。
- 「◯◯な人に対して、△△な価値を届ける」
- 「□□な社会を実現するために、▽▽をしていく」
STEP4:短く、覚えやすい一文にまとめる
「どんな価値を、誰に届けたいのか」がまとまったら、迷ったときにすぐ思い出せるように、毎日口にできるくらい想いのこもった一文にします。
- 「挑戦する人の背中を押し、成長を支え続ける」
- 「身近な人の“困った”を仕組みで解決する
個人のミッションステートメントも、一度決めて終わりではなく、企業のミッションとの関係を意識しながら見直していくことで、「自分の成長」と「会社への貢献」を結びつけて考えられるようになります。
ミッションステートメントの定着が企業成長の原動力に
ミッションステートメントは、企業にとって「なぜ存在するのか」を示す根幹です。
組織の方向性をそろえる経営判断の基準になるだけではなく、ステークホルダーからの信頼構築や採用力の強化といった多くの効果をもたらす重要な経営ツールです。
一方で、ミッションステートメントは「作っただけ」では機能しません。
策定したミッションステートメントを、従業員が日常的に触れる仕組みに落とし込み、組織全体に浸透させていくところまでを、徹底することが重要です。
ミッションステートメントの策定と浸透は、一朝一夕にはいきませんが、組織にとって大きなリターンのある投資です。ぜひ、自社のミッションステートメントを策定して、持続的な企業成長を実現する原動力として活かしてください。



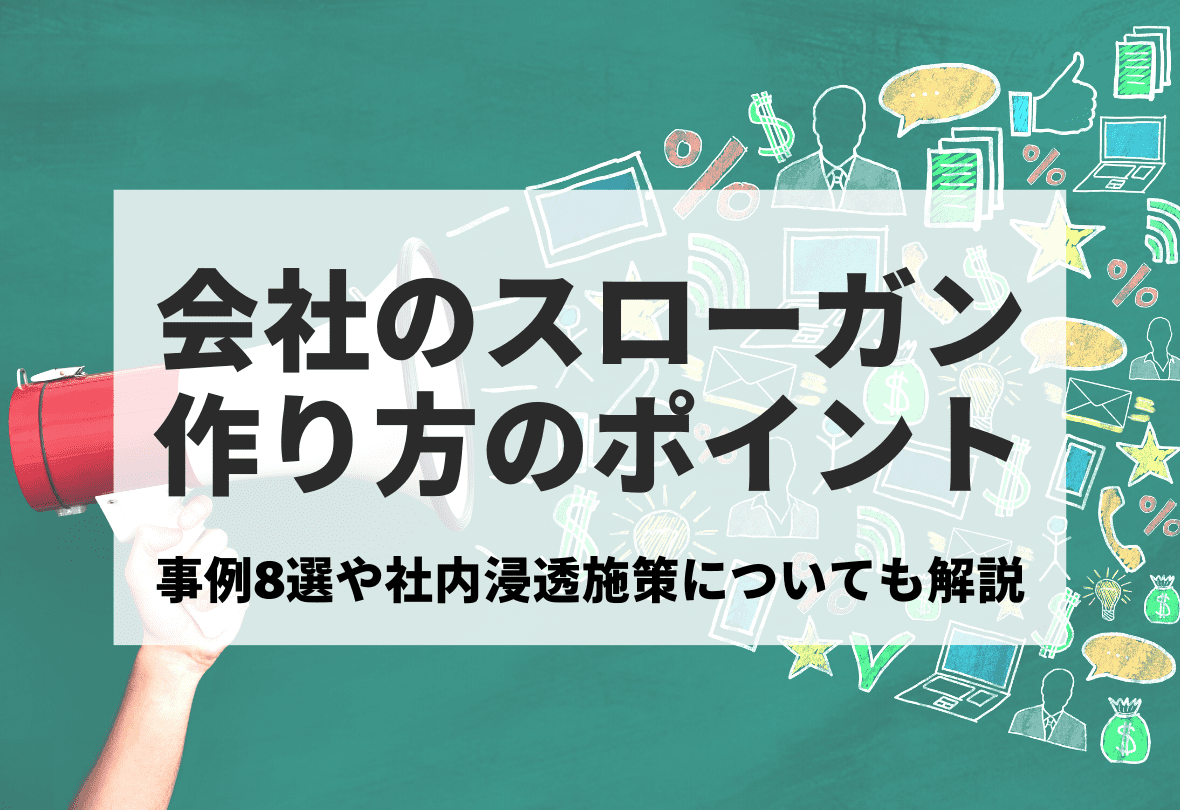
.webp&w=3840&q=75)








