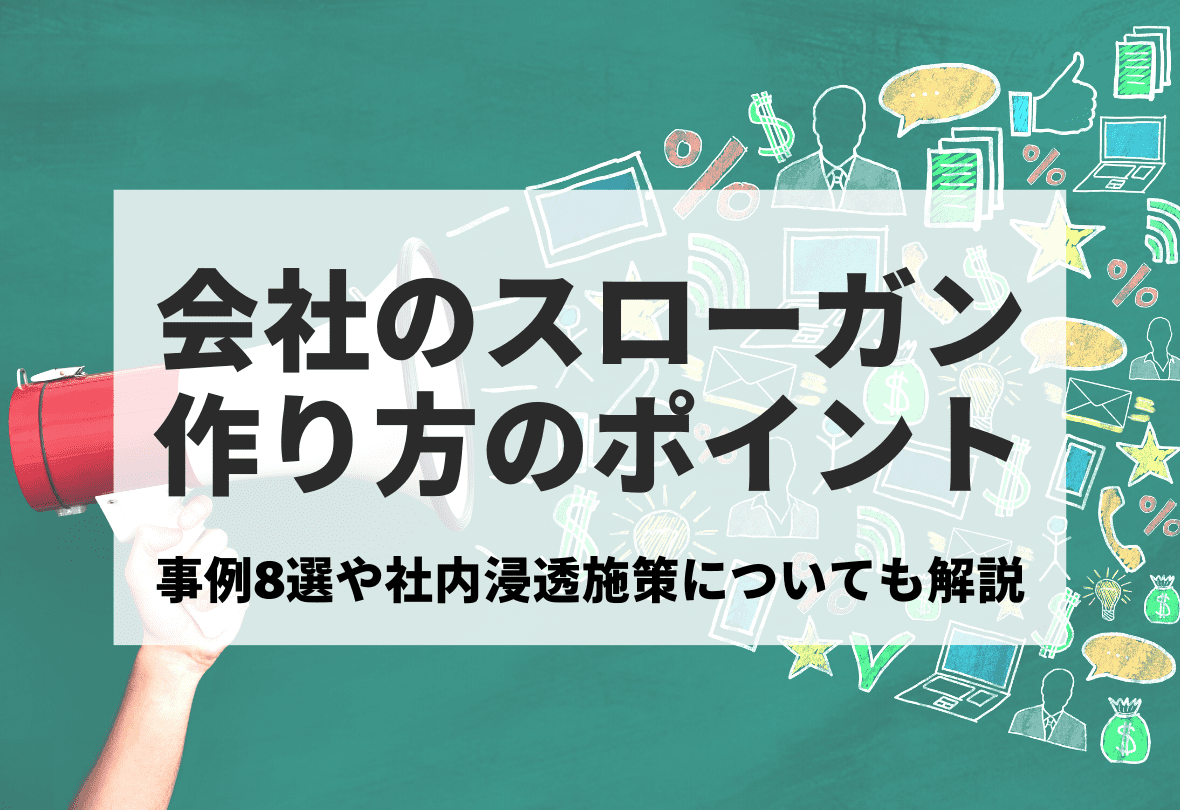インナーブランディング事例10選!離職率改善の施策と効果的な実施手順を紹介
インナーブランディングとは、従業員に対して自社のブランド価値や企業理念を浸透させる社内向けの取り組みです。適切に実施することで、従業員エンゲージメントの向上や離職率改善に大きな効果をもたらします。本記事では、インナーブランディングの基本概念から具体的な施策、実施手順まで詳しく解説します。人事・経営企画担当者が明日から実践できる具体的なアドバイスもまとめます。
インナーブランディングとは何か
人材の流動化が進む現代において、多様な人材が定着し、いきいきと活躍できる環境をつくることは、経営における重要な課題です。従業員が自社への誇りを持ち、主体的に行動できる組織をつくるために、多くの企業がインナーブランディングに注目しているのです。
ここではインナーブランディングの基本概念と、アウターブランディングとの違いについて、実務的な視点から解説します。
インナーブランディングの基本概念
インナーブランディングとは、企業理念や価値観を従業員に浸透させ、共感と行動変容を促す戦略的な人事施策を指します。インターナルブランディングやインナーマーケティングとも呼ばれ、従業員を対象とした社内向けブランディング活動として位置付けられているのです。
具体的な取り組みには社内研修や教育活動、社内報による情報発信、人事評価制度の見直しなどが含まれます。最終的な目的は従業員が企業のブランド価値やビジョンを深く理解し、日々の業務でそれを体現することにあります。
従業員一人一人がブランドアンバサダーとして機能することで、組織全体のパフォーマンス向上と持続的成長につながります。
アウターブランディングとの違い
ブランディングには、社外の消費者に向けた「アウターブランディング」と、社内の従業員に向けた「インナーブランディング」があります。アウターブランディングが顧客への訴求を重視するのに対し、インナーブランディングは従業員の意識変革と行動変容に焦点を当てます。
多くの企業では従来、消費者向けのアウターブランディングに重点を置いてきました。
しかし、企業が掲げるビジョンやブランドイメージが社内で十分に浸透していない状態では、説得力のあるメッセージを外部に発信することは困難です。働く従業員一人一人が組織の目指す方向性と自身の役割を理解してこそ、真に価値のあるブランド体験を顧客に提供できます。
つまり、インナーブランディングで組織の基盤を固めることが、効果的なアウターブランディングの重要な土台となります。
インナーブランディング施策がもたらす効果
インナーブランディング施策の実施により、組織にどのような変化がもたらされるのでしょうか。
従業員エンゲージメントの向上、離職率の改善、顧客満足度の向上という三つの重要な効果について詳しく解説します。これらの効果は相互に関連し合い、組織全体の競争力強化につながっていきます。
従業員エンゲージメント向上
インナーブランディング施策により企業のビジョンやミッション、価値観を従業員が深く理解することで、自身の役割と企業目標との関連性が明確になります。この理解が仕事の意義を見出す基盤となり、エンゲージメントを大きく向上させるのです。
社内研修やワークショップを通じて企業理念を共有することで、従業員は自分の業務が企業全体の成功にどう貢献するかを実感できるようになります。この気づきが、日々の業務への取り組み姿勢を根本から変えていくのです。
企業の一員であることへの誇りが生まれることで、従業員は自身の業務に更なる価値を見出し、企業成長を共に目指すパートナーとしての意識を高めるでしょう。
インナーブランディングによる理念浸透がエンゲージメントを高め、結果として生産性向上や離職率低下といった具体的な経営効果をもたらすのです。
離職率改善と人材定着率向上
インナーブランディング施策によって企業理念に共感した従業員は、所属組織でのキャリアを長期的視点で捉えるようになります。その結果、キャリアプランや企業のミッションを理解することで離職率が低下し、人材の定着率が向上します。
人材定着率の向上は、採用コストや研修費用の削減に直結します。業務ノウハウの蓄積、顧客との継続的関係構築、組織の安定性向上といった実質的なメリットが企業経営に大きな影響を与えます。
ブランドメッセージ統一による顧客満足度の向上
全従業員が統一されたブランドメッセージを理解し発信できるようになると、顧客に対して一貫性のあるコミュニケーションが実現します。営業、カスタマーサポート、開発部門など、どの部署の従業員と接しても同じ品質のブランド体験を提供できるのです。
この一貫性はブランドの信頼性を高め、顧客との長期的関係構築を支えます。特にサービス業では従業員の対応がそのままブランド体験となるため、従業員のブランド理解度が直接的に顧客満足度に影響します。
効果的なインナーブランディング施策
効果的なインナーブランディング施策の実行には、単なる周知活動を超えた戦略的アプローチが不可欠です。ここでは実効性の高い三つの施策を詳しく解説します。
社内イベント・ワークショップによる理念浸透策
企業ビジョンや価値観を共有する最も効果的な方法は、従業員同士が直接対話し議論する機会を設けることです。全社的なミーティングやチームビルディング活動を定期的に開催することで、企業の方向性や目標への理解が自然と深まります。
全社員参加型の理念浸透セッション、部署横断的な交流促進、成功事例やストーリーの共有、参加型ワークショップ形式での議論、経営陣との直接対話機会を設けることが重要です。企業理念を題材としたグループワークでは、各部署がどのように理念を実践できるかを具体的に検討します。
実際の業務事例や体験型ワークショップを交えれば、従業員は自分の役割をビジョン・ミッション・バリューと結び付けられるようになるでしょう。
社内報・社内SNSを活用した継続的コミュニケーション施策
インナーブランディングの成功は継続性にかかっています。社内報や社内SNSなどのコミュニケーションツールを効果的に活用することで、従業員間の情報共有と意見交換が促進され、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)が日常的に強調される環境を構築できます。
具体的には社内ニュースレターでの理念紹介、社内SNSでの成功事例共有、従業員インタビューの掲載、部署間の取り組み紹介、経営陣からのメッセージ配信などが挙げられます。
単なる業務連絡ではなく、企業理念に基づいた行動事例や従業員の活躍を積極的に紹介することが重要です。
動画・映像コンテンツによるビジュアル訴求施策
文字だけでは伝わりにくい企業の雰囲気や価値観を視覚的に表現する手法として、動画や映像コンテンツの活用が高い効果を示しています。感情に訴えかける映像は従業員の共感を得やすく、深い印象を残すことができるのです。
企業の歴史や成功事例をストーリー仕立てで社内共有すれば、従業員がブランドに対する共感を深められます。
リモートワークが普及する現在、動画コンテンツは場所を選ばずに視聴できる利点があります。短時間で要点を伝えられる動画は忙しい業務の合間でも視聴しやすく、全社員への一律な情報共有手段として高い効果を発揮するでしょう。
インナーブランディング施策の実施手順
インナーブランディングの成功は体系的なアプローチによって実現されます。現状把握から実行、継続的改善まで、段階的かつ戦略的に進めることで確実な成果を得ることができます。ここでは効果的な実施手順を三つのステップで詳しく解説します。
現状分析と課題設定
インナーブランディングの出発点は、企業の現状を客観的に把握することです。従業員のエンゲージメントやブランド認識のレベルを正確に評価しなければ、効果的な戦略は立てられません。
現状分析では従業員へのアンケート調査を実施し、理念の理解度や浸透度を数値化します。個別インタビューを通じて定性的な情報も収集し、組織内コミュニケーションの評価を行います。既存制度や施策の効果測定、離職率や定着率の詳細分析により、課題の全体像を把握しましょう。
この分析結果を基に、インナーブランディングの具体的な目的や目標を設定します。目標は具体的かつ測定可能であることが重要で、現状と理想のギャップを明確にし、どの領域に重点的に取り組むべきかを決定するのです。
優先順位を決定して実行
現状分析と課題設定が完了したら、具体的な施策の企画と実行に移ります。全ての施策を同時に実施するのではなく、効果的な順序で段階的に取り組むことが成功の鍵となります。
優先順位を決定する際は、効果の大きさと期待値、実施にかかるコストと時間、組織の受け入れ準備度を総合的に考慮します。他施策との相乗効果や短期・中期・長期の視点も重要な判断基準となるでしょう。
実行段階では各施策の責任者を明確にし、実施スケジュールと予算を決定します。
進捗状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて軌道修正を行う体制を整えることも重要です。従業員の主体的な参加を促す仕組みをつくることで、より効果的な結果を得られるでしょう。
効果測定とPDCAサイクルによる継続的改善
インナーブランディングの成功には継続的な効果測定と改善が欠かせません。施策の実施後は必ず効果を測定し、PDCAサイクルを回して継続的に改善していく姿勢が重要です。
効果測定では従業員エンゲージメント調査の実施、理念浸透度の測定、離職率・定着率の追跡、顧客満足度の変化、業績指標への影響分析を行います。
定期的なアンケート調査により従業員の意識変化を数値で把握し、施策への参加率や反応も重要な指標として記録し、数値だけでは測れない現場の声も反映しましょう。
評価結果を基に、どの施策が効果を上げているか、どの部分に改善が必要かを分析します。
効果の高い施策は継続・拡大し、効果の低い施策は見直しや改善を行います。
インナーブランディングの成功事例
実際の企業でインナーブランディングがどのように実践され、成果を上げているかを具体的な事例で見ていきましょう。ここでは五つの代表的な成功事例を紹介します。
スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社
従業員が主体的に行動し、顧客に対して満足度の高いサービスを提供していることで知られる「スターバックスコーヒー」のインナーブランディング施策に「行動指針の明確化」が挙げられます。
ミッションと具体的な行動指針を掲げ、従業員一人一人に浸透させることで、ブランドとして一貫性のあるサービスの提供を実現しているのです。
スターバックスコーヒーのミッション宣言は「当社の原則を一貫して守りつつ事業を拡大し、世界の最高級コーヒーの加工から小売まで一貫して扱う一流コーヒー専門会社としてのスターバックスを築いていく」ことです。
さらに、以下の6つの行動指針を明確に定めています。
- お互いに尊敬と威厳をもって接し、働きやすい環境をつくる
- 事業運営上での不可欠な要素として多様性を受け入れる
- コーヒーの調達や焙煎、新鮮なコーヒーの販売において、常に最高級のレベルを目指す
- 顧客が心から満足するサービスを常に提供する
- 地域社会や環境保護に積極的に貢献する
- 将来の繁栄には利益性が不可欠であることを認識する
そうしたインナーブランディングの結果、スターバックスは飲食業態ながら勤続年数が長いことで知られています。インナーブランディングにより従業員の定着率向上に成功した事例です。
株式会社オリエンタルランド(東京ディズニーリゾート)
オリエンタルランドは、顧客に夢と魔法を提供することをミッションとしており、この企業文化が社内に深く浸透しています。従業員一人一人がこの精神を体現し、来場者へ特別な体験を提供することを目指しています。
同社のインナーブランディング戦略の核となるのは、社員向けのブランド教育プログラムです。このプログラムは、単にブランド理念を伝えるだけでなく、社員がブランド価値を理解し、その価値を行動やサービスを通じて顧客に伝えるための仕組みを確立しています。
具体的な取り組みとして、定期的に開催されるブランド教育ワークショップでは、異なる部門の従業員が集まり、企業理念やブランドストーリーを深く学びます。
また、実際のゲストとのコミュニケーションを通して、オリエンタルランドならではの「おもてなし」を実践することで、客観的な評価の向上だけでなく、従業員自身の自己実現にも貢献しています。これらの活動は、社員のモチベーションを高め、長期的な企業の成長と顧客満足度の向上につながっています。
企業風土とES活動 | 従業員 | 社会 | サステナビリティ | 株式会社オリエンタルランド
日本航空株式会社
日本航空(JAL)は、2010年の経営破綻から、わずか2年で営業利益約2,000億円と驚くべきスピードで業績回復を果たしました。その背景には、3万5千人のJALグループスタッフに新生JALの価値を認識してもらうインナーブランディング施策がありました。
2010年の春には「ブランド構築プロジェクト」が立ち上がり、新たなロゴやコミュニケーションスローガンの策定などを行うことが決まりました。特に重視していたのが、JALが提供する価値であるブランドを社内に浸透していくことでした。
JALの特徴的な取り組みは、各部署の代表者でプロジェクトチームを発足し、JALブランドを伝えるためのツールとセミナーを一緒につくっていくプロセスを踏んだことです。客室・運航・旅客・営業・整備・貨物など、さまざまな職種のスタッフがいる中で、それぞれの部署が主体的に参加できるプランを実施しました。
2011年9月からセミナーを開始し、1年で約8,000人のスタッフが参加しています。参加者からは「困ったら原点である『伝統・革新・日本のこころ』に立ち返ればいい」という発言が聞かれるようになり、JALの軸となる考え方の浸透に成功しています。
参考:【日本航空株式会社様】3万5千人のスタッフにJALブランドを浸透させ、 再生へと、加速する。(経営理念浸透コンサルティング 導入事例)
株式会社リクルート
リクルートでは、「Airレジ」や「Airペイ」といったAirサービスにおいて、インターナルブランディングを推進しています。
2013年11月に「Airレジ」がリリースされて以来、Air事業では多くのサービスが誕生しました。事業の成功を最大化するため、これらのサービスは、事業運営の特性や対象ユーザーに応じて異なる事業ユニットに分かれて運営されています。
しかし、サービスと人員の増加に伴い、組織の分断が生じ、情報共有が滞り、事業のコンテクスト(歴史や背景など)に対する理解にばらつきが見られるようになりました。この課題に対処するため、どのサービスやユニットに属していても、Air事業に携わる全員が共通の知識や考え方を理解できるよう、インターナルブランディングが実施されました。
ブランドミッションを「お店を取り巻く煩わしさを減らし、自分らしいお店づくりができるようにする」、ブランドビジョンを「商うを、自由に。」と掲げ、継続的にインターナルブランディングに取り組んでいます。
目線を揃えることで、ブランドが浸透する。リクルートで社内へのブランド浸透に取り組んだ話
Google合同会社
Googleが実施しているインナーブランディング戦略の根底には、自由で革新的な思考を求める社風があります。代表的な施策として挙げられるのが「20%ルール」でしょう。
従業員の創造性とイノベーションを最大限引き出すために、社員の勤務時間のうち20%を「普段の業務とは異なる」業務に割いてよいという内容です。
結果として、革新的なアイデアが生まれやすくなり、GmailやGoogleマップ、Googleニュースといった数々の成果を生み出しました。
TUNAGを活用したインナーブランディングの成功事例
組織改善クラウドサービス「TUNAG(ツナグ)」は、多くの企業のインナーブランディングを支援しています。ここでは実際にTUNAGを活用して成果を上げている5つの企業事例を紹介します。
株式会社マティクスホールディングス
「地域の暮らしと移動を支える会社になる」を長期ビジョンに掲げる株式会社マティクスホールディングスでは、20以上の拠点に散らばる従業員への企業理念浸透が課題でした。
従来のFAXや会議による情報伝達では拠点間で温度差が生じていました。TUNAGを導入し、松本社長自らが週1回「トップメッセージ」を発信することで、中期経営計画や長期ビジョンを従業員一人一人に直接伝えています。
また、各拠点の「販売報告」や「今週のグッドニュース」による情報共有、紙のサンクスカードのデジタル化により称賛文化を醸成しました。拠点を超えた一体感の創出に成功している事例です。
中期経営計画を“社長の言葉”で全員に届ける。「少人数×多拠点」でもつながり、頑張りが見える社内インフラができた | TUNAG(ツナグ)
株式会社イーブレイン
ICT教育に強い学習塾運営を展開する株式会社イーブレインでは、33校舎という離れた拠点で理念が統一されていない課題を抱えていました。
1教室1人体制のため、「上手くいっているからこのやり方で良いだろう」という考えが広がり、理念に即していない運営が浸透していました。TUNAGを導入し、「Will Can Must」に沿った日報運用で評価制度と連携、129個のスタンプを活用した「○○からの速報」で認め合う文化を醸成しました。
「研修実践ニュース」による知識共有や、サンクスカードの送付数を「MOSTサンクス賞」として表彰することで、「教育と教室運営がつながっている」と社員が理解できる組織風土を構築しています。
離れている33校舎をつなぐ。理念浸透とコミュニケーションで教育の本質を伝える方法とは。 | TUNAG(ツナグ)
株式会社アワーズ
テーマパーク『アドベンチャーワールド』を運営する株式会社アワーズは、「こころでときを創るSmileカンパニー」という企業理念のもと、女性社員の離職率改善に取り組みました。
2018年に企業内保育園「キラボシ」を開設し、女性管理職・リーダーが6年で8.5倍に増加しました。TUNAGを社内ポータルサイトとして統合運用し、『キラボシ』の活動をインナーブランディングとして発信しています。「Smile+」コンテンツや「心の花束」というサンクスカードでは企業理念を実現する「3つのこころ」から選択するルールを設け、理念浸透を図っています。
産休・育休中の社員との交流会も開催し、多様な人材が活躍できる環境づくりを推進しています。
女性管理職・リーダーが6年で8.5倍に。企業内保育園とアドベンチャーワールドが推進する理念経営とは | TUNAG(ツナグ)
渡辺パイプ株式会社
全国約600拠点に約6,000人の従業員を持つ渡辺パイプ株式会社では、縦割り組織による横の情報連携不足と企業理念の浸透不足が課題でした。
毎年200名超が入社する一方で退職者も多く、横のつながりの希薄さに不安を感じる社員もいました。TUNAGを導入し、「SCリレーコラム」で各拠点の営業所長がリレー形式で拠点紹介を行い、従業員の顔が見えるコミュニケーションを創出しました。
「トップスピリッツ」による社長の考え発信、全社参加型の「TUNAG宝くじ」などにより、TUNAGの顔写真登録率90%超を実現しています。「TUNAG見ました」という声が拠点で聞かれるようになり、実際に離職率も改善傾向にある「コミュニケーション発火装置」として機能しているとのことです。
600拠点の従業員6,000名がつながる。コミュニケーション課題を解決した渡辺パイプの挑戦 | TUNAG(ツナグ)
カンロ株式会社
菓子・食品を製造販売するカンロ株式会社では、工場従業員の情報アクセス格差と、部門間の相互理解不足が課題でした。2022年に創業110周年を迎え、パーパス「"Sweeten the Future" 心がひとつぶ、大きくなる。」を策定しました。
TUNAGを導入し、パーパスの動画発信や従業員からの想いを募集、ワークショップ実施によりパーパス浸透を図りました。社長発信の「哲也の部屋」や「サステナビリティ座談会」で経営層との距離を縮め、品質保証部の「キューさんぽ」など各部署が専門知識をカジュアルに共有しています。
工場のシフト表共有などペーパーレス化も推進し、社内アンケートでパーパス理解度が順調に向上した結果、「これTUNAGで発信しよう」という文化が定着しています。
カンロ、社内報アプリとワークショップでパーパス浸透。本社と各拠点の情報格差を解消 | TUNAG(ツナグ)
インナーブランディングで社員の意識改革を
現代のビジネス環境において、人材の確保と定着は企業の持続的成長に不可欠な要素となっています。優秀な人材を引きつけ、長期的に活躍してもらうためには、単に給与や福利厚生を充実させるだけでは不十分です。従業員が自社に誇りを持ち、仕事にやりがいを感じられる環境づくりが重要なのです。
インナーブランディングは時間のかかる取り組みですが、その効果は組織の根幹に関わる重要なものです。従業員のエンゲージメント向上、離職率の改善、そして最終的には企業の競争力強化につながる投資として、ぜひ積極的に取り組んでみてください。



.webp&w=3840&q=75)