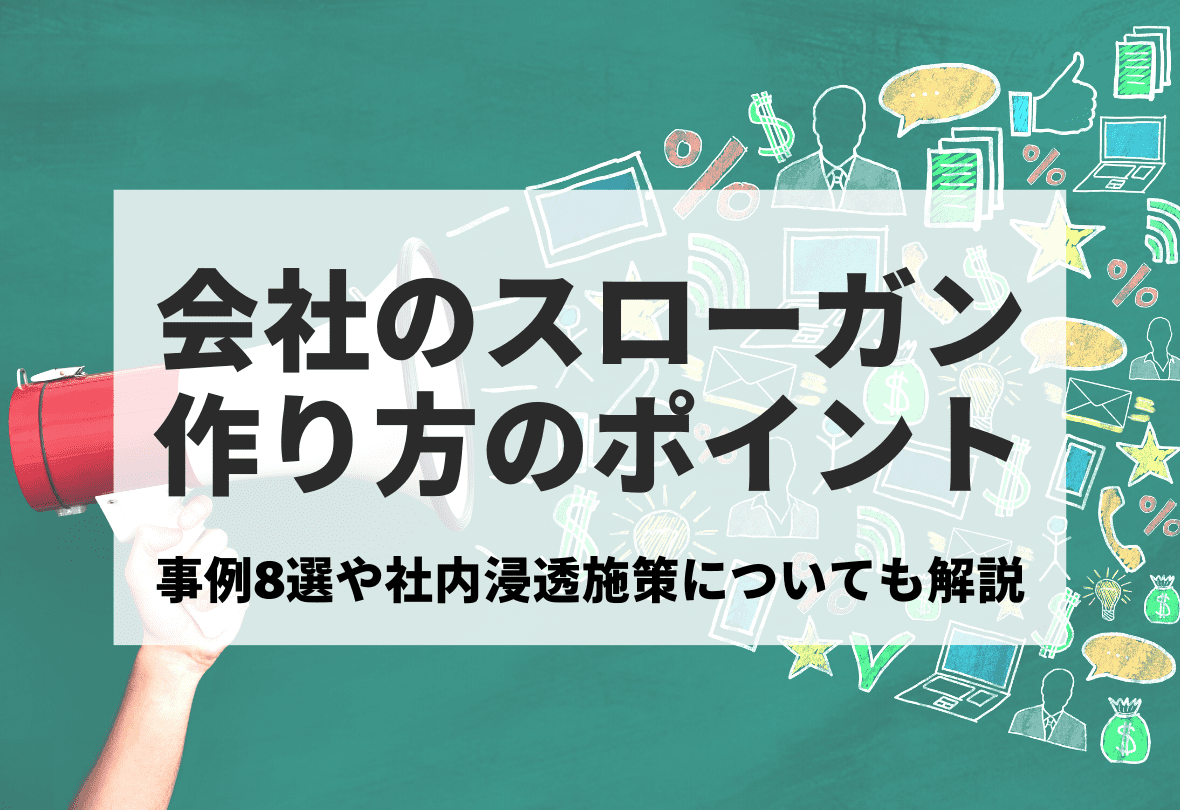MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)とは?策定意義や作り方をわかりやすく解説
企業には社会にどのような価値を提供するのかという存在意義があります。それを表現する考え方の一つにMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)です。本記事では、MVVの意味や違い、策定方法まで、わかりやすく解説します。
MVVとは?意味と重要性を理解する
MVVは現代の組織運営において欠かせない要素となっていますが、その真の意味と役割を正しく理解していなければ、効果を発揮しません。
まずは、MVVの基本構成と企業における役割を詳しく見ていきましょう。
MVVの基本構成と企業における役割
MVVとは、Mission(ミッション)、Vision(ビジョン)、Value(バリュー)の頭文字を取った略語です。これら3つの要素は、企業や組織の存在意義、目指す方向性、行動の基準を明文化したもので、経営戦略、人事評価、組織文化づくりの土台となります。
MVVが企業において果たす主な役割は以下の通りです。
- 組織の方向性統一:全従業員が同じ方向を向いて行動するための指針
- 意思決定の基準:迷った時の判断軸として機能
- 採用・評価の基準:企業文化に合う人材の見極めと評価
- ブランディング:対外的な企業イメージの統一
- 従業員エンゲージメント向上:働く意味や価値の明確化
それぞれの用語の意味を解説します。
ミッション
ミッションは、企業の存在意義や社会的使命を表します。「なぜその企業が存在するのか」「社会にどのような価値を提供するのか」を明確にします。
ミッションの特徴
- 企業の根本的な存在意義を示す
- 社会における役割や貢献を表現
- 時代が変わっても変わらない普遍的な内容
- 従業員の働く意味や誇りの源泉
例えば、「人々の生活を豊かにする技術革新を通じて、持続可能な社会の実現に貢献する」といった形で表現されます。
ビジョン
ビジョンは、企業が目指す将来像や理想の状態を描いたものです。「将来どのような企業になりたいか」「どのような世界を実現したいか」を具体的に示します。
ビジョンの特徴
- 将来の理想的な姿を描く
- 具体性があり、イメージしやすい
- 挑戦的で魅力的な内容
- 中長期的な目標設定の基準
ビジョンは「2030年までに業界No.1のサービス品質を実現し、お客様から最も信頼される企業になる」といった形で表現されます。
バリュー
バリューは、企業が大切にする価値観や行動指針を示します。「どのような考え方で行動するか」「何を重視して判断するか」の基準となります。
バリューの特徴
- 日常業務での判断基準
- 企業文化の根幹を形成
- 従業員の行動を導く指針
- 複数の項目で構成されることが多い
例えば、「お客様第一」「チームワーク」「革新への挑戦」「誠実さ」といった形で表現されます。
ミッション・ビジョン・バリューの違いと相互関係
MVVの3つの要素は、それぞれ異なる役割を持ちながら、相互に関連し合っています。ミッションを上位概念とし、段階構造があると理解すると、3つの要素の違いが明確になります。
ミッションを実現するためにビジョンがあり、ビジョンを達成するためにバリューに基づいた行動が必要です。この3つが一貫性を持っていることで、組織全体に統一感が生まれます。例えば、「教育を通じて社会に貢献する」というミッションがあれば、「すべての子どもが平等に学べる社会の実現」というビジョンを設定し、「一人ひとりを大切にする」「継続的な学習」といったバリューで行動指針を示すことができます。
MVV導入がもたらす3つの主要なメリット
MVVを社内に浸透させることで企業活動のあらゆる側面に対してメリットをもたらします。特に、企業の中核を担う人事や経営企画部門にとって、そのメリットは実務上の効果として期待できます。MVVの導入がもたらす主な効果を3つ解説します。
意思決定の迅速化
MVVは企業が何のために存在し、どこを目指すのかを社内全体に示す共通の基準となります。この基準が明確になることで、経営層から現場の従業員まで、全員が同じ方向を向いて行動し、判断できるようになります。従業員一人ひとりが迷いなく迅速に判断を下せるようになることで、余計な確認やすり合わせの時間が減りスピーディーな意思決定が可能になります。
採用の向上・ミスマッチ防止
MVVの明確な価値観は、自社の考え方に合う求職者を集めるフィルターとして機能します。企業の価値観に合わない人は採用の段階で落とすことができ、求職者企業の価値観に共感した方が集まりやすくなります。結果として、入社後のギャップ低減やミスマッチ防止に繋がることで長期的に活躍しやすい人材の確保が可能になります。
従業員のエンゲージメント向上
MVVが明確になることで組織が目指す方向性が明確化され、自分の業務会社の目指す方向がどのようにつながっているのかを理解しやすくなります。仕事に対する意義や目的意識が高まることで、日々の業務に前向きに取り組めるようになり、会社に対する信頼感や貢献意欲が向上します。
MVVの作り方
MVVの策定は、単なる文言作りではありません。組織の現状を正しく把握し、関係者の想いを汲み取りながら、実践可能な形に落とし込むプロセスが重要です。ここでは、効果的なMVVの作り方を4つの段階に分けて解説します。
自社の現状と課題を整理する
MVV策定の第一歩は、自社の現状を客観的に把握することです。現在地を正しく認識しなければ、目指すべき方向性も定まりません。
事業領域と競合他社との位置づけ、組織の強みと弱み、企業文化の現状と課題、従業員のエンゲージメント状況、顧客や社会からの評価を詳細に分析します。SWOT分析による内外環境の整理や従業員アンケートによる組織風土の把握、顧客ヒアリングによるブランドイメージの確認などの手法を活用するのです。
経営層だけでなく、現場の管理職や若手従業員からも意見を聞き、多角的な視点から現状を把握することが重要になります。
ミッション・ビジョン・バリューを言語化する
次に、ステップ1の分析結果を踏まえて、MVVの各要素を言語化していきます。この段階では、抽象的な表現から具体的で実践的な内容へと段階的に落とし込んでいくことが大切です。
シンプルで覚えやすく、従業員が共感でき、具体的な行動をイメージできる表現にし、自社らしさが伝わる独自性のある内容を目指します。
ミッションは「なぜ事業をしているのか」から出発して、20〜30文字程度でシンプルに表現し、ビジョンは5-10年後の理想的な姿を魅力的に描き、バリューは日常業務で実践できる3-5個程度の行動指針に整理すると良いでしょう。
関係者とすり合わせながらブラッシュアップする
言語化したMVVを、様々な関係者と共有し、フィードバックを得ながら改善していきます。この段階が、MVV浸透の成否を左右する重要なプロセスです。
経営陣、部門責任者、現場リーダー、一般従業員代表、場合によっては顧客や取引先とのすり合わせを行います。
ワークショップ形式での議論やアンケートによる意見収集、少人数グループでの対話セッションなどを通じて、分かりにくい表現の修正や従業員の共感度向上を図るのです。
完璧を求めすぎず、80%の完成度で一度運用を始め、実践の中で改善していく姿勢が重要になります。
MVVを浸透・実践できる形に落とし込む
最後は策定したMVVを組織に浸透させるために、具体的な制度や仕組みに落とし込みましょう。
この段階で手を抜くと、MVVが「飾り物」になってしまうリスクがあります。
人事評価制度への組み込み、採用基準の明文化、新人研修カリキュラムの整備、社内コミュニケーションツールでの共有、行動指針マニュアルの作成などを実施します。
経営陣が率先してMVVを実践し、具体的な行動事例を積み重ね、定期的な振り返りと改善の機会を設け、MVVに基づいた成功事例を社内で共有することが成功のポイントです。
MVVを組織に浸透させるための具体的な方法
MVVを策定しただけでは組織は変わりません。重要なのは、いかに従業員一人ひとりの行動に落とし込み、日常業務の中で実践してもらうかです。ここでは、効果的な浸透方法を具体的に解説します。
MVVに触れる機会を増やす
MVVの浸透には、従業員がMVVに触れる回数を増やすことが重要です。一度の研修で終わらせるのではなく、継続的に接触する機会を作りましょう。
朝礼や会議でのMVV唱和、社内ポスターや掲示物での告知、名刺やメール署名への記載、社内報やニュースレターでの定期的な紹介、1on1ミーティングでのMVVに関する対話などの方法があります。
形式的な唱和ではなく意味を考える時間を設け、MVVに関連する成功事例を定期的に紹介し、従業員からのMVV体験談を募集・共有し、管理職がMVVについて語る機会を増やすことが効果的な運用のコツです。
評価制度や日常業務に組み込む
MVVを人事制度に組み込むことで、従業員の行動変容を促進できます。評価される内容が変われば、自然と行動も変わってきます。
人事評価では、MVVに基づいた行動評価項目の設定、360度評価でのMVV実践度チェック、昇進・昇格基準へのMVV要素の追加、表彰制度でのMVV実践者の表彰を行います。
業務では、プロジェクト企画時のMVV整合性チェック、商品・サービス開発でのMVV観点での検討、お客様対応マニュアルへのMVV反映、意思決定プロセスでのMVV基準の活用を実施しましょう。
過度に細かい評価は避け、MVV実践の失敗を責めるより挑戦を称賛する姿勢が重要になります。
ITツールの導入でより身近なものに
デジタル化が進む現代において、ITツールを活用したMVV浸透は非常に効果的です。社内SNSや社内ポータル、e-ラーニングなど、従業員が日常的に触れるツールにMVVの考え方を組み込むことで、特別な施策を設けなくても自然な形で浸透を図れます。
従業員にMVVの策定背景も含めて理解してもらい、たとえば日々の業務の中でMVVに沿った行動が見られた際に、その取り組みを社内SNSで共有・称賛したり、人事評価システムや表彰制度と連動させたりすることで、日常の行動や判断とMVVを具体的に結びつけていきます。
ITツールを活用することで、従業員が日頃からMVVを意識できる環境を効率的に整えることができるでしょう。
MVVの浸透に成功した企業事例
MVVは掲げるだけでは効果を発揮しません。実際に成果を上げている企業は、明確な方針の共有に加えて、日々の行動や制度とMVVを結びつける工夫を取り入れています。ここでは、MVVの浸透に成功した企業の取り組みをご紹介します。
スターバックスコーヒージャパン
スターバックスでは、MVVに類似するものとして、OUR MISSION、OUR PROMISE、OUR VALUEの3つを掲げています。
【OUR MISSION】
「最高」のコーヒー体験を届けるかけがえのない存在となり、人々の心を豊かで活力あるものにするために―ひとりのお客様、一杯のコーヒー、そしてひとつのコミュニティから
【OUR PROMISE】
- OUR PARTNER PROMISE:一人ひとりの心豊かな明日を
- OUR CUSTOMER PROMISE:心をこめた一杯を、つながりの瞬間とともに
- OUR FARMER PROMISE:コーヒーの未来を確かなものに
- OUR COMMUNITY PROMISE:仲間をつくり、前向きな変化を
- OUR ENVIRONMENTAL PROMISE:自然のめぐみをポジティブな循環へ
- OUR SHAREHOLDER PROMISE:たゆみなく永きにわたる成長を
【OUR VALUE】
- CRAFT ― 思いをかたちにする
- RESULTS ― 成果に責任をもつ
- COURAGE ― 勇気をもって向き合う
- BELONGING ― 互いを理解し、認め合う
- JOY ― 楽しむことを力に
これらを軸に、日々の接客や店舗運営を大切にしてきました。全国に店舗が増えるにつれて、従業員ごとに理念の受け取り方に差が出やすくなり、同じ価値観のもとで働き続けることが課題となっていました。
そこで、理念を日常の中で意識できる環境をつくるため、教育プログラムや共有の仕組みの見直しを進めました。具体的には、従業員が理念に紐づいた体験を言葉にして共有する「グリーンエプロンブック」、店舗ミーティングで理念に沿った行動を紹介し合う場の設定、相手の良い行動を認め合うピアレビューなど、取り組みを継続的に行っています。こうした取り組みを通じて、理念に沿ったエピソードが店舗間でも自然と共有されるようになり、従業員同士のつながりが強まっています。新しく入ったメンバーも、Mission・Promise・Valueを理解しやすくなり、店舗の雰囲気やサービス品質にも良い影響が出ている事例です。
Our Mission, Promises and Values|スターバックス コーヒー ジャパン
株式会社大京アステージ
全国約54万戸のマンション管理を担う大京アステージ社と穴吹コミュニティ社では、2社統合を見据え、2023年に共通のMVVを策定しました。
MVVの浸透にあたって、イントラネットや業務用のコミュニケーションツールの活用も考えたものの、社員同士の双方向のやり取りを活性化させたい点や、理念についての情報が埋もれてしまう懸念を考慮し、最適なツールを模索し始めます。
そこでMVVに関する発信や、従業員同士のやり取りの場として社内コミュニケーションアプリ「TUNAG」を導入しました。Valueに沿った行動を称え合う「Value称賛カード」や、役員のつぶやきなど、MVV身近に感じられたり、経営層との距離感を近づける仕組みを構築しました。
その結果、導入から10ヶ月で「MVVへの意識が高まった」と答えた従業員は7割を超え、1年間でやり取りされたValue称賛カードは3万枚以上にのぼりました。カードの送受信やコメントを通じて部署やエリアを越えたコミュニケーションが生まれ、理念に基づいた称賛文化が定着しつつあります。
MVVの浸透だけでなく、会社や他部署への理解が深まったり、日々の仕事への前向きな気持ちが高まったりと、従業員の働きがいにも良い影響が出ている事例です。
年間3万を超える称賛カードで理念が行き交う職場を実現。社員にMVVを浸透させた施策とは? | TUNAG(ツナグ)
MVVを活用して組織の一体感と成長を実現する
MVVは、単なる理念や標語ではありません。適切に策定し、効果的に浸透させることで、組織の一体感を醸成し、持続的な成長を実現するための強力な軸となります。
一方で、MVVの浸透は一朝一夕には実現できません。地道な取り組みを継続することで、少しずつ組織文化は変化し、従業員のエンゲージメントは向上します。結果として企業の競争力向上と持続的な成長につながっていくでしょう。
社長メッセージをメールで配信したり、掲示板にMVVを貼り付けたりする方法もありますが、従業員が日常的に触れる機会が少なく、自分ごととして捉えづらいという課題があります。そこで有効なのが、ITツールを活用した浸透施策です。情報浸透や双方向のやり取りができる社内SNSやWeb社内報、社内ポータルなどを活用することで、従業員一人ひとりが日常業務の中でMVVに触れる機会を自然に増やすことができます。
社内コミュニケーションアプリ「TUNAG」でMVV浸透を促進
株式会社スタメンが提供する社内コミュニケーションアプリ「TUNAG」では、MVVを浸透させるのに必要な機能や仕組みが整っています。
- サンクスカードで、MVVにマッチした行動を称賛する
- 日報をMVVと紐付け、毎日の行動でMVVを意識できるようにする
- MVVに関する社長メッセージを週に1回配信、全従業員にスピーディーに情報を届ける
といった取り組みが可能です。
こうした積極的な情報発信と、日常の何気ない業務の中にMVVを組み込む仕組みによって、従業員がMVVを身近に感じる習慣が育まれていきます。さらに、各施策の利用率や社長メッセージの既読率などをデータとして可視化できるため、感覚ではなく数値に基づいてMVV浸透の取り組みを改善・加速させることもできます。
組織の価値観や方向性に課題を感じている経営者や人事担当者の皆さんは、ぜひMVVの策定と浸透に取り組んでみてください。



.webp&w=3840&q=75)