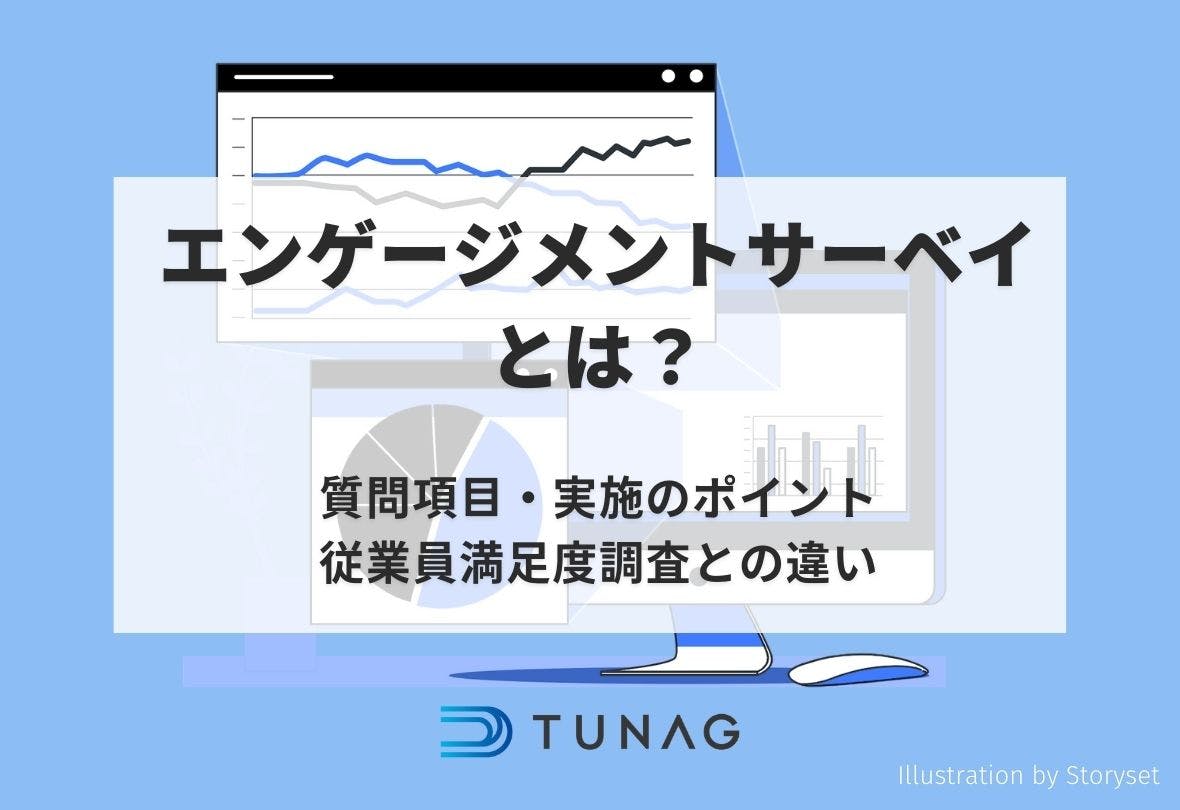従業員エンゲージメントを高めるには?効果や向上しない要因、施策まで徹底解説!
人材が定着しなかったり従業員のモチベーションが低かったりする原因は、エンゲージメントの低さかもしれません。エンゲージメントは、定着の促進やモチベーションを向上させる大きな要素です。エンゲージメントを高める具体的な取り組みを、向上の効果や阻害要因とともに解説します。
エンゲージメントを高める効果
ビジネスにおける「エンゲージメント」には、顧客エンゲージメントと従業員エンゲージメント(ワークエンゲージメント)があります。人材の定着や従業員のモチベーションに直接関わるのは、従業員エンゲージメントです。この記事ではエンゲージメントを「従業員エンゲージメント」として解説しています。
エンゲージメントを向上させると、どのような効果が得られるのでしょうか。実務的な観点から、定着率の向上、自発的な行動の促進、そして業績向上という三つの重要な効果について詳しく解説していきます。
定着率が上がる
エンゲージメントを高める効果として大きいのが、人材の定着率が向上することです。エンゲージメントとは従業員と企業の間にある「愛着」や「相互の関係性」など、深く結び付いた関係を意味します。従業員が企業に対して愛着を持つようになれば、離職率は自然と下がるはずです。
定着率が上がれば、苦労して採用・教育した人材が、組織で活躍する前に離職するリスクを下げられます。新しい人材を採用・教育することになると、二重にコストがかかります。エンゲージメント向上は、企業の損失を減らすことにもつながる取り組みです。
従業員が自発的に動くようになる
従業員が自ら企業のために動くマインドを持てるのも、エンゲージメントを高める効果です。エンゲージメントが高い従業員は、自分の仕事に対して情熱を持ち、企業の目標達成に向けて積極的に貢献しようとします。これは管理職にとって、チームの生産性向上やマネジメントの効率化といった実務的なメリットにもつながります。
エンゲージメントが高い従業員の特徴は、企業やチームの一員としての自覚を持っていること、企業の成功に貢献したいと思っていることです。このような心理状態で働く人々は、指示待ちではなく自ら課題を発見し、解決に向けて行動します。
業績・生産性の向上につながる
従業員のエンゲージメントは、企業の業績と密接な関係があると考えられています。自発的で意欲の高い従業員が多ければ積極的な営業活動やイノベーションが促され、離職率が低ければ人員の交代によって顧客満足度を下げる心配も少ないでしょう。このように、従業員のエンゲージメントと企業の業績には強い相関関係があると考えられます。
生産性の面でも大きな効果があります。エンゲージメントの高い従業員は、企業の成功に貢献したいという強い意識を持っているため、効率的な業務遂行を自然と心がけます。時間当たりの付加価値が向上し、残業時間の削減にもつながるでしょう。
エンゲージメントが上がらない要因
単発の施策を実施しても、すぐにエンゲージメントが高まるとは限りません。企業や組織そのものにエンゲージメントの向上を阻害する要因があると、施策の効果が得られないばかりか、逆に低下する可能性もあります。要因として挙げられる要素を見ていきましょう。
現代にそぐわない制度や慣習がある
現代では、人材の働き方に対する価値観は大きく変化し、終身雇用制度も崩壊しつつあります。その中で古い価値観に基づく制度を維持していると、従業員のエンゲージメント向上を妨げる一因となります。特に、新しい働き方を求める若手層の離職リスクを高める可能性があります。人事部門や経営層は、自社の制度が時代に適合しているか見直す必要があります。
例として挙げられるのは、勤務時間の完全固定や実力を無視した年功序列型の賃金制度などです。効率を重視する現代においては、形式だけの会議や不要な書類の提出など、慣習に基づく業務もエンゲージメントの向上を妨げる要因となり得ます。
組織形態が複雑で非効率な業務が発生している
組織形態が複雑化すると、管理者が多くなって連絡系統の混乱が生じたり、無駄な承認が多くなったりして非効率が生じます。効率の悪い業務は生産性の向上も期待できない上、従業員にとって大きなストレスとなるでしょう。
働く上でのストレスが多ければ、エンゲージメントの向上は期待できません。組織形態をすぐ変えることは難しいとはいえ、非効率を減らす仕組みづくりは工夫次第で可能です。
トップダウンで部下が自発的に行動できない
従業員エンゲージメントの向上には、自発的に行動・挑戦して成功体験を得る機会が必要です。
強いトップダウン文化がある組織では、従業員は失敗を恐れて新しい挑戦を避ける傾向があります。指示されたことだけを実行する受動的な姿勢が定着すると、イノベーションが生まれにくくなり、組織の競争力も低下します。
特に若手従業員は成長機会を求めているため、自発性を発揮できない環境では離職リスクも高まるのです。
適切な権限委譲と、失敗を許容する組織文化の醸成により、従業員の自発性とエンゲージメントを同時に向上させることができるでしょう。
従業員が自身の成長を感じにくい
組織に対するエンゲージメントの向上には、そこで自らが成長できているという実感や達成感が欠かせません。自分がした仕事が成長につながっているのか、何かに貢献しているのか見えにくいとエンゲージメントが向上しません。
キャリアパスが見通せない環境も、キャリアアップの道筋が見えず不安になり、エンゲージメントが低下します。特に終身雇用の崩壊によってキャリア構築が自己責任とされがちな現代日本では、キャリアパスの不透明さはエンゲージメント向上の阻害要因として大きいでしょう。
エンゲージメントが低いと起こる問題
エンゲージメントが低い状態を放置すると、企業にとって深刻な問題が発生します。これらの問題は相互に関連し、負のスパイラルを生み出す危険性があります。
ここでは、エンゲージメントの低下が引き起こす三つの重大な問題について、経営視点から詳しく解説します。
優秀人材の流出による組織力の低下
エンゲージメントが低い組織では、優秀な人材から順に離職していく傾向があります。市場価値の高い人材ほど転職の選択肢が豊富であり、魅力のない職場に留まる理由がないためです。この優秀人材の流出は、組織の競争力を根底から揺るがす深刻な問題となります。
優秀な人材の離職は、単なる人員減少以上の影響をもたらします。彼らが持つ専門知識やノウハウ、顧客との関係性も同時に失われるのです。さらに残された従業員への負担が増加し、彼らのエンゲージメントも低下するという悪循環に陥るでしょう。
人材の質の低下も避けられません。優秀な人材が去った組織は採用市場での魅力も低下し、質の高い人材の獲得が困難になります。結果として組織全体の能力が低下し、中長期的な成長戦略の実現が困難になってしまうのです。
負の連鎖による組織文化の劣化
エンゲージメントの低下は、組織文化そのものを蝕んでいきます。やる気のない従業員が増えると、職場に「どうせ頑張っても無駄」という諦めの雰囲気が蔓延します。この負の組織文化は、新入社員や中途入社者にも伝染し、組織全体が停滞してしまうのです。
特に深刻なのは、「静かな退職」と呼ばれる現象の広がりです。従業員は形式的には在籍していても、最低限の業務しかこなさず、創造的な貢献を一切しなくなります。会議では発言せず、改善提案も出さず、ただ時間を過ごすだけの従業員が増えていきます。このような状態では、組織の活力が失われ、変革や改善が不可能になるでしょう。
組織文化の劣化は、採用活動にも悪影響を及ぼします。SNSや転職サイトでの評判が悪化し、企業ブランドが毀損されます。優秀な人材は入社を避けるようになり、人材獲得競争でますます不利な立場に追い込まれてしまうのです。
市場競争力の喪失と事業継続リスク
エンゲージメントが低い企業は、急速に変化する市場環境への対応力を失います。従業員が受動的で、新しい挑戦を避ける組織では、デジタル変革や事業モデルの転換が進みません。競合他社が革新的なサービスを次々と投入する中、取り残されていくことになるでしょう。
特にサービス業では、サービスの品質や従業員の態度が直接的に顧客体験に影響するため、致命的な問題となるのです。
最終的には、事業継続そのものが危ぶまれる状況に陥ります。エンゲージメントの低下を軽視していた企業が、数年後には市場から退場を余儀なくされるケースも少なくないのです。
エンゲージメントを高める取り組み
向上の効果や低下による問題を把握できると、エンゲージメントを高める取り組みの重要性を一層強く実感するでしょう。では具体的に、どのような取り組みがエンゲージメント向上につながるのでしょうか。
まずはエンゲージメントサーベイで組織課題を特定する
エンゲージメントを高めるには、まず現在従業員が企業・組織のどこに不満を持っているか、つまりエンゲージメントにおける組織課題を明確にする必要があります。組織課題に合わない施策は効果がないばかりか、かえって従業員の不満を招く恐れがあるためです。
組織課題の特定には、エンゲージメントサーベイや社内アンケートツールの活用が有効です。これらのツールを利用することで、従業員のエンゲージメント状態を客観的なデータとしてスコアリングできます。
例えば、組織のためのエンゲージメントサーベイ「TERAS」は、従業員が本音を回答しやすいように設計されています。回答は完全匿名であり、ログインや煩雑な手続きも不要なため、従業員の心理的安全性を確保したうえで忖度のない意見を集めることが期待できます。
また、スマートフォンから5分程度で手軽に回答できるため、従業員の負担を最小限に抑えながら、精度の高いサーベイを実施することが可能です。
組織のビジョンやミッションを共有する
ビジョンやミッションは、組織の価値観や目指す方向性を示すものです。エンゲージメントの要素「企業への理解・共感」には、ビジョン・ミッションの共有が求められます。企業・組織の価値観や方向性は、従業員が自分の役割を理解し、組織の目標に共感するための基盤です。
ビジョンやミッションを共有すれば、従業員が企業への理解を深め、向かう方向を一つにして業務に取り組めるようになります。結果としてエンゲージメントが向上するということです。
柔軟な働き方ができるよう制度を見直す
職場環境の柔軟性を高めて従業員のワークライフバランスを支援することは、エンゲージメントを向上させる重要な施策です。自分の状況に応じた働き方を実現できるようになれば、従業員は企業に感謝の気持ちや信頼感を抱き、エンゲージメントが向上します。
また従業員が一人一人の実力を発揮して業績に貢献するためにも、ワークライフバランスや働く環境が自身にとって整っていることが重要です。柔軟な働き方を実現する制度には、次のようなものがあります。
- 在宅勤務やサテライト勤務などのリモートワーク制度
- フレックスタイム制
- 時短勤務
柔軟な働き方を実現するには、組織風土の見直しも欠かせません。本来は定時で帰れる状態でも上司の残業中は残らなければならない、家庭や自身の重要な都合で休暇を取得することに否定的な雰囲気があるなら、早急な意識改革が必要です。
公平性のある評価制度を設ける
評価(人事考課)の制度も、エンゲージメントを左右する要素です。自らの働きぶりに応じて適切な評価を受けられれば、満足度が高まりエンゲージメントが向上します。
評価は公平であることが大前提です。評価する人の好みや個人的感情による評価は、エンゲージメントを下げる要素になり得ます。公正な評価に必要な軸は、次の3種類です。
- 業績考課(成績考課):プロセスではなく、数値として確認できる結果を評価する
- 能力考課:数値化しにくい知識や能力・プロセス(判断力や企画力・交渉力など)を評価する
- 情意考課(態度考課):仕事に対する姿勢・勤務態度(規律性や積極性・チームワークなど)を評価する
上記の軸をベースに、評価制度を見直してみましょう。どの軸を重視するかは、企業の性質(成果主義的かどうか)や評価対象者の勤続年数などによって変わります。
業務を効率化できるツールを導入する
業務の非効率は従業員のストレスとなり、エンゲージメントの向上を阻害します。組織形態の複雑さは短期間で改善できませんが、ツールの導入は比較的すぐに実施できる対策です。業務効率化に貢献するツールとして、ワークフローシステムや勤怠管理システム・SFA・CRMなどが挙げられます。
また、エンゲージメントツールの中には、単にエンゲージメントサーベイを実施できるだけでなく、「TUNAG(ツナグ)」のようにワークフローや日報など業務効率化に役立つ機能を内包するものもあります。エンゲージメント向上を考えているなら、TUNAGのようなツールの検討も一つの選択肢です。
自発的な発信が可能なコミュニケーション環境をつくる
エンゲージメントと自発性は、相互に作用します。エンゲージメントを高めるには、従業員の自発性の向上が欠かせません。自発的な行動の第一歩として、「自分で情報を発信する」ことが挙げられます。
立場を超えたコミュニケーションが活発にできれば、若手も自然と発言機会が増えて情報を発信する癖がつくでしょう。結果として自発性とエンゲージメントの向上が期待できます。
また、社内コミュニケーションの活性化には、職場の一体感や信頼関係を深める効果があるのも一つの理由です。例えばチームビルディング活動や社内イベントの開催で従業員同士のつながりが強まり、働きやすい職場環境が醸成されれば、エンゲージメントは高まります。
ただし、業務に関係のないイベントをストレスに感じる従業員も少なくありません。業務に支障がないのであれば、イベントのような業務外の活動は任意参加としましょう。
社会貢献や事業の状況を共有する
自分が何のために仕事をしているのか分からないと、エンゲージメント向上に必要な自発性が育ちません。従業員の自発性や意欲を引き出すためにも、社会貢献や事業の状況を可視化して共有しましょう。
自らの仕事がどのように役立っているのかが分かれば、従業員が仕事に意義を見いだせるようになります。特に仕事に社会的意義を求める従業員にとって、社会貢献状況の共有はエンゲージメント向上に効果的です。
事業状況の共有は、従業員が自分の役割を明確に認識するのに役立ちます。今後何をすべきか・どのような役割が求められているのかが分かれば、自発性が高まりエンゲージメントも向上します。
従業員の自己成長を支援する
従業員が自己成長できる環境の提供は、エンゲージメント向上に直結します。自己成長を促すことで、従業員は自身の成長を実感し、仕事に対する意欲を高めるでしょう。
自己成長の支援として企業ができることとして、次のような施策が挙げられます。
- 研修を実施する
- 新たな業務を任せてみる
- 目標を設定し、達成状況の進捗を管理する
- 定期的な面談で業績や業務姿勢をフィードバックする
業務外でできる知識やスキルの習得には、成長につながる講座の費用支援なども効果的です。業務内で可能な支援として、新たな業務へのアサイン・目標設定と進捗管理・面談によるフィードバックが考えられます。いずれも仕事をしながら、自己成長とその実感を促すことが可能です。
キャリアパスを明確にする
従業員が自らのキャリアパスを明確に認識できれば、モチベーションが高まり、エンゲージメントの構成要素である「帰属意識」が強まります。キャリアパスが明確だと努力がどう報われるかが理解しやすくなり、積極的に仕事に取り組むことが可能です。
社内におけるキャリアパスの明確化は、「この企業で長く働きたい」という気持ちにもつながります。キャリアパスを提示されることで、従業員が企業から長く勤めることを期待されていることが分かるためです。
また、管理職だけでなく、専門職としてのキャリアパスも重要です。全員が管理職を目指すわけではなく、専門性を極めたい従業員も多くいます。複線型のキャリアパスを用意することで、多様な人材が活躍できる環境を整備できます。社内公募制度や異動希望制度も、キャリア形成の選択肢を広げる有効な施策です。
定期的な1on1を実施する
定期的な1on1ミーティングの実施も、エンゲージメントを高めるために必要な取り組みです。1on1では従業員と上司の間でオープンにコミュニケーションを取り、課題や目標のフォローアップをします。従業員一人一人に丁寧に向き合う場となるため、エンゲージメント向上の阻害要因となっている不満・不安の解消が可能です。
同じ部署の上司相手だと言いにくい問題を抱えている場合、他部署の上司との1on1を実施する方法もあります。部署内の業務については相談できませんが、部署内では相談しにくい事柄も打ち明けやすいでしょう。
1on1を実施する際は、記録を残しておくのがおすすめです。次回の1on1で前回の記録を参考に、どう変わったかをフィードバックできます。
エンゲージメント向上ツールの選び方
エンゲージメント向上には多角的なアプローチが必要であり、すべての施策を手作業で実施するのは現実的ではありません。効率的にエンゲージメント向上を実現するには、適切なツールの活用が不可欠です。
ここでは、数多く存在するエンゲージメントツールの中から、自社に最適なツールを選ぶための三つの重要なポイントを解説します。
目標を達成できる機能の有無をチェックする
エンゲージメント向上を目的にツールを導入するといっても、その前段階として設定するゴールは企業の課題によって変わります。例えばコミュニケーション活性化が課題なら、社内SNSやチャット機能が充実したツールが適しています。業務効率化が目的なら、ワークフローやタスク管理機能が重要です。
多くの企業では複数の課題を抱えているため、統合型のプラットフォームを選ぶケースも増えています。ただし、機能が多すぎると使いこなせない可能性もあるため、優先順位を明確にすることが大切です。
まずエンゲージメント向上のための中間目標を立てて必要機能を書き出し、その目標を達成できるツールを選びましょう。必要機能があまりに多く予算に合わなそうなら、優先順位付けをして絞り込みます。
従業員・管理者双方の使いやすさを考慮する
エンゲージメントツールの成功は、従業員の利用率に大きく依存します。どんなに高機能なツールでも、使いにくければ定着しません。現場の従業員と管理者の両方にとって使いやすいツールを選ぶことが、導入成功の必須条件です。
従業員の視点では、直感的なインターフェースと簡単な操作性が重要です。特に製造現場やサービス業など、PCを日常的に使わない従業員も多い企業では、スマートフォンアプリの充実度が選定のポイントとなります。ログインの手間を減らすシングルサインオンや、既存システムとの連携機能も、利便性を高める重要な要素でしょう。
現場の従業員だけでなく、管理する側の使いやすさも考慮しましょう。管理画面が分かりにくかったり、管理に手間がかかったりするツールだと、管理する人材のエンゲージメントが下がってしまいます。
サポート体制について確認する
ツール導入後の成功は、ベンダーのサポート体制に大きく左右されます。特にエンゲージメント向上は長期的な取り組みであるため、継続的なサポートが受けられるかどうかが重要です。契約前にサポート内容を詳細に確認することが、後々のトラブルを防ぐことにつながります。
導入初期は操作方法のような基本的なサポート、定着期にはエンゲージメント向上の支援を提供しているサービスがベストです。サポート体制はツールによって大きく違います。Web上の公式情報で具体的に把握できなければ、資料請求や問い合わせをしましょう。
エンゲージメント向上を支援するクラウドサービス「TUNAG」
エンゲージメント向上をサポートするツールの一例が、組織改善クラウドサービス「TUNAG(ツナグ)」です。特徴を見て自社の課題に合うと思ったら、ツールの候補に入れてみてください。TUNAGの概要が分かる特徴・強みを四つまとめました。
組織課題に合わせて必要な施策をカスタマイズできる
企業の組織課題や目指すべき組織像は、100社あれば100通りあります。最適なエンゲージメント向上施策は企業によって当然変わってくるでしょう。TUNAGはリアルタイムな組織状態に合わせて、自社用に施策をカスタマイズできます。
施策の設計・実施、さらに「社内アンケート」のような分析機能から社内制度の効果を分析することで、エンゲージメントを高める施策のPDCAサイクルを回し続けることが可能です。
日常的に使うツールとしての豊富な機能を搭載している
エンゲージメント向上や組織課題解決のための施策を設計しても、従業員が認識した上で活用できなければ意味がありません。TUNAGは社内掲示板やワークフロー・社内チャットなど、従業員が日常的に使うツールとしての機能も豊富に備えています。
そのため従業員のログイン率が高く、TUNAG内で共有されている社内制度や企業からのお知らせが自然と目に留まりやすいでしょう。エンゲージメント向上の取り組みは、従業員に認知されてこそ効果を発揮します。
組織状態をリアルタイムに把握できる分析機能がある
組織や企業の状態は常に変化します。エンゲージメントを高める施策は、定期的に成果や課題を把握して改善していかなければなりません。
TUNAGの分析ダッシュボードでは、施策の効果や従業員のエンゲージメント状態を可視化し、改善ポイントを見つけることが可能です。取り組みを改善する方向性を決めやすくなり、エンゲージメント向上の成功に近づきます。
使いやすさやサポート体制にも強みがある
TUNAGにはスマホアプリもあり、仕事でPCを使わない従業員でも手軽にアプリを使えます。マニュアルのチェックや日報の報告もスマホアプリから可能です。
管理者の視点では、設計の自由度が高いにもかかわらず、自社の取り組みをノーコードでカスタマイズできます。Webツールに慣れていなくても簡単に操作できるでしょう。もし操作に困ったときも、サポートを頼れます。
TUNAGでは、主に操作手順などの悩みをサポートする「初期サポート」、施策の効果から改善提案を実施する「運用支援」を用意しています。専任サポートがつくため、ツール導入に不安がある企業にもおすすめです。
TUNAG導入によるエンゲージメント向上の成功事例
TUNAGの導入でエンゲージメント向上に成功した事例に、株式会社BPのケースがあります。ウェディング事業を中心としてサービスを展開する株式会社BPでは、業務が多様化しセクションも増える中で、誰が誰を承認すればよいのか分かりづらく、連帯感にも課題がありました。
そこで導入を考えたのが、スマホで簡単にサンクスカードを送れるエンゲージメントプラットフォーム「TUNAG」です。同社ではTUNAGを導入し、従業員がサンクスカードを送り合いやすい仕組みを構築しました。サンクスカードを送った数・もらった数で評価し社内表彰する体制をつくり、日常的に称賛し合う文化を築けています。
アルバイト従業員が1,000人を超える同社では、新人アルバイトの日報に先輩スタッフから称賛のコメントを送って努力を評価するなど、会社を挙げて従業員同士が称賛する文化の醸成に取り組みました。その結果、アルバイトの定着率が30%改善されています。またエンゲージメント向上によってリファラル採用が進み、3カ月で300人のアルバイト採用を実現した時期もありました。
関連記事:アルバイト定着率が30%改善、3ヶ月で300名採用:BPが「友達に紹介したくなるバイト先」を作るまで
エンゲージメントを高めて一体感ある強い組織に
従業員と企業の間の関係性を示す「エンゲージメント」は、高めることで定着率や自発性・業績の向上など企業にとってプラスの効果が多くあります。逆にエンゲージメントが低いと、離職者が増えてコストがかさんだり、従業員のモチベーションが下がったりします。
エンゲージメント向上に効果的な施策は、企業の課題によってさまざまです。加えて多角的なアプローチが必要なので、効率的に進めたいならツールを導入するのが現実的かもしれません。TUNAGのように日常業務にも使う機能も備えたツール上で取り組みの情報を発信すると、従業員に注目されて施策の効果を最大化しやすくなるでしょう。